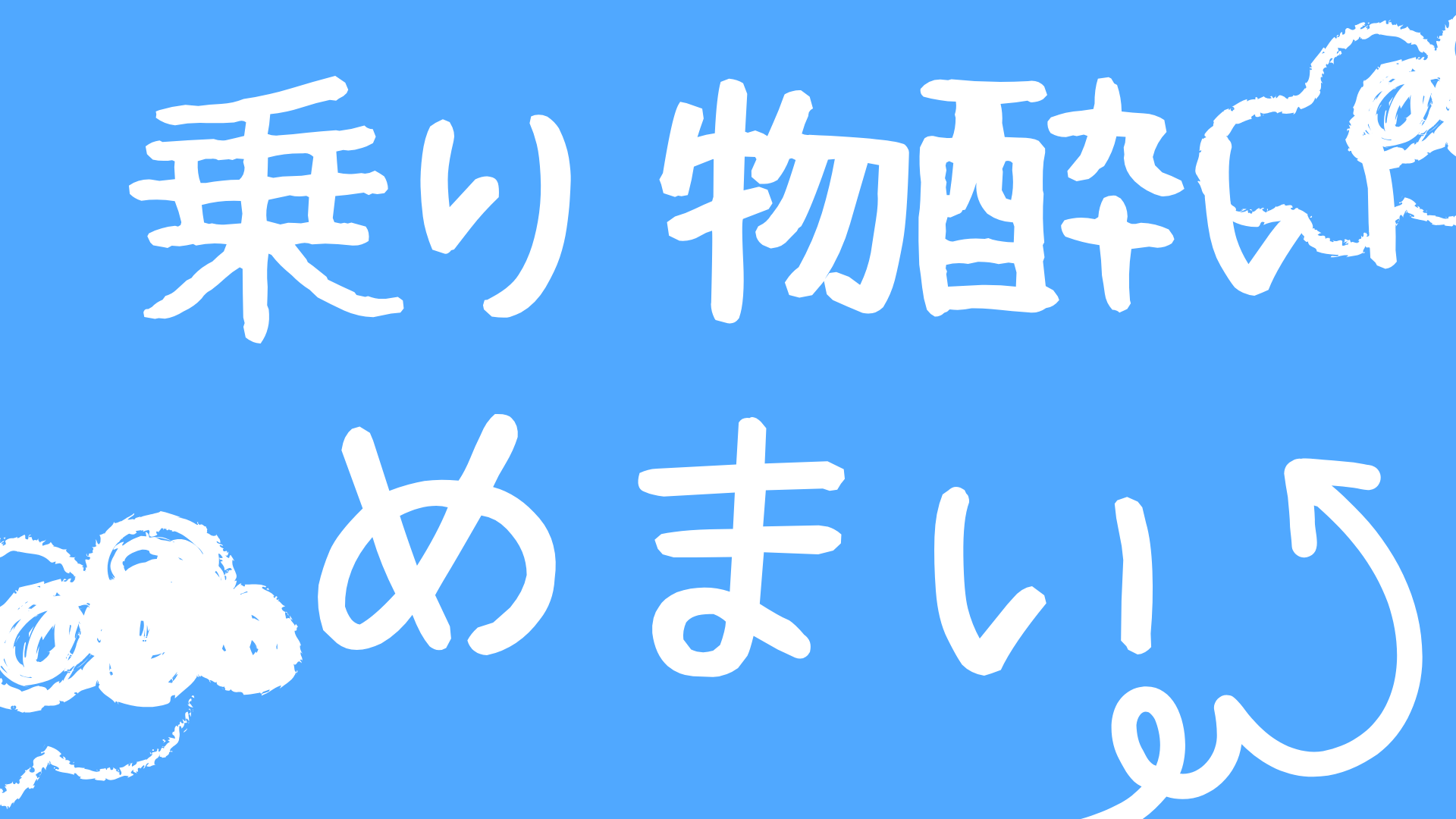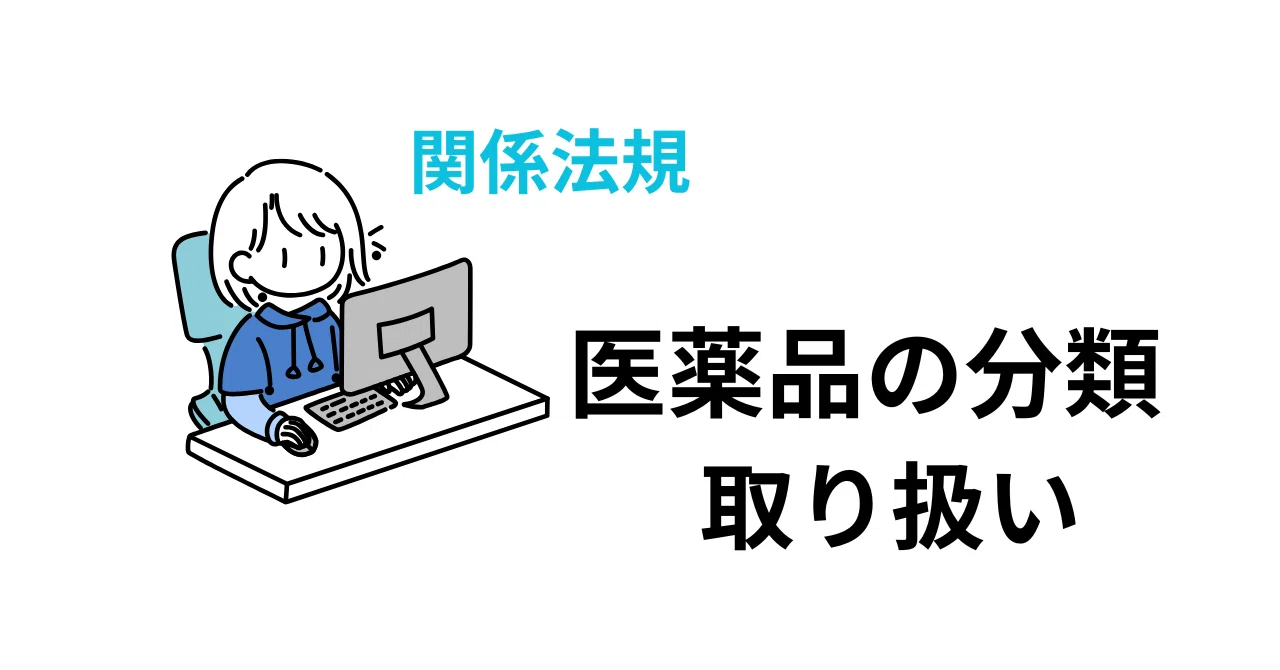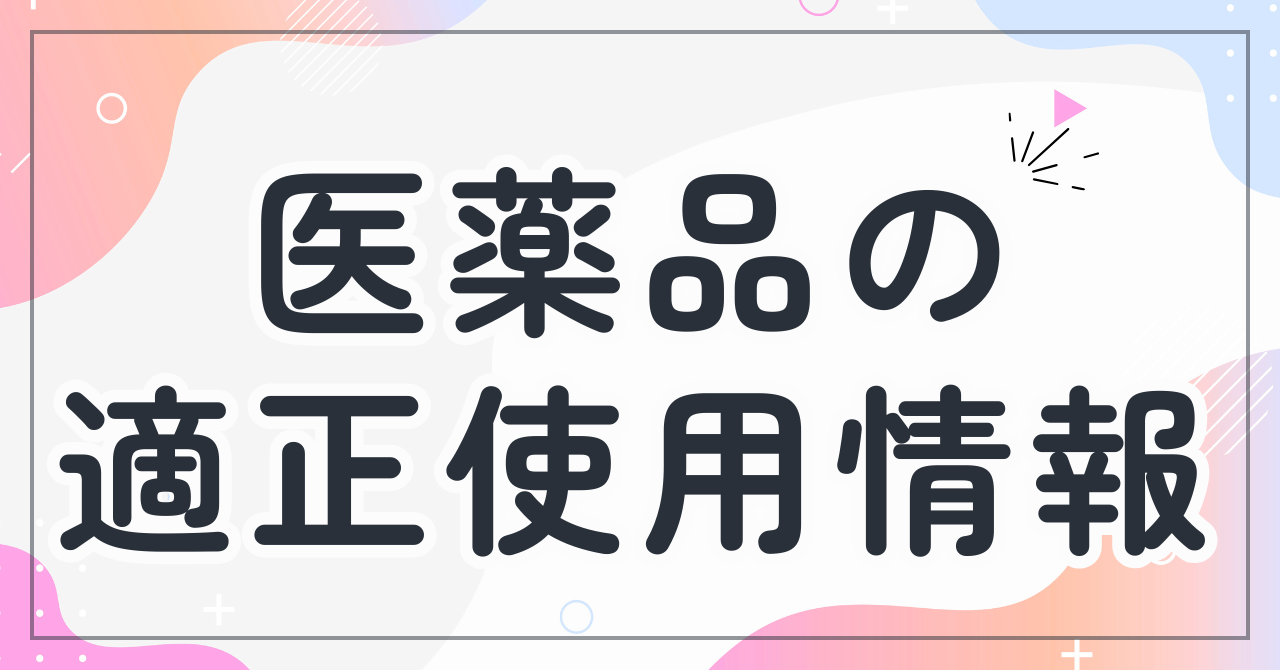登録販売者試験#18検査薬

一般用検査薬とは?
■ 一般用検査薬と体外診断用医薬品の違い
• 体外診断用医薬品:医療機関での診断補助を目的として使われる
• 一般用検査薬:一般消費者が自身の健康状態を把握するために使用するもので、薬局や登録販売者が販売可能
⸻
■ 一般用検査薬の目的と特徴
• 日常生活者が使用し、異常の早期発見・受診につなげる
• 対象となる項目:尿、糞便、唾液、鼻汁、涙液など(体液や分泌物)
• 疾患の診断確定ではなく、受診のきっかけを与えるもの
• ガン、遺伝的素養など、重大な疾患の診断を一般用検査薬には認めていません
⸻
■ 販売時に説明すべき注意点
以下の点は必ず説明が必要です:
• 診断目的で使用するものではない
• 検査薬の採取時期とその重要性
• 性能(感度・特異度)の限界
• 使い方や保管方法
• 妊娠・持病・薬剤が結果に与える影響
• 判定後の対応と受診勧奨
医療のプロが採取して検査するわけではないため、そもそも採取量が適切かも分からない状況での結果が、もしかしたら陰性を示し、その後実は陽性だったのに何らかの混入や反応がされずに…
という事もあります。
これを偽陰性と言います。
その逆に、偽陽性というのもありこれは医療現場でもある程度の確率で起こりうるものなので、一般用ではもっと確率は上がると考えて下さい。
確定診断できるものではないため、適切な受診が必要である事は伝える必要があります。
尿糖・尿タンパク検査薬
■ 異常値の原因
• 通常、糖分やタンパク質は腎臓で再吸収されるため、尿中には出ない
• 高血糖状態(糖尿病)や腎障害(ネフローゼ症候群、腎盂腎炎など)で異常値が出る
• 尿路異常(感染、結石、脱水など)でも検出される
■ 検査時の注意点
| 項目 | 内容 |
| 容器の汚れ | 検査対象物質が付着していると誤判定の原因に |
| 採尿のタイミング | 尿糖:食後1〜2時間、タンパク:起床後の尿(早朝尿)が適している。 運動後などは筋肉が分解されタンパク尿が出やすかったりする。 |
| 採尿の仕方 | 中間尿を採取するのが望ましい(最初の尿は混入物が多い) |
| 検体の取り扱い | 時間が経つと分解・変質するため採取後すぐに検査 |
| 検査薬の保管 | 直接手で触れないこと、湿気に注意 |
| 食事や薬の影響 | 尿は弱酸性が通常だか、食事によって変動する。また、ビタミンC(アスコルビン酸)や特定薬剤により誤判定の可能性あり |
■ 判定と受診勧奨
• 陽性=病気であるとは限らない。医師の診断が必要
• 陰性でも、症状が続く場合は受診をすすめる
• 一般用検査薬は、診断確定ではなく異常の目安として使う
妊娠検査薬
■ 妊娠の早期発見の意義
• 妊娠12週までは胎児が外的影響を受けやすいため、早期発見が重要
• 食事や薬の制限、飲酒・喫煙・感染症対策など、母体の健康管理が必要になる
⸻
■ 検査の原理と影響する要因
• 妊娠すると、胎盤からhCG(ヒト絨毛性ゴナドトロピン)が尿中に分泌される
• 月経予定日から1週間後以降が推奨時期(早すぎると陰性に出ることも)
•妊娠が成立してから4週目前後の尿中hCG濃度が目安とされている。
⸻
■ 検査結果に影響する要因
| 要因 | 内容 |
| 検査の時期 | 排卵後すぐなど、hCGの濃度がまだ低い時期は陰性に出やすい。月経後1週以降。 |
| 尿のタイミング | 早朝尿が最適(hCGが濃縮されている) |
| 検査薬の保存・取り扱い | 温度管理が重要。高温・低温で正確な反応が得られない |
| 混入物質 | 汚れや不純物があると誤反応が起きる可能性あり |
| ホルモン剤の使用 | hCGに影響する不妊治療薬、ホルモン療法で誤判定の可能性も |
| ホルモン分泌異常 | 何かしらの疾患の影響で、hCG分泌されており反応することがある。(多くの場合腫瘍による) |
■ 判定と受診勧奨
• 妊娠検査薬は妊娠の有無を診断するものではない
• 陽性でも異常妊娠(子宮外妊娠など)の可能性あり
• 陰性でも生理が来ない、実は妊娠の可能性あり。症状がある場合は医師の受診を促す(無月経症など)
登録販売者として、一般用検査薬を販売する際は、以下のような姿勢が求められます:
• 検査薬の限界を理解し、誤解を招かない説明
• 適切な受診勧奨
• 判定結果を過信しないよう伝える配慮
知識に加えて、患者様の不安に寄り添う接客力も大切です。
 | 2025-26年版 登録販売者 合格のトリセツ テキスト&一問一答問題 (登録販売者合格のトリセツシリーズ) [ 東京リーガルマインド LEC登録販売者試験対策プロジェクト ] 価格:2860円 |
外用薬の抗ヒスタミン成分
(虫さされ、湿疹用クリーム,点鼻薬など)
“かゆみ止め”でも副作用が出る!?塗った場所が腫れることも。
抗ヒスタミン成分とは?
抗ヒスタミン成分は、体内でアレルギー反応を引き起こす物質「ヒスタミン」の働きを抑えるものです。
主に以下のような症状を軽減するために使われます:
• かゆみ(掻痒)
• 赤み(紅斑)
• 腫れ(腫脹)
• 湿疹や蕁麻疹
市販薬では、「ジフェンヒドラミン」「クロルフェニラミン」などが外用剤として使われています。
外用薬でも副作用が出ることがある?
「塗り薬だから安心」と思っていませんか?
抗ヒスタミン薬は、確かに皮膚のヒスタミン反応を抑え、炎症やかゆみを軽くしてくれます。
しかし、まれに以下のような副作用が出ることがあります。
• 塗布部位の腫れ
• 発赤(赤み)
• 発疹やかゆみの悪化(接触性皮膚炎)
• 水疱ができることも
特に以下のような使い方では注意が必要です:
• 長期間使い続けている(長期連用)
• 広範囲に使用している
• 他の外用薬と併用している
• 日光に当たる部位に使っている(光接触皮膚炎)
患部のヒスタミン反応を抑えて炎症を軽減する一方で、まれに塗布部位に腫れや発疹などの過敏症状が出ることも。特に長期連用や、広範囲に塗布する場合には注意が必要です。
原因がアレルギーなのか、真菌(カビ)感染なのかによって治療薬は大きく変わります。
市販のかゆみ止めを漫然と使い続けることで、症状が慢性化したり、逆に悪化するケースも少なくありません。