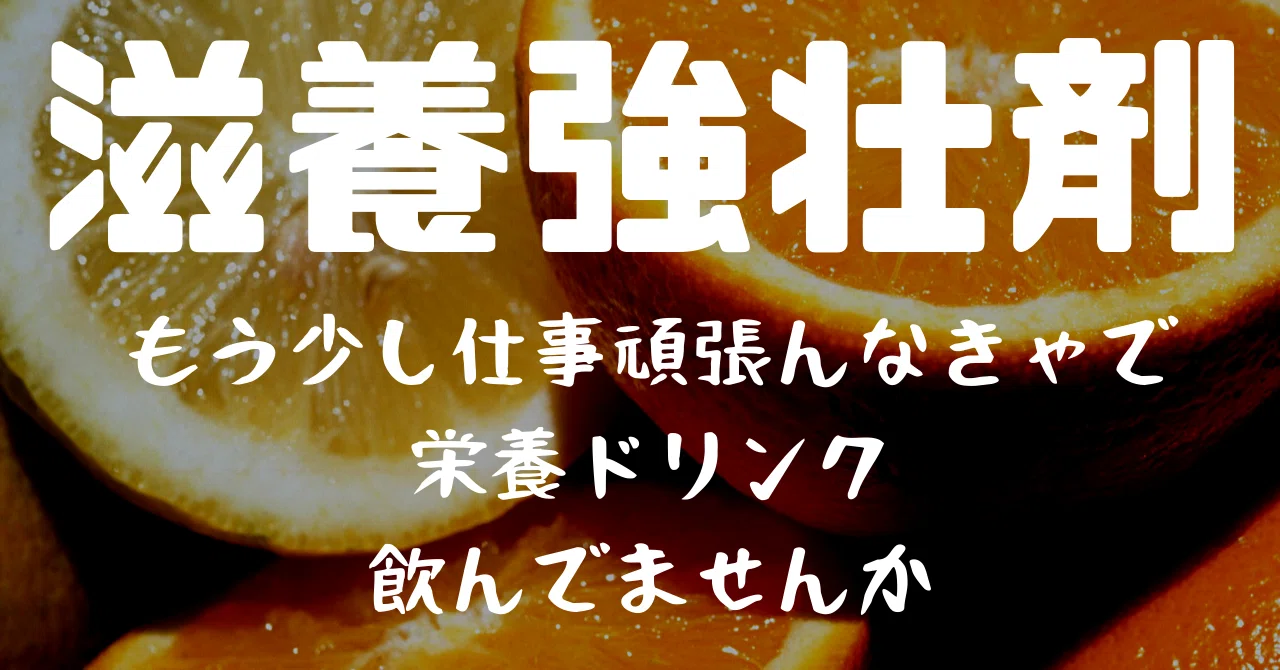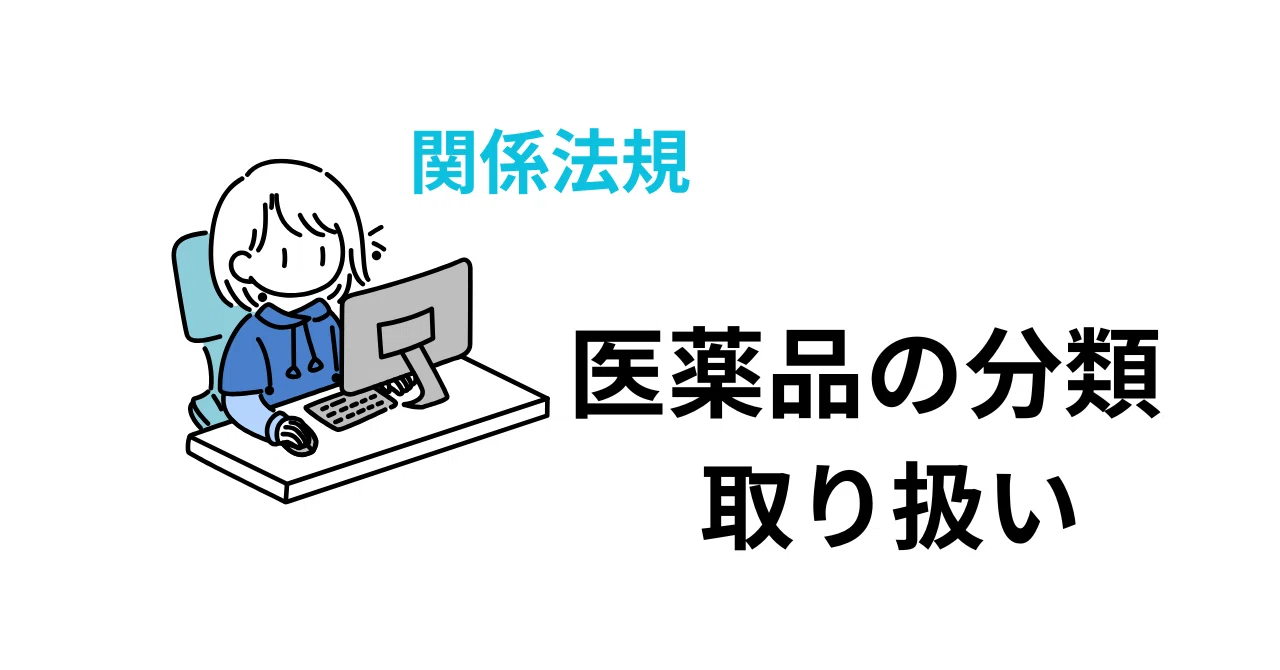登録販売者 関係法規#6第1・2・3類

第1類・第2類・第3類と別々に書こうと思いましたが、別々に書くのややこしいものの全体像がはっきりしませんでした。
重なる事が多いのでまとめて、違う部分を覚えればいいのかなと思います。
薬局や店舗販売業者が第一類医薬品を販売する際には、購入者が適切に使用できるように薬剤師による情報提供が義務付けられています(薬機法 第159条)。これは、配置販売業にも適用されます。
情報提供には、**書面(説明文書)**を使い、使用法や注意点などを丁寧に伝える必要があります。
情報提供の義務
• 薬剤師のみが情報提供を行うことが義務。
• 書面を用い、対面で販売前に情報提供を実施。
• 購入者が内容を理解したこと、質問がないことを確認。
情報提供の努力義務
• 薬剤師または登録販売者が対応可能。
• 必要に応じて、購入者の症状や背景を確認。
• 疑問がないか、理解しているかを確認。
書面の記載事項(任意)
• 名称、有効成分、用法・用途、効能、注意点など。
指定第2類医薬品に関する措置
• 小児・妊婦・高齢者などに注意が必要。
• 依存性・習慣性がある成分を含むケースもある。
• 陳列方法・表示方法にも配慮し、注意喚起が求められる。
(購入するものが、副作用や禁忌を確認し、相談できる事が購入者自身に認識できるように陳列する必要がある)
• 情報提供が不十分な場合は、販売しないことも検討すべき。
情報提供について
• 情報提供は「望ましい」とされている(努力義務)
• 購入者からの相談があった場合など、必要に応じて対応。
情報提供の方法(8つのポイント)
1,情報提供場所を設ける(相談カウンター)情報提供及び指導を行う。
2,医薬品の適正な使用のために必要な情報(用法・用量、併用薬の確認、副作用、保管法など)を個別に提供。
3,他の医薬品の併用や副作用の有無も確認。
4,服薬指導に薬手帳を活用。
5,疑わしい副作用があった場合は対応方法も説明。
6,内容を理解できたか、質問の有無。確認。
7,必要に応じて、医師への受診勧奨も行う。
8,情報提供を、行なった薬剤師名を伝える。(或いは2類は登録販売者名)
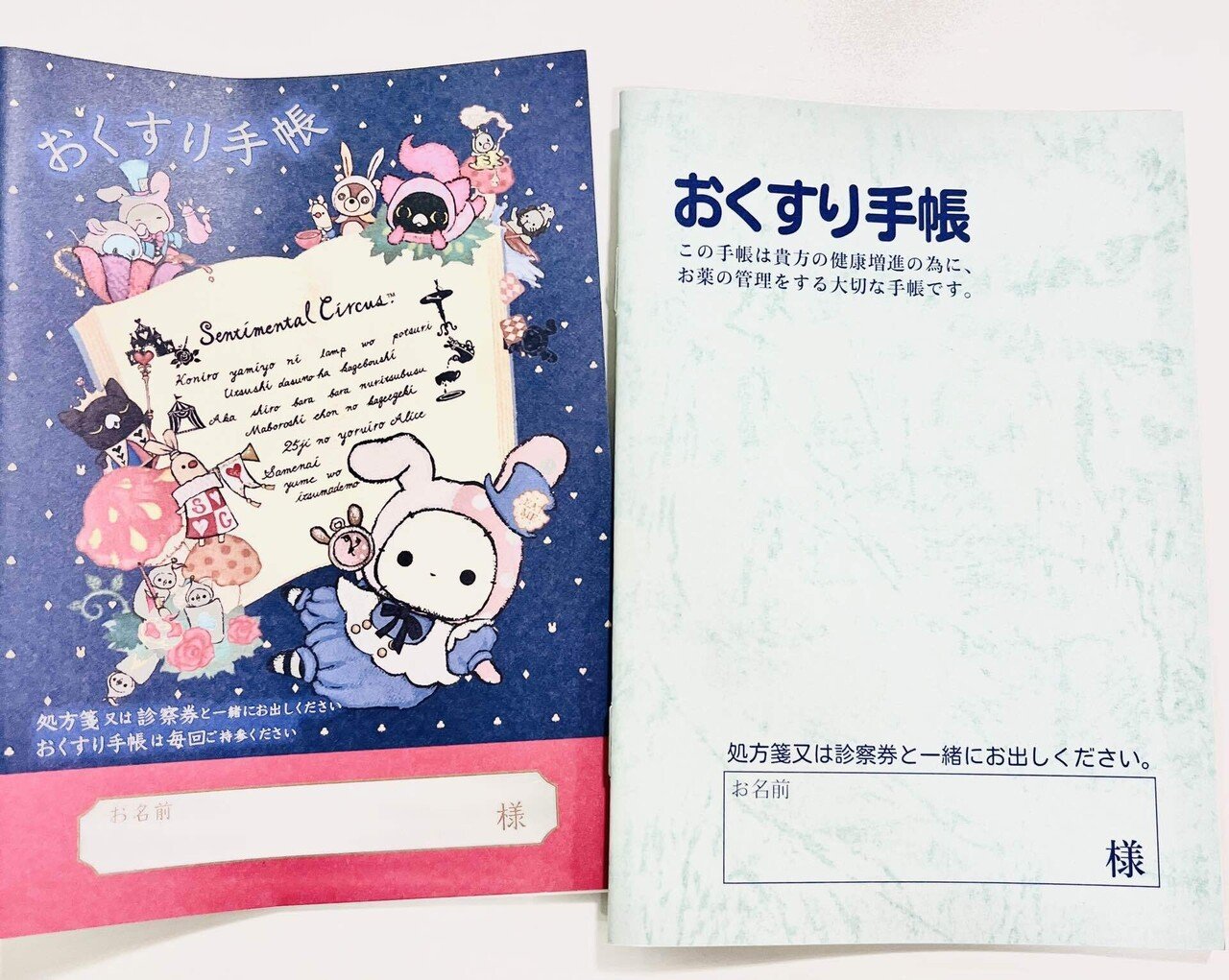
一般用薬品購入時も持参があるか確認する事で併用していいかを、調べたり、確認しやすいのでお客様に習慣にしてもらうようにしましょう。
これはお客様の健康を守る事と、自分のリスクを軽減する事になります。
書面に記載すべき内容書面の保存義務
• 医薬品の名称、有効成分、分類
• 用法・用量
• 効能・効果
• 注意点(危害防止に必要な事項)
• その他適切使用のために必要と判断される情報
いずれの区分にせよ、相談を受けたら受ける義務はあります。
情報提供時の確認事項
| 要指導医薬品 | 第一類 | 第二類 | 第三類 | |
| 年齢・性別 | ◎ | ◎ | △ | /(望ましい) |
| 現在の薬の使用状況 | ◎ | ◎ | △ | / |
| 症状 | ◎ | ◎ | △ | / |
| 受診の有無、診断名 | ◎ | ◎ | △ | / |
| ほかの疾患、持病 | ◎ | ◎ | △ | / |
| 妊娠の可否、授乳 | ◎ | ◎ | △ | / |
| 目的の薬の使用履歴 | ◎ | ◎ | △ | / |
| 副作用歴、薬剤名、状況 | ◎ | ◎ | △ | / |
| 必要と判断した事項 | ◎ | ◎ | △ | / |
| 対面販売 | 〇(本人のみ) | ネット販売可 | ネット販売可 | ネット販売可 |
要指導薬品は必ず本人に対面で販売する事になりますが、第一類医薬品は情報提供は義務ですが対面である必要はありません。オンラインやネット販売が可能で、薬剤師が対応する必要があります。第2類、第3類は一般用薬の約90%を占めており、登録販売者も販売が可能で、対面販売ではなくても販売が出来ます。
受診勧奨
皮膚症状
• 市販薬を5〜6日使用しても改善が見られない
• 症状が2週間以上続く
• かゆみ・赤み・発疹が悪化している
• アレルギーや真菌感染が疑われる
• 慢性化、広範囲に広がる
医師の処方による内服でないと、治療出来ない水虫や皮膚炎がある事を覚えておきましょう。
皮膚症状は自己判断で薬を使い続けると、原因の特定が難しくなることも多いため、タイミングを見て早めに受診しましょう。
なぜ記録が必要なのか?
書面の保存義務。
薬局・店舗販売業者・配置販売業者が医薬品を販売した場合、購入者の安全とトラブル防止のために、販売内容を「書面に記録し、保存」することが法律で定められています。
特に、一般の生活者に販売・授与した場合は、次の事項をしっかり記録する必要があります。
リスク区分別の情報提供と指導
| 区分 | 記載する内容 | 保存の義務 |
| 薬局医薬品・要指導医薬品・第1類医薬品 | 品名、数量、販売日時、情報提供を行った薬剤師の氏名、購入者が内容を理解した確認の結果 | 2年間の保存義務 |
| 第2類医薬品 | 品名、数量、販売日時、情報提供者(薬剤師または登録販売者の氏名)、理解確認の結果 | 努力義務 |
| 第3類医薬品 | 品名、数量、販売日時、情報提供者(薬剤師または登録販売者の氏名) | 努力義務(理解確認の有無不要) |
書面への記録事項と保存の義務
記録する理由と注意点
• トラブル時の証拠として重要
• 副作用が起きた場合、販売記録を確認することで対応が可能
• 要指導医薬品や第1類医薬品は、義務的に2年間保存
• 第2・第3類についても、可能な限り記録と保存に努めることが推奨
⸻
試験対策ポイント
• 保存義務があるのはどの医薬品か?
• 記録に何を記載するのか?
• 記録対象者は誰か?
この項目は、実務でも重要でありながら試験にも頻出のテーマです。特に「第1類は薬剤師が対応」「確認の結果まで記録」がポイントです。