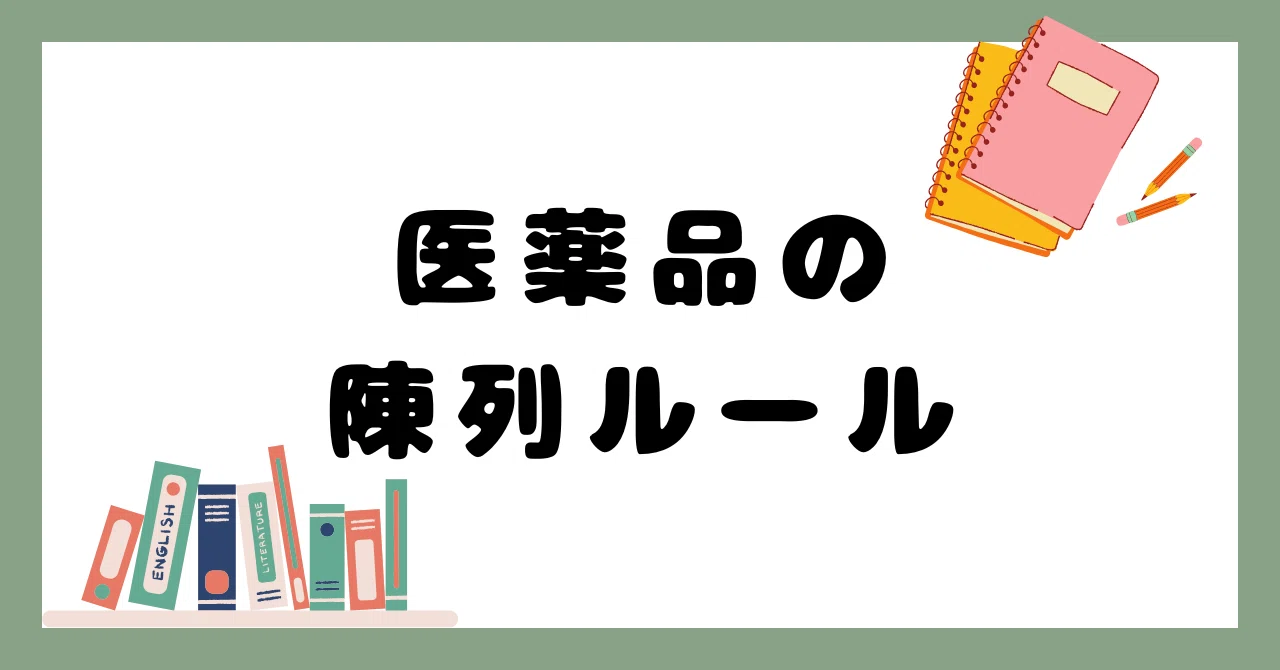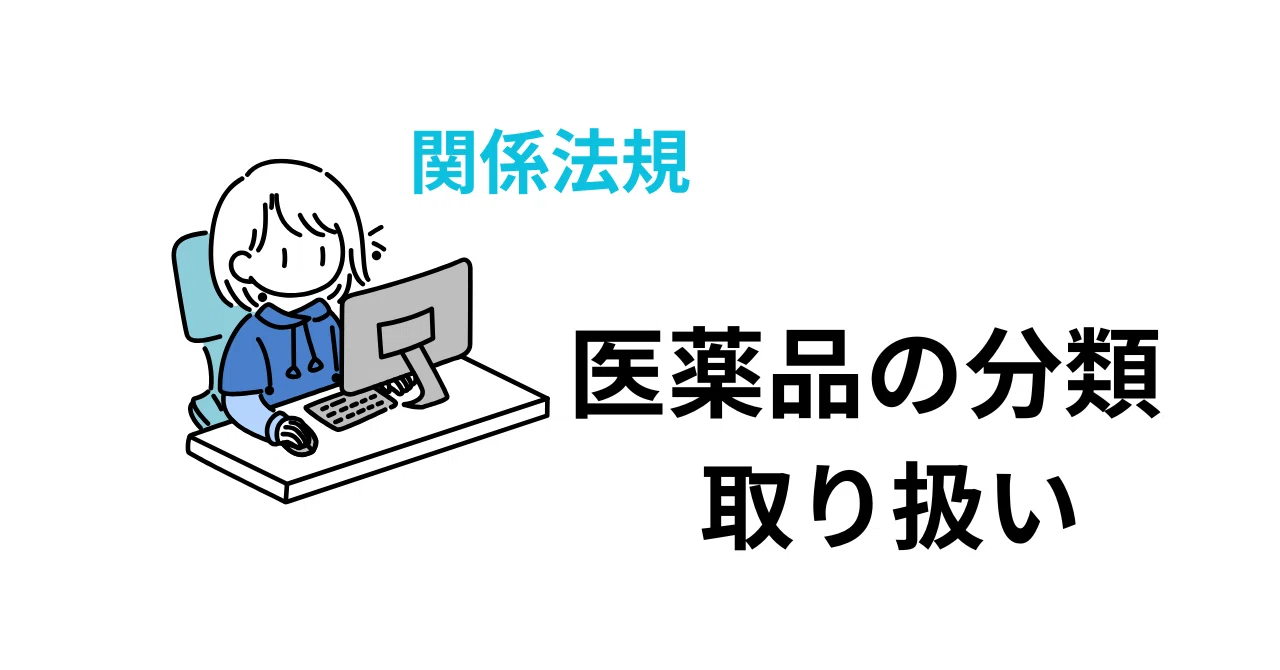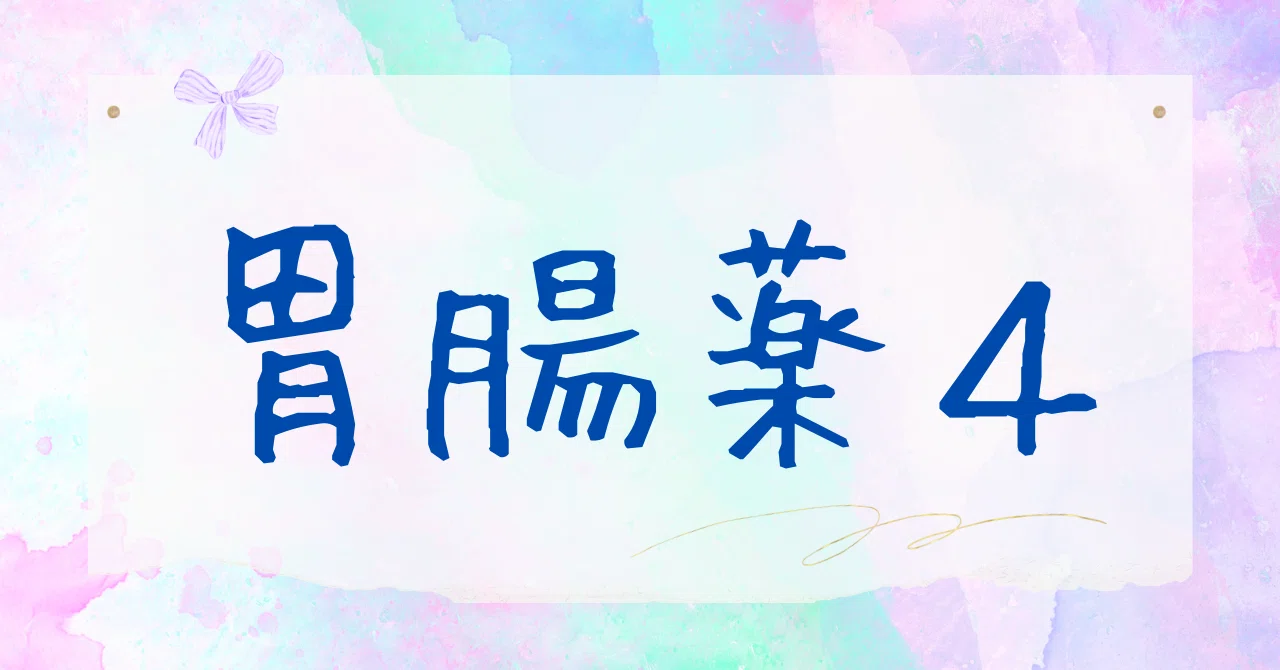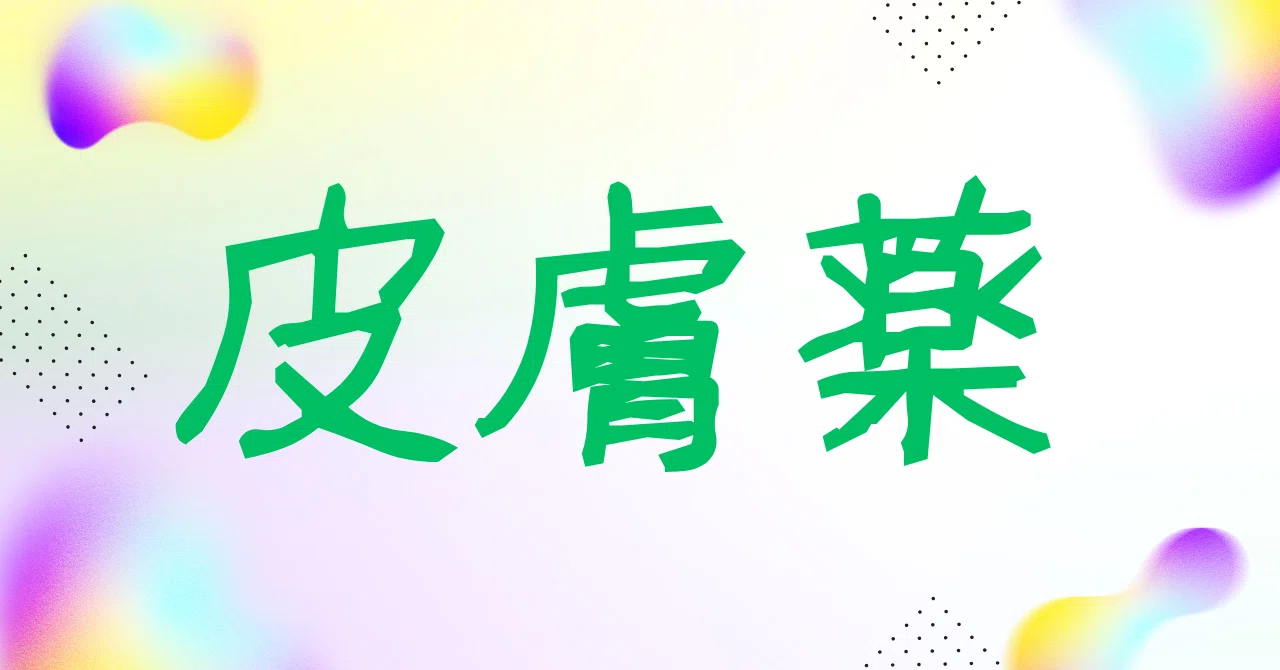登録販売者 関係法規#7医薬品の陳列ルール
yamadap1984@
実践×東洋医学ラボ
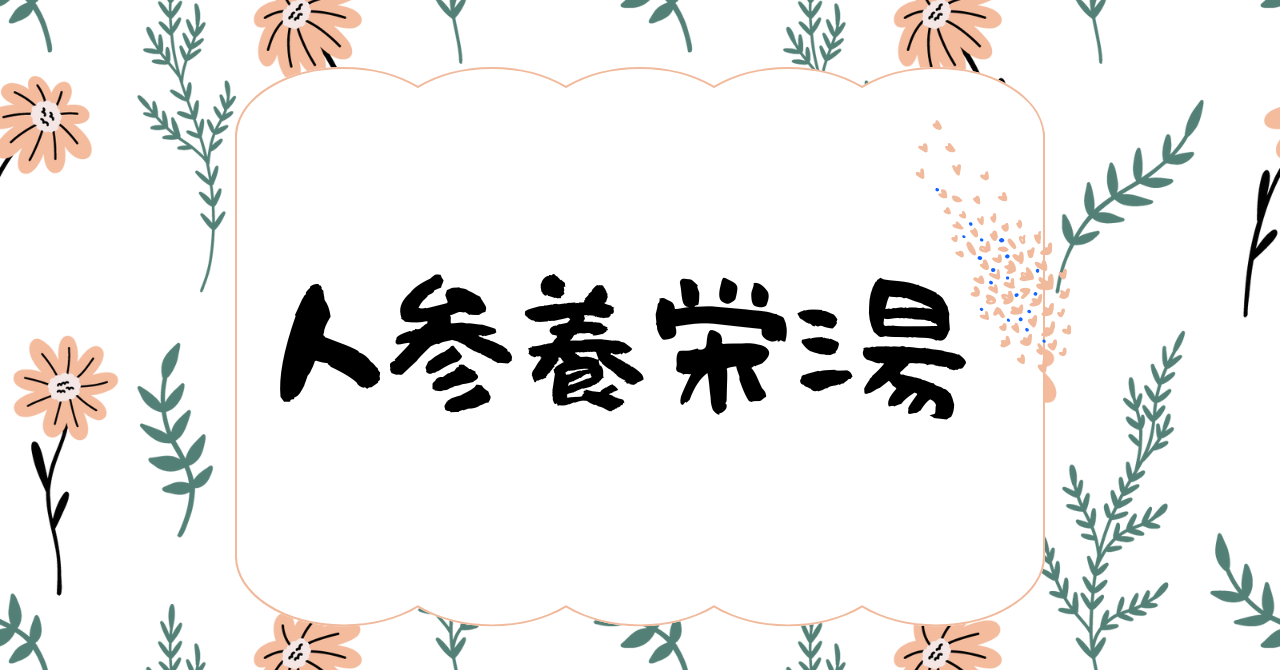
人参養栄湯(にんじんようえいとう)は、気(エネルギー)不足と血(栄養)不足を同時に改善する漢方薬です。
病後や長期間の疲労、虚弱体質によく用いられます。
「気血両虚」による以下の症状に使用。気が血を動かすが、気は血に乗って運ばれる。
• 疲れがとれない
• だるい
• 顔色が悪い
• 動悸、息切れ
• 手足の冷え
• 食欲不振
• 病後・産後の体力低下
• 長引く虚弱体質
→ 慢性疲労・貧血傾向に特に適する
効能・効果
体力虚弱なものの次の諸症:病後・術後などの体力低下、疲労倦怠、食欲不振、ねあせ、手足の冷え、貧血
• 「気」と「血」をともに補う方剤。
• 虚弱体質や冷え性、食欲不振、疲労、血色不良に適応。
• 高齢者や病後の回復に用いられることが多い。
● 構成生薬(特徴:補気+補血)
補気薬(エネルギーを補う):人参、白朮、黄耆、茯苓、陳皮、甘草
補血薬(血を補う):当帰、芍薬、
その他の調整薬:五味子、遠志
● 中医学的理解
• 気(エネルギー)不足 → だるい・息切れ
• 血(栄養)不足 → 顔色悪い・めまい
両方を同時に補うことで
→ 全身の代謝・造血環境を改善
→ 慢性的な疲れに有効
• 人参養栄湯:「気」と「血」を補う → 冷え・貧血・高齢者や病後の体力回復
そもそも気も血も足りてない人が、外部から何かを取り入れても、気は脾胃が元気に動いて吸収して体にとり入れるんですが、気、血の足りない人はそもそも吸収する力も落ちています。
漢方は吸収することが出来るまで、底上げをしてくれて、そのあと鉄分や食事吸収率を上げていくという考え方が理にかなってる。
以下 覚えなくても大丈夫な所です。フーンと眺めて頂けたらと思います。
| 生薬名 | 作用のポイント |
|---|---|
| 地黄(ジオウ) | 補血・造血を助ける |
| 当帰(トウキ) | 血を補い巡らせる、血行改善 |
| 白朮(ビャクジュツ) | 補気、胃腸を丈夫に |
| 茯苓(ブクリョウ) | 利水、胃腸機能を整える |
| 人参(ニンジン) | 補気の代表、体力回復 |
| 桂皮(ケイヒ) | 身体を温め気血の巡り改善 |
| 遠志(オンジ) | 安神、精神安定、記憶改善 |
| 芍薬(シャクヤク) | 補血、筋肉の緊張をゆるめる |
| 陳皮(チンピ) | 消化促進、気の巡り改善 |
| 黄耆(オウギ) | 補気、免疫力向上 |
| 甘草(カンゾウ) | 諸薬の調和、胃の保護 |
| 五味子(ゴミシ) | 体力回復、汗の調整 |
分類:第2類医薬品
製品名:人参養栄湯エキス顆粒(医療用108)
服用:成人1回1包 1日2〜3回
食前または食間に服用
養生方法
鉄剤
鉄分そのものを補給
効きが速い
胃腸負担が出やすい→
鉄剤が合わない人の選択肢にも
ビタミン剤(サプリメントも含め)様々な栄養吸収、疲労物質の分解などに利用され、継続的使用する事で疲れの改善と、疲れにくくする作用がある。
⸻