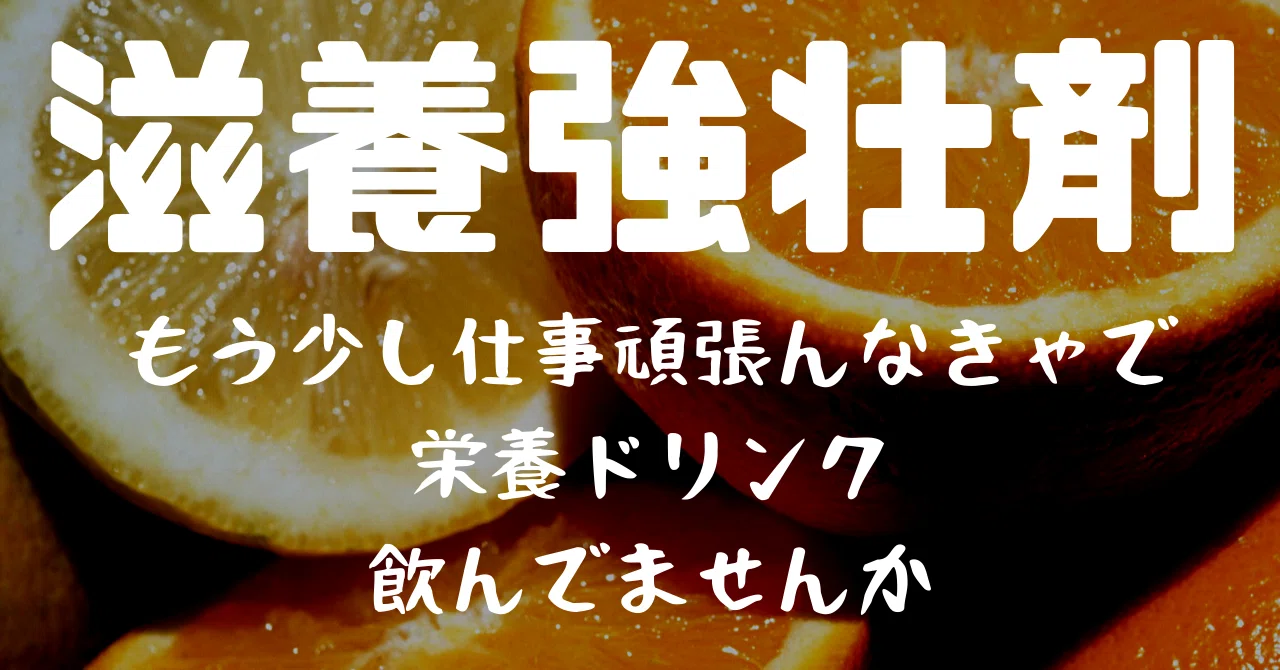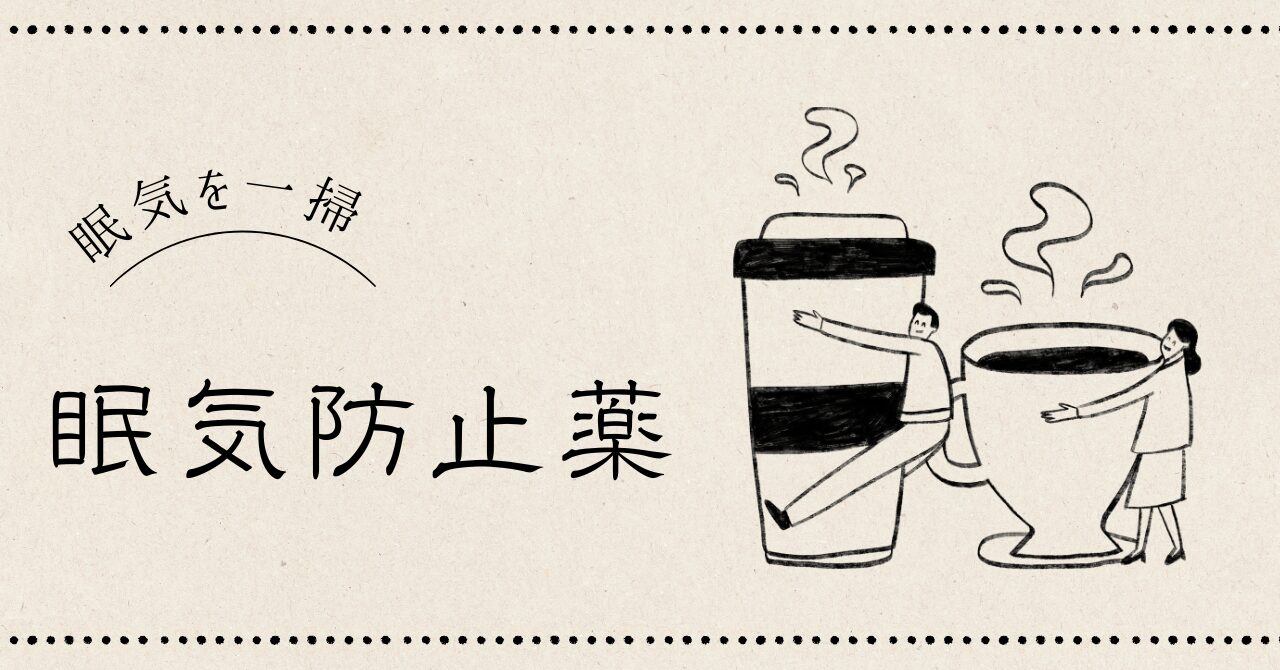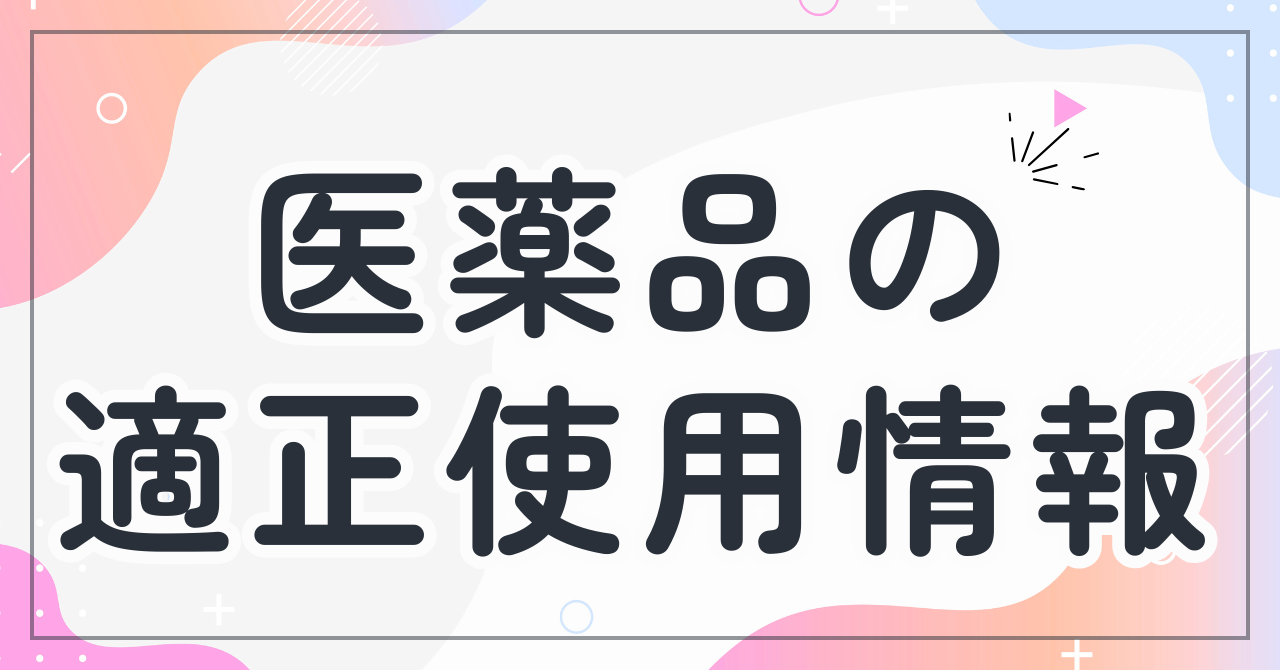医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因(後編)#4

今回は主に「人の状態や年齢」によってどのような配慮が必要か、また品質や保存についての注意点も紹介します。
7. 年齢や状態に応じた配慮
医薬品は、年齢や体調に応じた使い方が必要不可欠です。以下に、特に配慮が必要なケースをまとめました。
【1】小児への配慮
● 特徴
• 吸収率が高く、副作用が出やすい
• 血液脳関門が未発達のため、中枢神経に影響しやすい
• 肝臓や腎臓の機能が未熟なため、代謝や排泄に時間がかかる
● 使用時の注意
• 誤飲のリスクが高く、保管場所に注意
• 症状が急変しやすく、一般薬の使用は最小限に
• お薬の使用後は保護者がしっかり観察
年齢区分と特徴
- 新生児:生後4週未満
- 乳児:生後4週~1歳未満
- 幼児:1歳~7歳未満
- 小児:7歳~15歳未満
【2】高齢者への配慮
● 特徴(65歳以上が対象)
• 肝臓や腎臓の機能が低下 → 副作用が出やすい
• 薬の効き方に個人差が大きい
• 飲み込みやすさの低下・誤嚥リスク
• 基礎疾患の影響で症状悪化の可能性もあり
● 使用時の注意
• 薬の説明に時間がかかることもある
• 文字が小さい添付文書の確認が困難な場合あり
• 飲み忘れや間違いが起きやすく、周囲のサポートが必要
⸻
【3】妊婦・妊娠の可能性がある女性への配慮
● 特徴
• 胎児は胎盤を通して母体から栄養とともに薬の影響も受ける
• 薬の胎児への移行と影響は未解明な部分が多い
● 使用時の注意
• 安全性の評価が難しいため、必ず医師に相談する
• 妊婦に対して自己判断で市販薬を使わない
⸻
【4】授乳中の女性(授乳婦)
• 一部の薬成分が母乳に移行し、乳児に影響を与える恐れあり
• ジフェンヒドラミンなどは注意
→ 授乳中は避ける、または一定期間授乳を控える
⸻
【5】医療機関で治療中の人
• 症状の悪化や治療の妨げになる可能性がある
• 購入時には、服用中の薬や病名、服用時期などを確認し、必要があればお薬手帳を活用
⸻
8. プラセボ効果(偽薬効果)
• 実際には薬理作用がないのに、「効くはず」という心理的効果で症状が改善すること
• 暗示効果・自然緩解・条件づけ反応などが関与
• ただし、プラセボ目的で薬を使うことはNG!
イトーヨーカドーの商品を最短70分で【IYNSbyONIGO】
9. 医薬品の品質劣化と使用期限
● 品質劣化の要因
• 光(紫外線)・高温・湿気・空気などにより、薬の有効成分が変質・分解
• 効き目が落ちたり、副作用が強く出るリスクも
● 使用期限の意味
• 薬は未開封かつ適切な保管で有効性が保証される期間
• 購入時に使用期限をチェックし、十分な猶予があるかを確認することが重要
⸻
【まとめ】
ここまで、医薬品の効果や安全性に影響を与える多くの要因を紹介してきました。
登録販売者として、正しい知識を持ち、利用者にわかりやすく、丁寧にアドバイスできる力が求められます。
/
小規模サロンの予約はリピッテBEAUTY
カフェイン類が配合されている場合
(例:鎮痛薬、眠気対策薬、総合感冒薬など)
眠気覚まし効果の裏にリスクあり!妊娠・授乳中も要注意。
カフェインは一時的に頭がスッキリしたり、眠気が抑えられたりする効果があるため、さまざまな市販薬に配合されています。特に眠気防止や鎮痛作用の補助として活用されていますが、摂りすぎや長期使用にはリスクも潜んでいます。
まず、カフェインは胃酸の分泌を促す作用があるため、空腹時や胃が弱い人では胃痛や吐き気などの症状が現れることがあります。また、作用が弱いと感じて繰り返し摂取することで習慣化しやすく、知らぬ間に過剰摂取になりやすい点にも注意が必要です。
妊娠中の方は特に注意が必要で、カフェインの一部は胎盤を通過して胎児に達するため、胎児の心拍数が上昇するなどの影響が出る可能性があります。また、授乳中の方でも、カフェインは母乳に移行し、乳児が興奮して寝つきが悪くなったりすることがあります。
「眠気覚ましにちょっとだけ…」という軽い気持ちが積み重なると、意外な副作用を招くことも。体質や生活状況に応じて、カフェイン入り医薬品の使用は慎重に行いましょう。