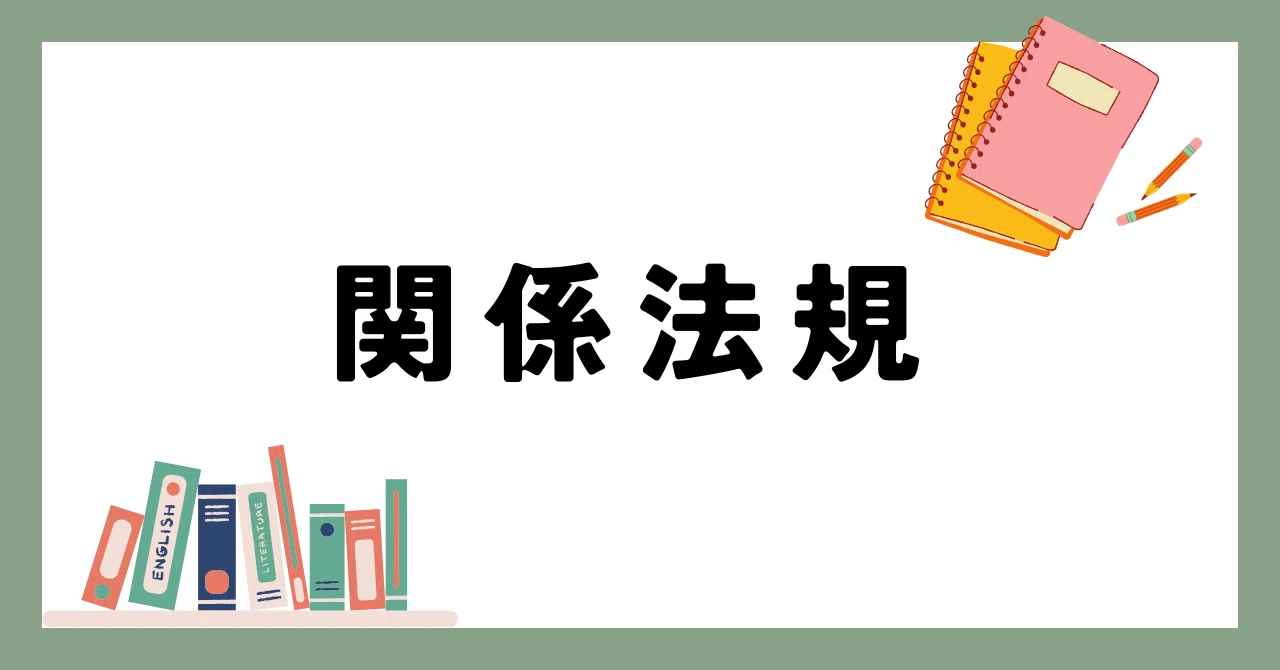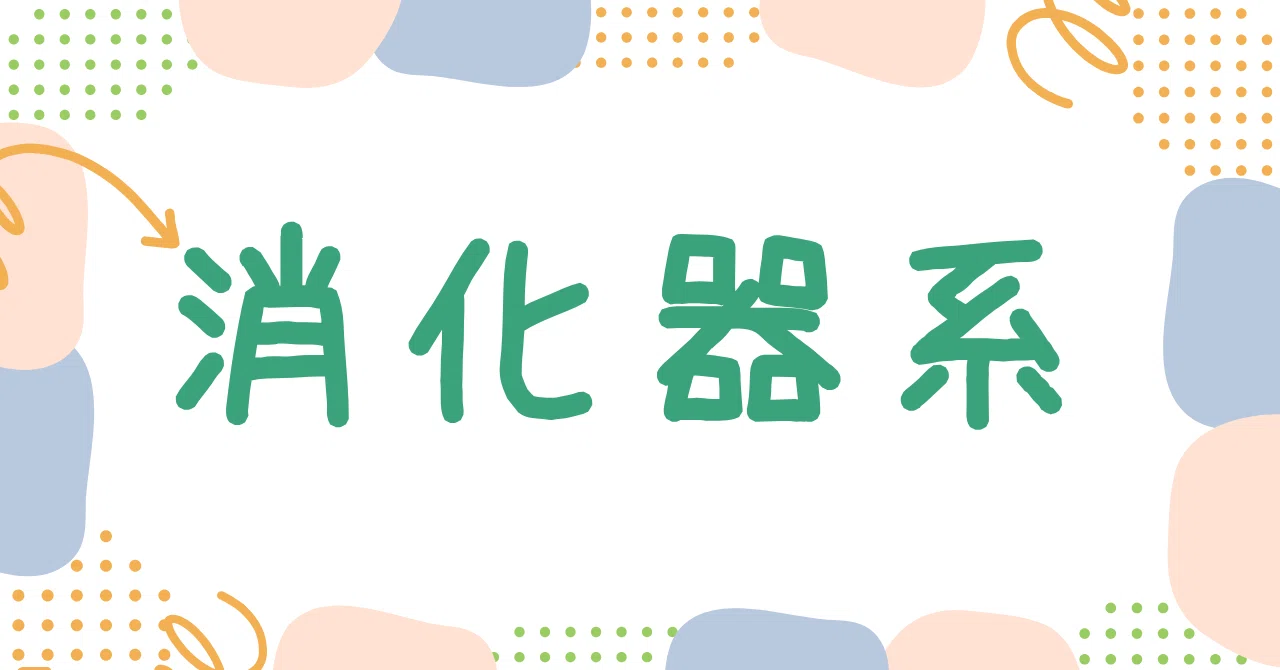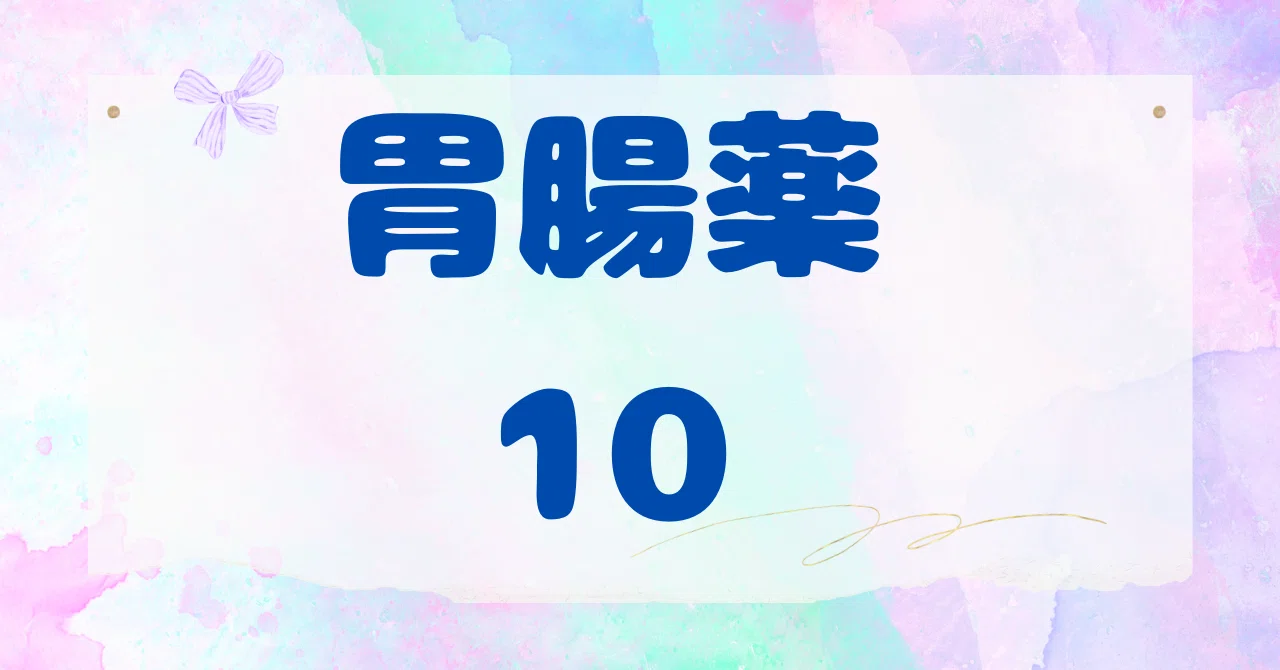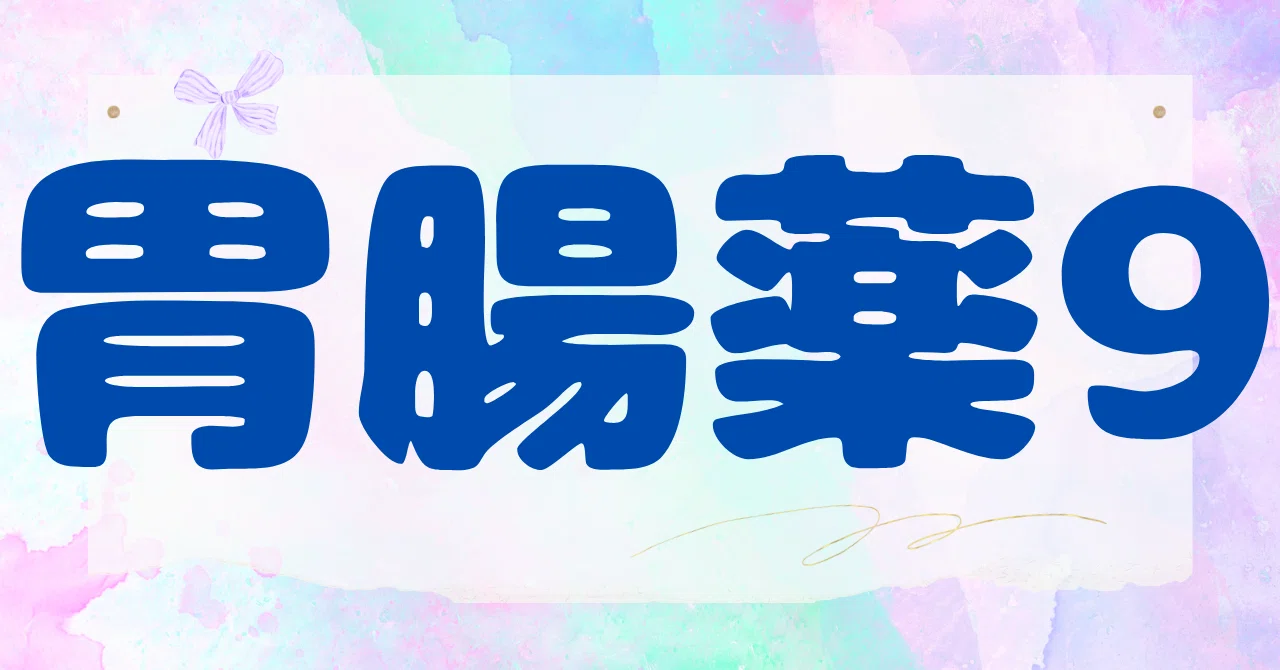登録販売者#13 解熱鎮痛剤

薬単体で続けて羅列するとと面白くないので
こんな感じで単発的に
入れて行きたいとおもいます。
よく購入される痛み止め、
熱冷ましからやっていきます。
頭痛、発熱、生理痛…。そんな時に使われるのが「解熱鎮痛薬」。ですが、正しく理解せずに使うと思わぬ副作用につながることもあります。今回は、解熱鎮痛薬の仕組み・成分・注意点について簡単にまとめました。
痛みや発熱が起こるしくみ
痛みや発熱は、病気や外傷に対する警報として体が出すサインです。
〇痛み(生理痛など)は、体の異常を知らせるもの
〇発熱は、ウイルス感染などに対して免疫機能を活性化させる反応の一つ
(つまり生体防御機能の一つ)
こうした反応には「プロスタグランジン」
が深く関わっています。
プロスタグランジンの主な働き
- 痛みの感覚を強める
- 温熱中枢に作用して体温を高く維持する
- 炎症や関節の痛みを引き起こす
- 胃腸粘膜を保護し、胃酸分泌の調節にも関与
つまり、プロスタグランジンは体にとって必要不可欠な物質ですが、過剰になると痛みや発熱の原因にもなるのです。
解熱鎮痛薬とは?
解熱鎮痛薬は、プロスタグランジンの生成を抑え、
「発熱や痛みを一時的に和らげる薬」です。
ただし、病気の原因自体を治すものではありません。あくまで症状を緩和する対症療法にあたります。
また、腹痛で痙攣性のものによる内臓痛は発生機序が異なるため一部の漢方を除き解熱鎮痛剤じゃ効きません。
◆ 主な成分とその働き
【1】化学的に合成された成分
- 中枢神経系の作用でプロスタグランジンの産生を抑制
- 腎臓での水の再吸収を促進し、体温調節に関わる
- 局所での抗炎症作用も期待される
※使用時は、次のような注意が必要です。
◆ 注意すべき副作用と使用上の注意点
- 心臓に障害がある → 循環負担が大きくなり悪化するおそれ
- 腎機能に障害がある → 腎血流を減少させ、機能悪化の可能性
- アレルギー体質の人 → アレルギー反応の誘発に注意
- 肝機能障害がある → 解熱鎮痛薬で症状が悪化することがある
- 胃・十二指腸潰瘍がある → 胃粘膜への影響が大きく、悪化する可能性
- 高齢者・妊婦 → 使用前に医師と相談を
- アナフィラキシーショック、皮膚粘膜眼症候群、中毒性皮膚壊死融解症、喘息(アスピリン喘息という痛み止めに反応して起る喘息がある:アスピリン以外の痛み止め全般に起こる)
◆ 成分別の特徴
◆ アスピリン

https://search.sato-seiyaku.co.jp/pub/product/2236/(佐藤製薬)
- 胃腸障害を起こしやすい
- 血液を凝固しにくくするため、手術・出産時などは要注意(容量依存性で低容量だと”血液サラサラの薬”)
- 出産予定日の12週以内の使用は避ける、分娩時の出血過多、妊娠期間延長など(とはいえ、妊産婦には市販薬は勧めないほうがいい)
- 重篤な副作用としてまれに、肝機能障害
◆ エテンザミド

https://brand.taisho.co.jp/naron/product/acetaminophen/(大正製薬)
- 痛みの発生を抑える作用
- 他成分と併用することで相乗効果がある
- アセトアミノフェン・カフェイン・エテンザミドの組み合わせは「ACE処方」と呼ばれ、頭痛薬によく使われる
◆ ライ症候群とサリチル酸系の関係に注意!
アスピリンやサザピリンなどのサリチル酸系成分は、ライ症候群の発症リスクがあるため、
15歳未満の小児には使用禁止。
- サリチルアミド、エテンザミドなども同様に注意。
水痘やインフルエンザにかかっている子どもに使う場合は、必ず医師に相談を!
※ライ症候群:小児が水痘、インフルエンザなどのウイルス性疾患発病時、激しい嘔吐や意識障害、痙攣などの急性脳症を起こすことがあり、解熱剤との関連性が高いとされている。
◆ アセトアミノフェン

https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/products/details/calonal-a_tab/(第一三共)
中枢性作用で解熱、鎮痛作用をもたらし、末梢での抗炎症作用は期待できない。
- 解熱・鎮痛効果が穏やかで、胃腸障害が少ないのが特徴。だが食後の服用が推奨される。
- 皮膚粘膜眼症候群、中毒性表皮壊死症、肝機能障害などの重い副作用の可能性あり。(日常での酒量多い人に起こりやすい傾向)
- 空腹時やアルコール摂取時には特に注意。
◆ 坐薬との併用に注意!
- 小児に使う坐薬にもアセトアミノフェンが含まれることがあり、内服薬との併用で過剰摂取になることがある。
- 「坐薬と飲み薬は別」と思い込まず、成分をしっかり確認すること!
◆ イブプロフェン
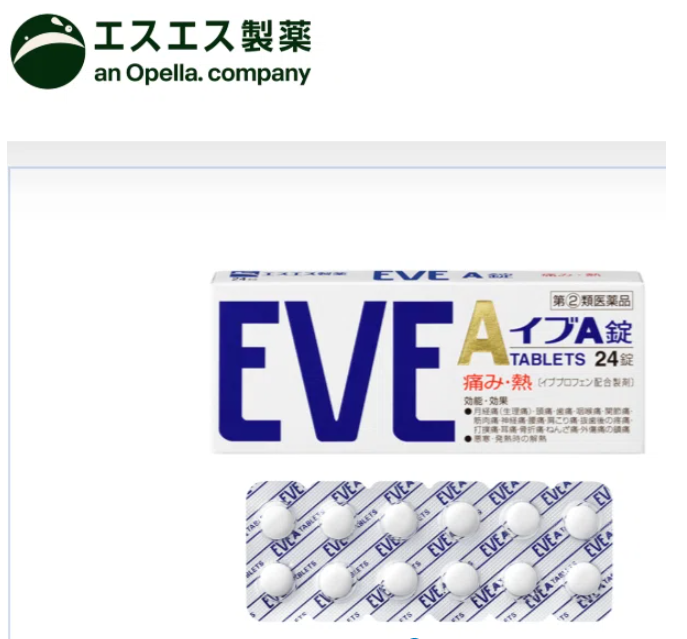
https://www.ssp.co.jp/product/detail/evea/(エスエス製薬)
- アスピリンより胃腸への悪影響が少ない。
- 抗炎症作用も強く、月経痛・腰痛にも使用される。
- ただし、胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎・クローン病は再発を招く。
- 稀な重篤度の高い副作用として肝障害・腎障害・無菌性髄膜炎などが生じる。
- 出産予定日12週以内の妊婦は服用しない。
- エリテマトーデスまたは混合性結合組織病の診断を受けた人は、無菌性髄膜炎になりやすいため、医師に相談してもらう。
- 15歳未満には使用不可。
◆ イソプロピルアンチピリン(ピリン系)

https://www.shionogi-hc.co.jp/sedes/product/sedeshigh.html(塩野義製薬)
- 解熱、鎮痛作用が強いため根強いファンがいる。
- セデスが代名詞だが、セデスはピリン以外も同ブランド内で展開しているので成分名を理解するのは大事です。
- 抗炎症作用は弱い。他の解熱鎮痛剤と併用される
- ピリン系は(ピリン疹という固有の強い)アレルギー症状を引き起こすリスクがある。
- ただし「非ピリン系なら薬疹の心配がない」というのは誤解。
【2】◆ 生薬成分にも解熱・鎮痛作用がある
生薬による解熱鎮痛の作用はプロスタグランジン産生とは別にと考えられています。科学的に合成された薬は(清熱解表のものが多い)
生薬入りの総合感冒薬に入っている事があり、考え方としては、
熱がある(体の水分が燃える又は熱によって水分が蒸発して燃えやすい状態なので発熱している、熱を発散できなくて熱がこもっている)と考える。
そこに水分を足したり、水で消火活動をするような働きをする生薬が加えられている事が多いです。水は単に水の場合と、血液量をさす場合もある。(体液全般と考えるとわかりやすい)或いはその水を(汗にして)蒸発させて気化熱で熱をさげようとする。
痛みに関しても(炎症なので消火活動がイメージされやすい)
火を消せば.→痛みも治まる。
筋肉からくる痛みも、筋肉の柔軟性が水分不足によって硬くなり痛みを出しているので、やはり水分補給系の生薬が使われやすい。
- ジリュウ(地竜:ミミズの炭焼き)、ショウキョウ(生姜:ショウガ)、ケイヒ(桂皮:シナモン):解熱作用
- シャクヤク(芍薬の花の根)、ボタンピ(牡丹の木の皮)、ボウイ(防已):鎮痛作用
生薬については別にまた書いていこうと思うので今は登録販売者用に覚えてください。後々これをベースに深堀したいと思います。
- 関節痛などに使われるコンドロイチン硫酸ナトリウムと組み合わされることもある。
◆ 骨格筋の緊張を鎮める成分
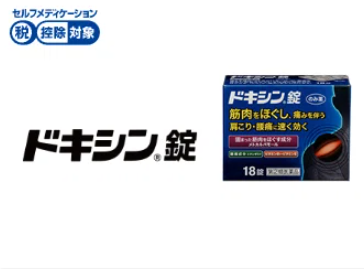
https://alinamin-kenko.jp/products/genestu/doxin.html(アリナミン製薬)
- メトカルバモール:筋肉のこりをやわらげ、肩こりや腰痛に効果。
- 副作用として、眠気・ふらつき・運転注意。(カフェインが入っているけど緩みすぎてボーっとしてしまいやすい)
まとめ
解熱鎮痛薬は、成分の違いで効果や副作用が大きく異なる薬です。年齢・持病・体質などをふまえて選ぶ必要があり、市販薬であっても慎重に使うことが大切です。
 | ユーキャンの登録販売者 これだけ!一問一答&要点まとめ 第7版 (ユーキャンの資格試験シリーズ) [ ユーキャン 登録販売者試験研究会 ] 価格:1870円 |