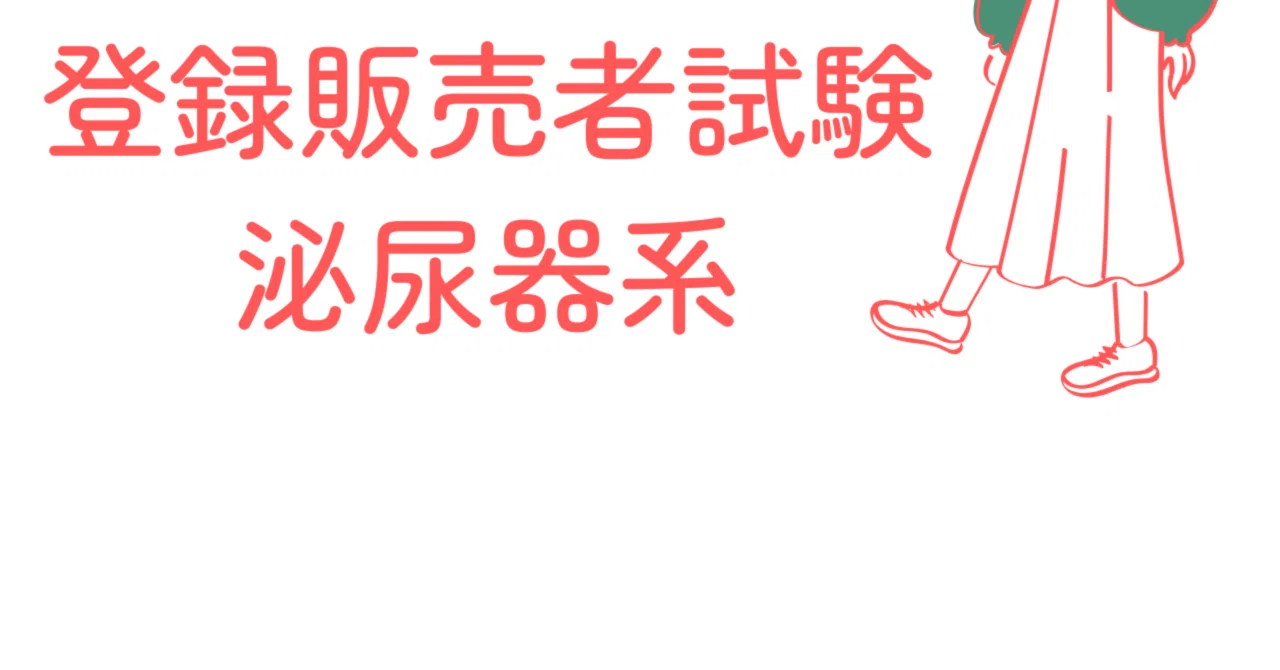登録販売者試験 関係法規、制度#2医薬品の販売業の許可
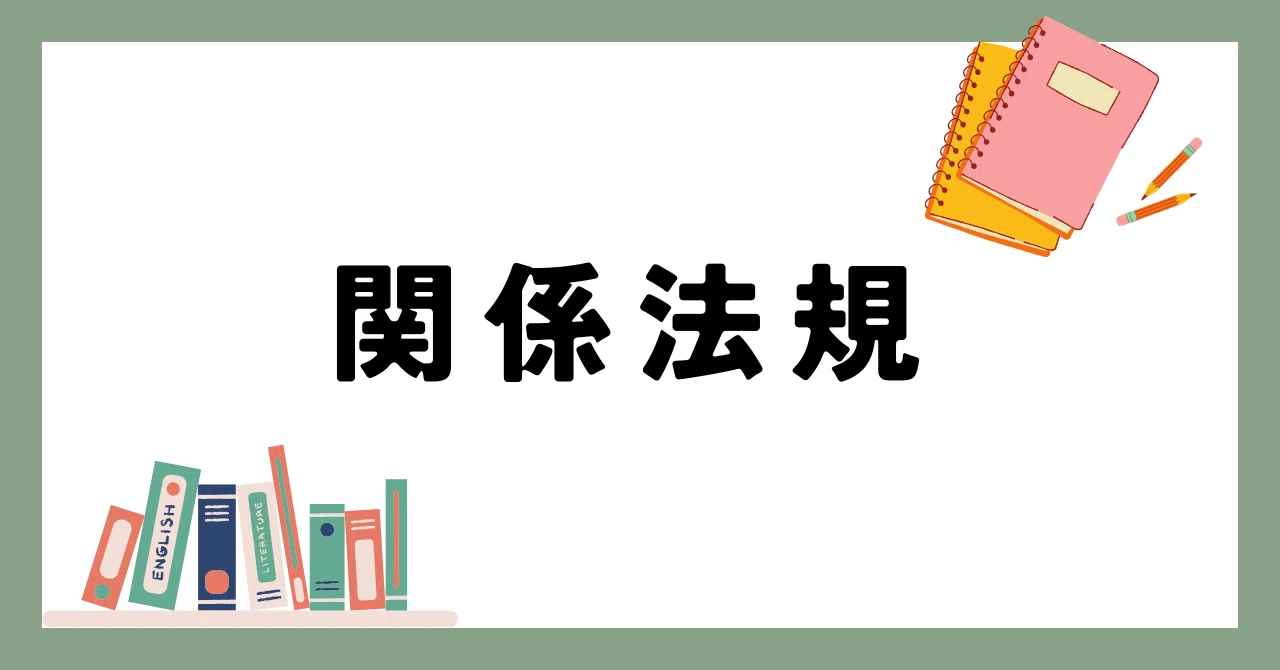
医薬品の販売業の許可制度を理解しよう
1.販売業許可とは?
▷ 医薬品を販売するために必要な「許可制度」
医薬品を(販売、授与→その目的で貯蔵、陳列)するには、
薬局開設者や販売業者が都道府県知事の許可を受ける必要があります。無許可で販売すると懲役や罰則があります。
▷ 許可の種類は3つ!(25条)
• 店舗販売業:薬局以外の店舗で販売(例:ドラッグストア)
• 配置販売業:「富山の薬売り」に代表されるような、家庭などに薬を預けておく形式
• 卸売販売業:医療機関などに向けて薬を販売(一般向け販売は不可)
▷ 許可の有効期間
• 6年ごとに更新が必要です(更新しないと効力を失います)。
⸻
2.販売方法の制限
▷ 店舗販売と配置販売の違い
• 店舗販売業者は、「店舗で販売すること」が原則。
• 配置販売業者は、「あらかじめ置いた薬を回収・補充する形式」で販売。
いずれも、決められた方法以外での販売は違法で、罰則の対象となります。
認められない販売形態
• 露天販売や現金行商などは、販売側の責任追及が困難なため禁止されています。
(違法な物や、期限切れ、品質劣化のものを販売して、売り逃げるのを防止しています。)
⸻
3.販売の特別な扱い:「分割販売と小分け製造」
•薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、特定の購入者の求めに応じて量り売りする事が出来ますが(量り売り、零売『れいばい』)分割する場合どんな容器で分割したか等法的に決まった事項を記載する必要があります。
(分割者の氏名、薬局又は名称、所在地など)
• 薬品を予め小分けにして「分けて売る」行為(分割販売)は、製造と同様の扱いとなり、基本的に禁止。
• 分割販売を行うには、氏名・販売内容の記録義務がある。
• 登録販売者や店舗販売業者が勝手に小分けすることは無許可製造にあたる可能性があります。
例えば、
Aさんが塩を100g欲しいと言いプラスチック容器に100g量って売る。OK
塩100gが高価で売れないのでら10gに小分けして売るのはNG
⸻
4.各販売形態の定義と特徴
▷ 薬局
• 調剤・医療用医薬品の販売が可能。
• 一般用医薬品のうち、第二類・第三類は登録販売者が販売可。
• 開設には、都道府県知事の許可が必要。
▷ 店舗販売業
• ドラッグストアなど。
• 調剤はできないが、一般用医薬品の販売が可能。
⸻
5.薬局の運営管理体制
▷ 薬局管理者の指定
• 原則:薬剤師自身が管理者になる
• 管理者不在の場合、薬剤師の中から薬局の業務に精通した者を管理者に指定。
• 管理内容は記録・保存義務あり。
▷ 薬局開設者の責務
• 法律に沿って薬局を運営。
• 薬局管理者の意見を尊重し、必要な指導や措置を記録・保存する必要あり。
⸻
6.特別な薬局の形態(地域や機能に応じた分類)
種類
特徴
地域連携薬局:医師や歯科医師と連携して、地域の医療・服薬支援を行う。都道府県知事の認定が必要。
専門医療機関連携薬局:がんや難病など専門的な治療に対応。高度な指導ができる薬局。
健康サポート薬局:健康維持のための支援・相談機能を備えた薬局。認定基準を満たす必要あり。
7.薬剤師不在時間に関する注意点
• 薬剤師が不在の時間帯は、調剤を行うことはできない。
• 不在時間帯には、外から見える場所に表示しなければならない。
• この間に登録販売者が販売できるのは、第二類医薬品と第三類医薬品のみ。
また、「要指導医薬品」や「第一類医薬品」は、鍵付きで保管し、販売禁止です。
⸻
受診推奨 1. 関節痛や筋肉痛
(自己判断で続けず、早めの受診をすすめるケース)
自己判断では危険なケースも!体のサインを見逃さないで。
1)関節や筋肉の痛み
• 痛みが次第に強くなる
• 脱臼や骨折が疑われる
• 一般薬では治らない、歩けないほどの痛みが続く場合(変形性関節症、痛風、心疾患など)
このような場合には、市販薬に頼るのではなく、早期の受診が大切です。