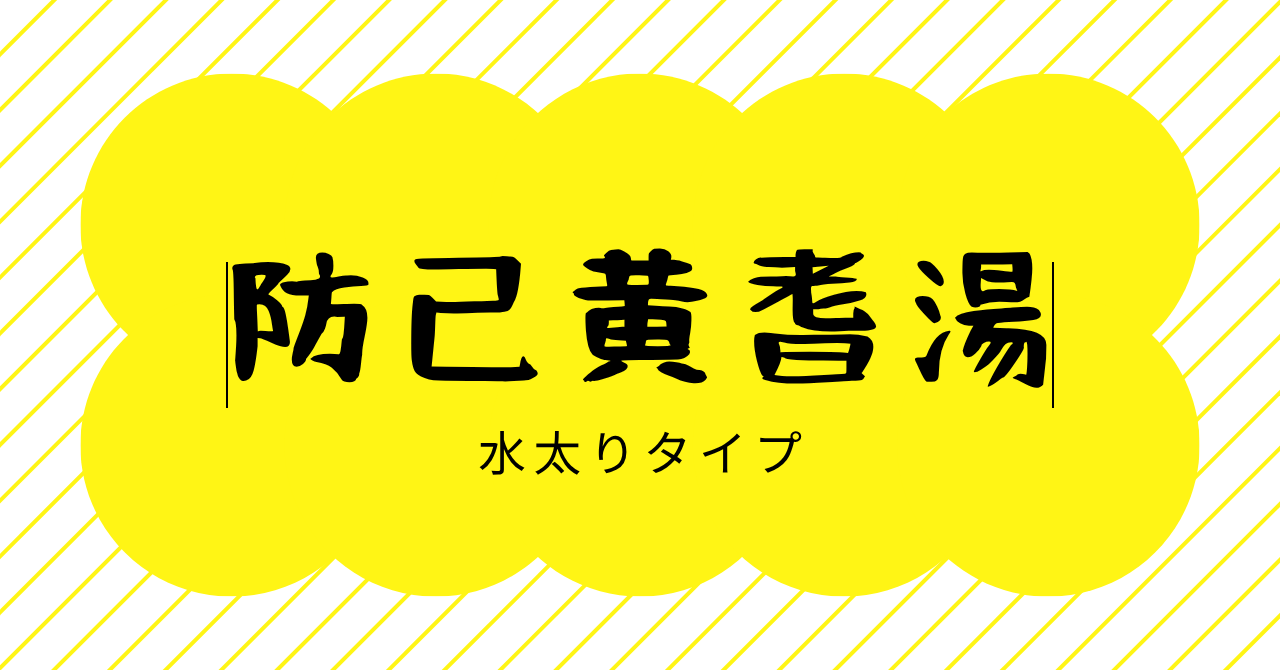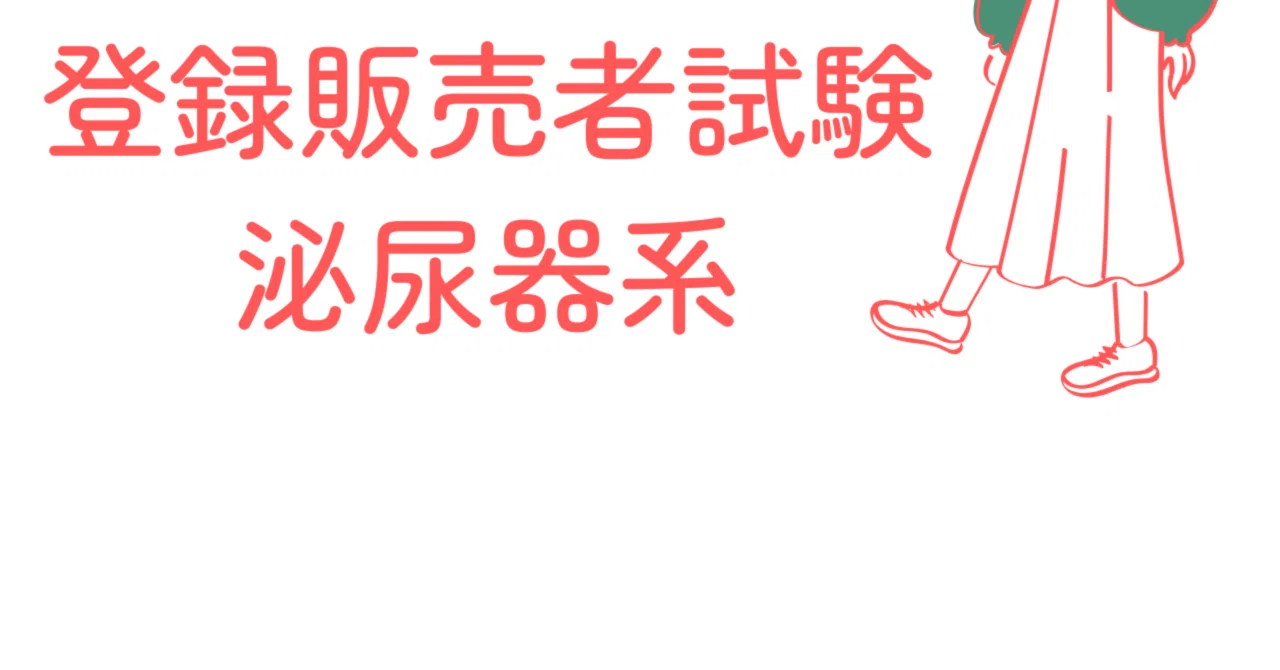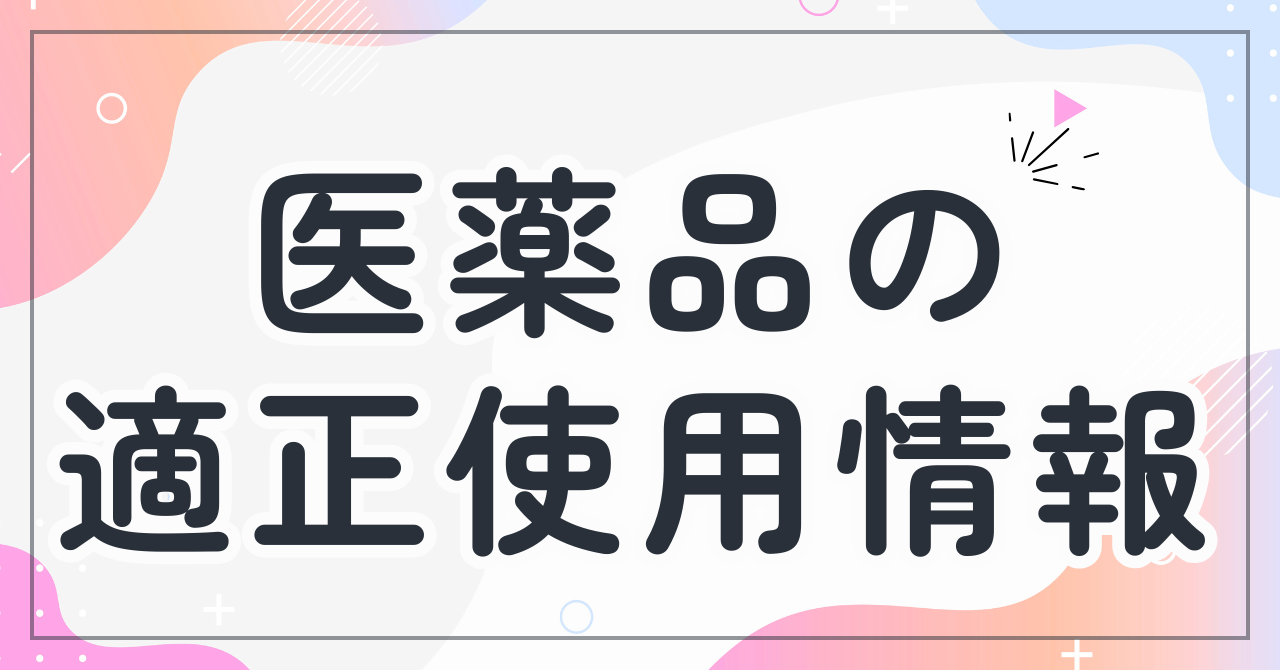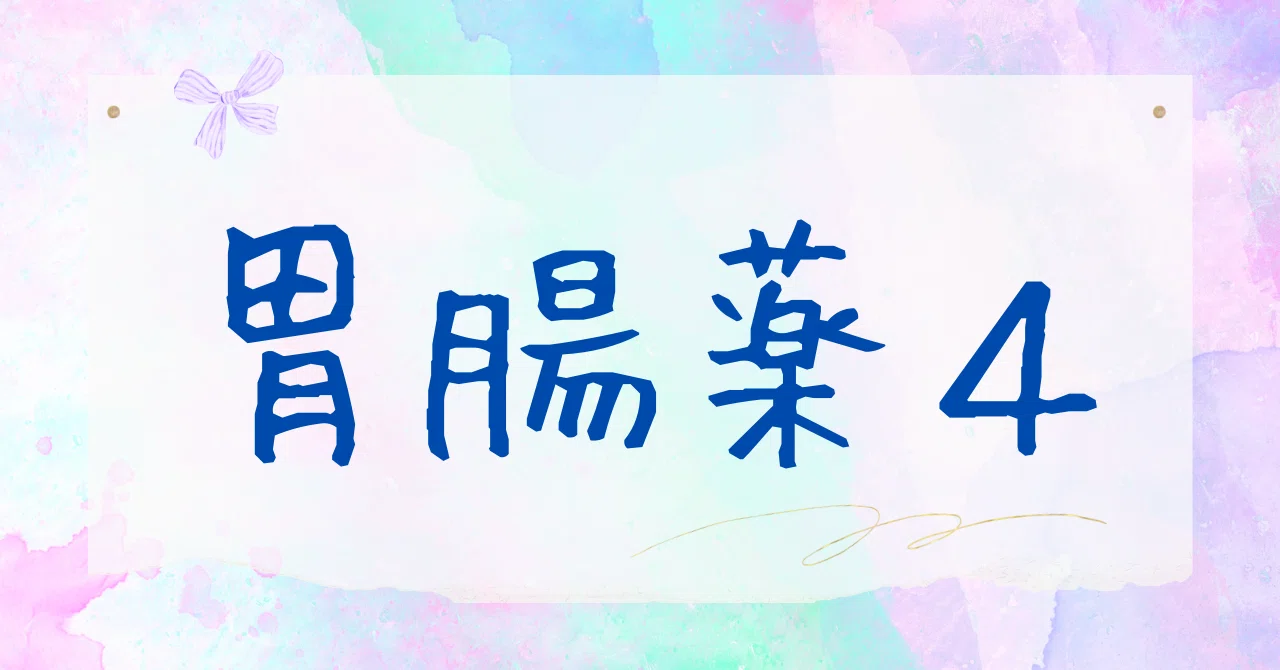登録販売者試験#17代謝・排泄・血中濃度のしくみ

薬の体内での旅:代謝・排泄・血中濃度のしくみ
薬が体内に入ってから排泄されるまで、どのようなプロセスをたどるのでしょうか?
薬の効果や副作用の出方に深く関わる「代謝」や「排泄」、「血中濃度」について書いてみます。
⸻
1.薬の代謝とは?
代謝(たいしゃ)とは、薬が体内で化学的に変化することです。
この変化によって、体が異物と判断したものは解毒(体に安全な形に変化)、排泄されやすい形に変化させます。
また、代謝によって作用が失われたり(=不活性化)、逆に活性を持つ別の物質に変わることもあります。
この仕組みを利用して薬の効かせ方を設計されている薬もあります。
⸻
2.薬の排泄とは?
代謝された薬(代謝物)は、体外へ排出されていきます。
主な排泄経路は以下のとおり:
• 腎臓 → 尿中へ排泄(主経路)
• 肝臓 → 胆汁中へ排泄(消化管を通って便中に)
• 肺 → 呼気中に排出されることも(揮発性の薬)
• 汗・母乳中への移行もあり(特に乳児に注意)
肝機能が悪い人:代謝して無毒化されるはずの薬物が残留して副作用につながったり、代謝後の成分で薬効を発現するはずが、効果が薄いなどが起こります。
腎機能が悪い人:排泄最終出口が詰まっている様な物で、体に不要で出そうとしているのに出せず蓄積して副作用につながったり効果発現の調節が、しにくくなる。また、腎臓の疲弊につながる。
⸻
肝初回通過効果(かんしょかいつうかこうか)とは?
口から飲んだ薬は、消化管で吸収されたあと、「門脈」を通って肝臓へ運ばれます。
このとき、肝臓の酵素によって代謝されると、全身に届く有効成分が減ってしまう現象があります。これが
肝初回通過効果(first-pass effect)です。
ポイント:
• 肝機能が低い人ではこの代謝がうまくいかず、未代謝成分が多く残る
• その結果、「副作用が出やすくなる」リスクがあります
⸻
3.循環血液に入った薬の働き
吸収・代謝を経た有効成分は、最終的に全身の血液中へ移動します。
そこで、体内の「標的(ターゲット)」と呼ばれる細胞に届き、薬としての作用を発揮します。
このとき、有効成分は:
• 血漿中のタンパク質(アルブミンなど)と結合しながら運ばれたり
• 受容体や酵素、輸送体にくっついて、細胞内で効果を出したりします
⸻
4.血中濃度とは?(薬の効果と副作用のバランス)
血中濃度とは、血液中に薬がどれだけ溶けているかを示す濃度のこと。
薬の効果や副作用は、この血中濃度に大きく影響されます:
• 最低有効濃度(最小有効濃度)より低い → 効果が出ない
• 治療域(有効域)内 → 安全かつ効果的
• 危険域(中毒域)に達すると → 副作用・毒性が出やすくなる
⸻
代謝:体内で化学的に薬を変化させること
排泄:薬や代謝物を体外へ出すこと
肝初回通過効果:肝臓での代謝により、薬の有効成分が減ること
血中濃度:血液中に溶けている薬の濃度
有効域(治療域):
安全に薬の効果が出る血中濃度の範囲
中毒域(危険域):
副作用や毒性が出やすくなる濃度範囲
要注意】肝機能・腎機能が低い方
• 肝機能が低い → 代謝できず、血中濃度が高くなりやすい
• 腎機能が低い → 排泄されにくく、薬が体内に残りやすい
→ いずれも副作用リスクが高まるため、慎重な投与が必要!
 | 【完全攻略】医薬品「登録販売者試験」合格テキスト 2021年版 [ 藤澤 節子 ] 価格:3520円 |