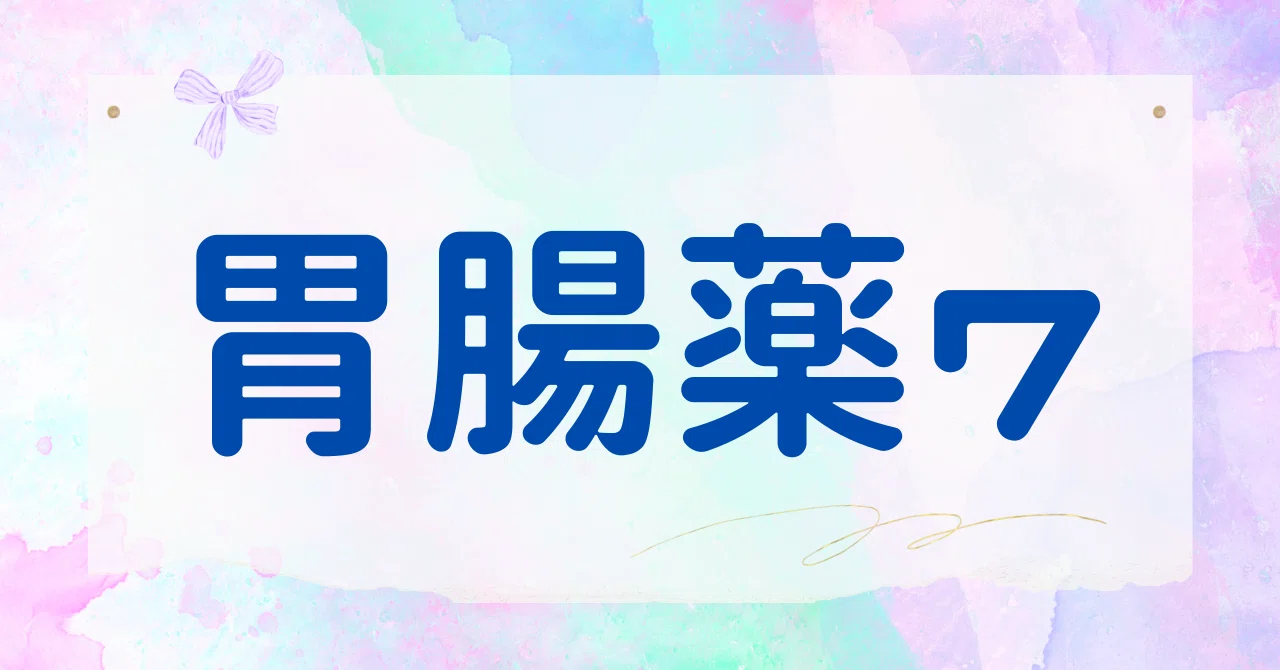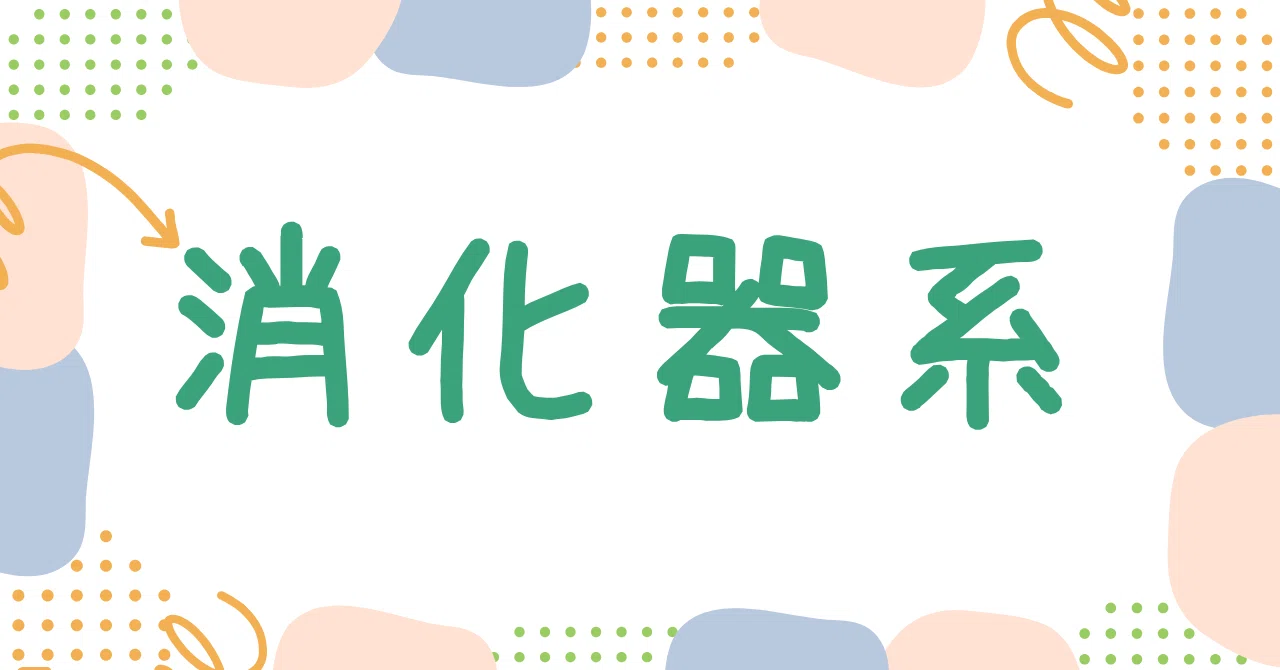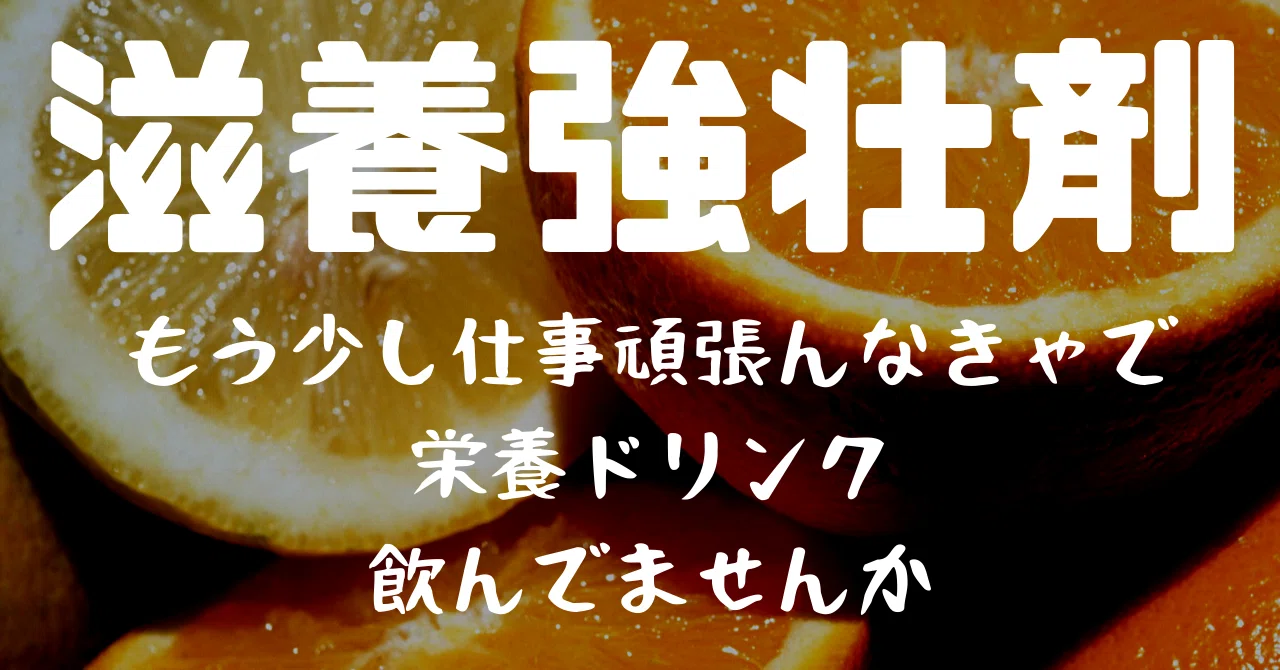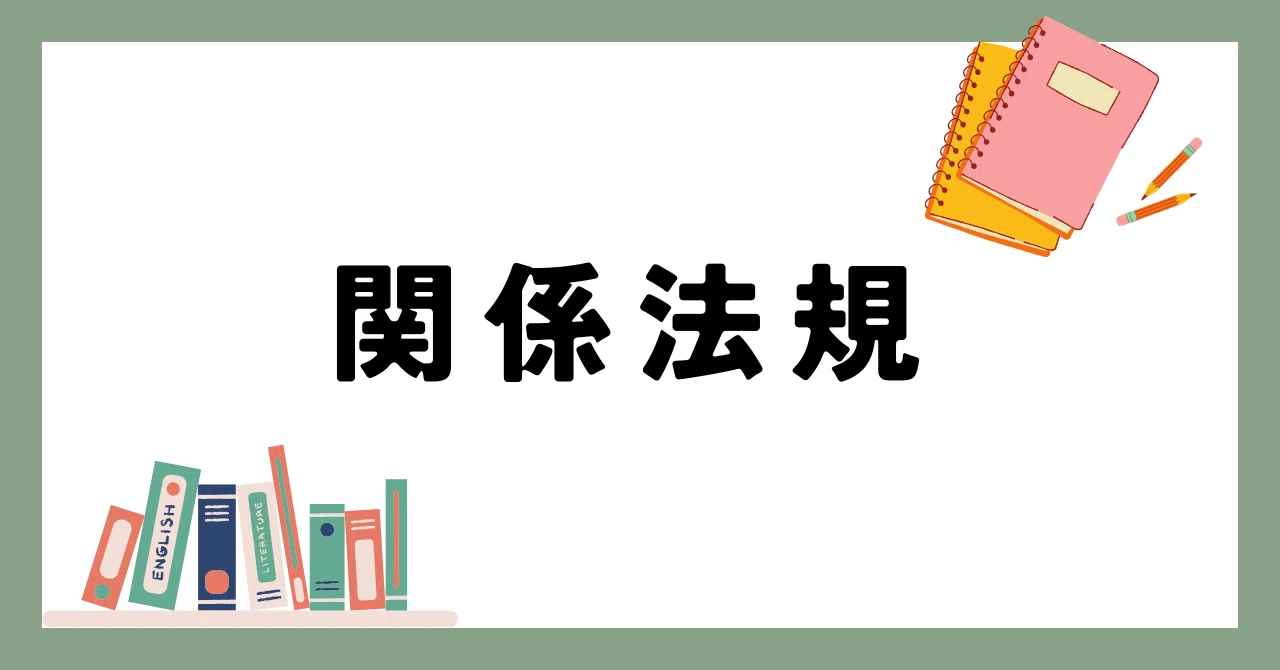登録販売者#12体の仕組み⑦脳・神経系

脳や神経系の働き
神経系は「中枢神経系」と「末梢神経系」に大きく分けられ、それぞれに異なる役割があります。
❶ 中枢神経系(脳と脊髄)
脳
• 主に思考・感情・記憶・運動などを司る。
• 脳血流は全身の約15%、酸素消費は約20%、糖の消費は25%。
• 脳幹(延髄・橋・中脳)は呼吸や心拍を調整。
• 間脳(視床・視床下部):ホルモン分泌や自律神経の中枢。
・脳の血流を一定に保つしくみを 血液脳関門(BBB) といいます。
脊髄
• 脳と末梢神経をつなぐ中継路。
• 一部は脊髄だけで反射的に反応(=脊髄反射)。
❷ 末梢神経系
末梢神経系は以下の2つに分類される。
| 分類 | 働き |
| 体性神経系 | 意識して行う運動 (随意運動)知覚や感覚 |
| 自律神経系 | 呼吸・消化、循環、発汗等 無意識で生命活動の維持 |
自律神経の2つの顔
自律神経は「交感神経」と「副交感神経」からなり、一方が働くと、もう一方は抑えられる仕組み(=二重支配)になっています。
| 神経 | シチュエーション |
| 交感神経 | 戦う・逃げる |
| 副交感神経 | リラックス |
⭐︎交感神経が働くと…
- 瞳孔が拡がる(視野拡大)
- 心拍数が増える(ドキドキ×ドキドキ)
- 血圧が上がる、気管支が拡がる
⭐︎副交感神経が働くと…
- 胃腸が活発になる(消化促進)
- 心拍数が減る(リラックス)
- 尿の排出が促される(排泄モード)
交感神経と副交感神経の薬理作用
| 神経 | |
| 交感神経 | ノルアドレナリン |
| 副交感神経 | アセチルコリン |
●アドレナリン作動成分(交感神経を刺激)
⇒ 血管収縮、気管支拡張など。風邪薬や点鼻薬によく含まれる。
例えば、咳がひどくて苦しい時交感神経優位にして気道を広げると呼吸が楽になる。という仕組みです。
●抗コリン成分(副交感神経の働きを抑える)
⇒ 鼻水・涙を減らす、胃腸の働きをおさえるなど。
コリンとは、アセチルコリンの事でリラックス状態で出る物質と考えて下さい。それの「抗」=アンチなので、食欲や排泄、唾液や鼻水といった人が休息時に行われる現象がストップします。
(この作用は多くの場合、副作用としても現れてしまうので大事な所です。)
| 効果器 | 交感神経 | 副交感神経 |
| 瞳孔 | 散大 | 収縮 |
| 唾液腺 | 少量・粘性 | 多量・漿性・ |
| 心拍数 | 増加 | 減少 |
| 抹消血管 | 収(血圧UP) | 拡(血圧DOWN) |
| 気管・気管支 | 拡張 | 収縮 |
| 胃 | 血管収縮 | 胃酸分泌亢進 |
| 腸 | 低下 | 亢進 |
| 肝臓 | グリコーゲン分解 | グリコーゲン合成 |
| 皮膚 | 立毛筋収縮 | / |
| 汗腺 | 発汗亢進 | / |
| 排尿筋 | 弛緩 | 収縮 |
抗コリン成分
(例:かぜ薬、乗り物酔い薬、鼻炎薬などに含まれる)
乾き・眠気・目の異常…高齢者や緑内障の人は要注意。
抗コリン成分は、副交感神経の働きを抑えることで、鼻水・くしゃみ・吐き気・めまいなどの症状を和らげる目的で使われています。しかしその一方で、口の渇き、便秘、排尿困難、視力のぼやけ、といった副作用が出やすい成分でもあります。
特に高齢者では、もともと排尿障害や緑内障を持っている人が多く、抗コリン作用によって症状がさらに悪化する恐れがあります。また、眼圧を上げたり、緑内障を進行させたりするため、眼の病気を持つ人にも注意が必要です。
眠気も強く出ることがあり、服用後の車の運転や高所作業、精密機器の操作などは避けるべきです。中には、ぼんやりする、判断力が鈍るといった認知機能への影響も報告されており、日常生活に支障をきたす場合もあります。
「ちょっと鼻水が気になるから」「風邪気味だから」という目的で安易に服用すると、思わぬリスクを招くことも。体調や年齢に応じて、抗コリン成分の入った薬は慎重に使いましょう。
 | 【完全攻略】登録販売者試験合格テキスト&問題集 試験問題の作成に関する手引き 準拠 [ 藤澤節子 ] 価格:3960円 |