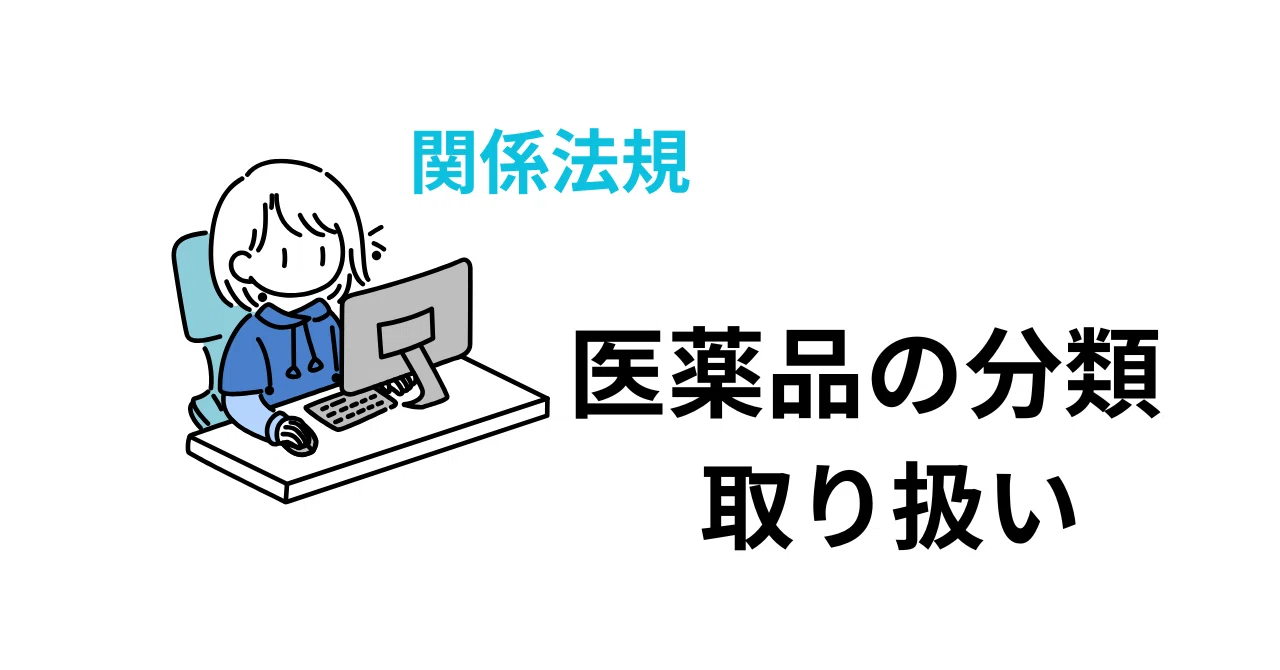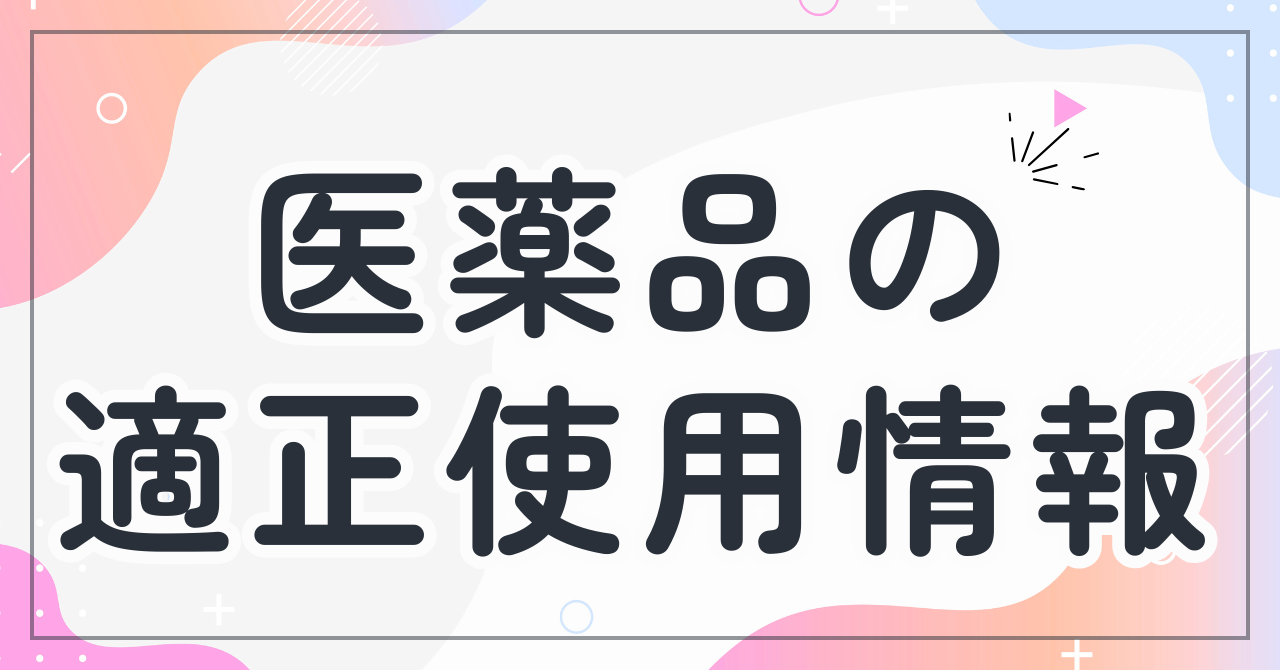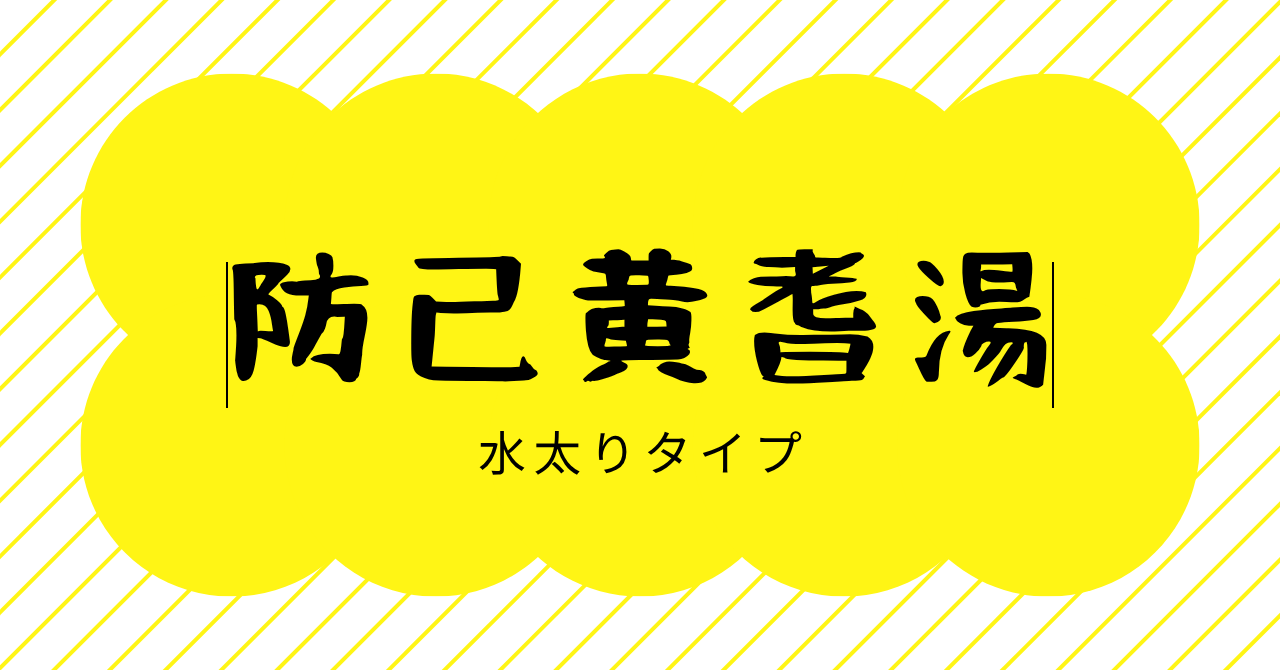登録販売者試験 関係法規#17医薬品販売での法令遵守

第1回:医薬品販売広告に関する規制
1. 誘引広告等の禁止
• 虚偽誇大広告の禁止(法66条1項)
医薬品等の名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽または誇大な記事を広告・記述・流布することは禁止。違反した場合は懲役・罰金の対象となる。
また、効能・効果または性能に関して「保証したもの」と誤解されるおそれのある広告も誇大広告に該当する。
また、医薬品等に関して堕胎を暗示し、またはわいせつな文書、図画を用いてはならない。
• 承認前広告の禁止(法68条)
「承認前」の医薬品等の名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告は禁止。違反者は懲役や罰金に処される。
• 虚偽の誇大表示の禁止(法66条3項)
虚偽や誇大の表示を暗示し、事実と異なる広告をすることは禁止。違反した場合は刑事罰あり。
ポイント:「何人も」とは広告主だけでなく、すべての人に適用される規制。
2. 規制対象となる広告
規制の対象はマスメディア広告だけではなく、
• 薬局・店舗販売業者・配置販売業者が使う チラシ・ダイレクトメール・POP広告
• 店頭ディスプレイ・カード等
すべてが規制対象となる。
条件は以下の通り:
1. 顧客を誘引する意図が明確であること
2. 特定医薬品の名称が明示されていること
3. 一般人が認識できる状態であること
3. 医薬品広告を規制する法律
医薬品医療機器等法による規制や、保健衛生の規制により、不当な表示による顧客誘引の防止のため。
• 景品表示法:不当表示を防ぐ
• 特定商取引法:不当な勧誘を防ぐ
●厚生労働大臣、都道府県知事
虚偽誇大広告、承認前広告に違反した者に対し、その行為の中止、再発防止等の措置命令を行える。
●課徴金制度:課徴金額として、それらの広告(違反)期間の対象商品の売り上げ額×4.5%
厚生労働大臣が納付命令
●過剰な消費や濫用を助長する広告は不適切である。
☆事実に反する認識をさせるおそれがある広告
• 漢方処方製剤などでは、使用する人の体質等を限定したうえで特定の症状等に対する改善を目的としています。
• その際「効能・効果に一定の前提条件(=しばり表現)」がついている場合があります。
• これを省略して広告することは認められていません。
• 漢方処方製剤の場合、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当です。
• 個々の生薬が相互に作用して効能を発揮するため、単体の作用だけを強調してはならないのです。
• 一般用医薬品と同じ有効成分を含んでいても「医療用医薬品の効能・効果」をそのまま標榜することは不可。
• 一般用医薬品として承認された効能効果の範囲で表示・広告しなければなりません。
• 一般用医薬品は「軽度の疾病や不快な症状の初期段階」に用いることが前提。
• 「がん」「糖尿病」「心臓病」などの治療を目的とした表現は自己治療が可能であるかのような誤解を与え、不適切です。
• 医薬品の有効性・安全性が確実である保証の表現は禁止されています。
•明示的、暗示的であるにかかわらず誇大広告として規制を受ける。
• 「使用前・使用後」で分かる図面や写真を提示することも、誤解を与えるため禁止。
• 「絶対効く」「日本一安全」などの最大級表現も不適切とされています。
• チラシやパンフレットで「医薬品と医薬品ではない製品」を同一紙面に掲載すること自体は可能。
• しかし、医薬品でない製品について「医薬品的な効能・効果がある」と誤認される恐れがある場合は、承認前広告の禁止(法第68条)に違反します。(医薬品でない物は承認されていない=承認前という事のよう)
2. 過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告
• 「医薬品が不要な人」まで使用を促す広告はNG。
• 「天然成分だから副作用がない」といった事実に反する広告表現も禁止。(過度に摂取を煽る事以外にも虚偽、誇大広告にも該当)
公認・推薦・運用表現の禁止
• 医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が「公認」「推薦」「運用」していると誤認させる広告も不適切です。(○○大学で認められた!!等)
• 仮に事実であっても、一般生活者への影響が大きいため原則禁止。
化粧品的表現の禁止
• 「食品的な表現」や「化粧品的な用途」が強調されている場合、医薬品の誤使用や過剰使用を助長するおそれがあるため禁止されます。