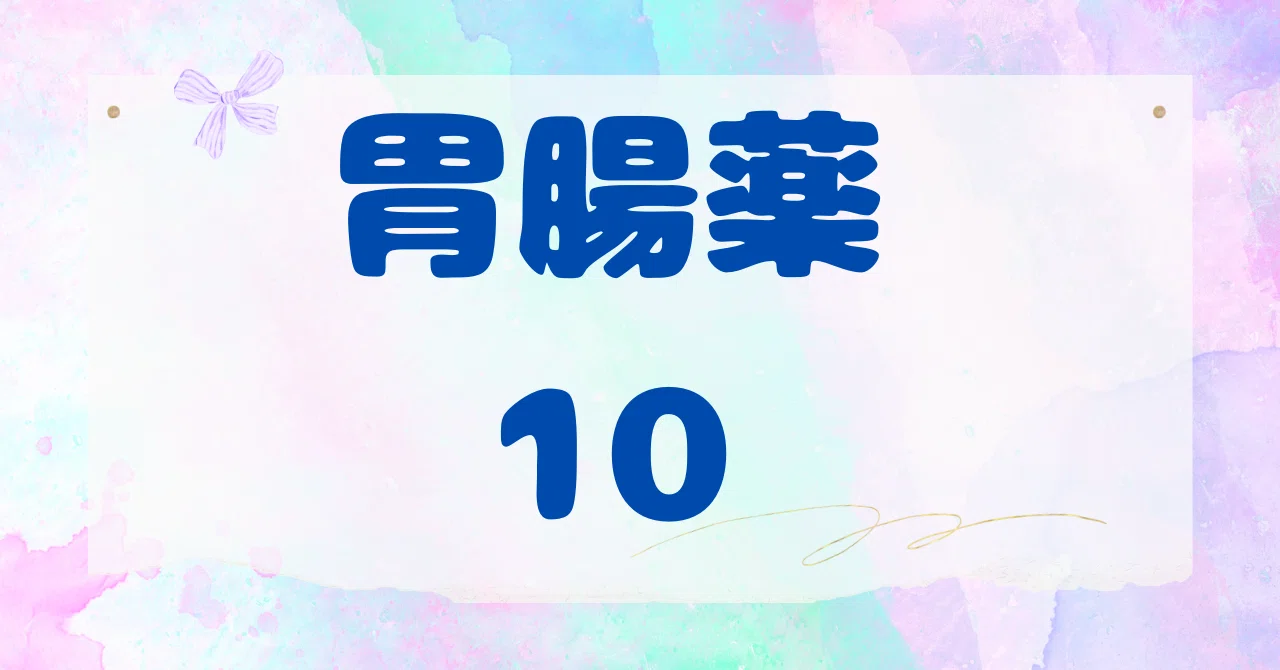登録販売者試験#15殺虫剤・忌避剤

殺虫剤や忌避剤は、私たちの生活に身近な医薬品等ですが、登録販売者試験ではそれぞれの違いや有効成分の知識が問われます。
⸻
殺虫剤と忌避剤の違いとは?
● 医薬品か医薬部外品として医薬品医療機器等法の対象
• 殺虫剤・忌避剤は、ハエ・ダニ・蚊などの衛生害虫の防除を目的としています。
• 一般的に、人体への作用が緩和なものは医薬部外品、強く持続的に作用するものや劇薬に該当するものは医薬品として扱われます。
(医薬品に該当する物のイメージとして、ある一定の注意が必要で、原液を希釈して用いたり、作用が長期間にわたるもの。また一回の作用が強烈のもの)
ポイント!
忌避剤は、虫が「近寄らないようにする」ためのもので、刺された後のかゆみや腫れを抑える効果はありません。
⸻
主な殺虫成分の種類と特徴
殺虫剤に使われる成分は、大きく次のように分類されます。
| 1. 有機リン系殺虫成分 |
| 主な成分 ジクロルボス、フェニトロチオン、トリクロルホン、クロルピリホスメチル 、ダイアジノン、プロペタンホスなど |
| 特徴 神経伝達物質アセチルコリンを分解する酵素を不可逆的に阻害して、アセチルコリンの過剰が起こり毒性自体は低いが作用が強い、神経を興奮状態にする。筋肉麻痺・けいれん,縮瞳、呼吸困難などが出ることも。 |
| 2. ピレスロイド系殺虫成分 |
| 主な成分 ペルメトリン、フェノトリン、フタルリン など |
| 特徴 除虫菊から開発された成分。蚊取り線香が代表的。神経細胞に直接作用して神経伝達を阻害。比較的毒性が低く、自然分解しやすいので家庭用に広く使われる。 フェノトリンは、人には直接の毒性がないため唯一使える、シラミ駆除薬などにも使われます。 |

https://www.kincho.co.jp/seihin/insecticide/shirami/sumithrin_l(KINCHO)
/
| 3.カーバメイト系・オキサジアゾール系成分 |
| 主な成分 プロポクスル(カーバメイト系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系) |
| 特徴 有機リン系と同じく、アセチルコリンエステラーゼと可逆的に結合して神経を興奮させる。毒性は比較的低い。ピレスロイド抵抗性の害虫に使われる。 |

https://www.earth.jp/products/tokojiramigokiearth-450/index.html(
アース製薬)
/
| 4. 有機塩素系成分 |
| 主な成分 オルトジクロロベンゼン |
| 特徴 体内蓄積性があり、神経細胞に作用して殺虫。ボウフラ駆除などに限って使用される。 |
昆虫成長阻害成分(IGR)
幼虫から成虫になる過程を妨げるタイプ。直接殺虫はしないが、変態や脱皮を阻害します。
| 成分 | 特徴 |
| メトプレン、ピリプロキシフェン | 幼虫が「さなぎ」になるのを防ぐ。成虫にならない不完全変態の昆虫には効果がない。 |
| ジフルベンズロン | 幼虫の正常な脱皮をできなくする。 |
殺虫補助成分
| 成分 | 特徴 |
| ピペニルブトキシド(PBO)、チオシアノ酢酸イソボニル(IBTA) | 殺虫効果を高める目的で配合される成分です。 |
忌避成分(虫よけ成分)
| 成分 | 特徴 |
| ディート | 年齢制限や使用回数制限がある。 蚊、ブヨ、アブ、マダニ以外にノミ、ヤマビル、トコジラミなど広くに効果。 |
| イカリジン | 年齢制限なく使え、ディートに比べ肌刺激が少ない。 蚊、ブヨ、アブ、マダニに有効 |
虫が寄ってくるのを防ぐ効果あり。ディートは広範囲に有効だが、刺激性があるため注意が必要。イカリジンは年齢制限がなく安全性が高い。
ディート:海外では神経毒性が言われており、生後6ヶ月から12歳までは顔への使用は避ける。また、1日の使用制限として6ヶ月から2歳は1日1回。2歳から12歳は1日1〜3回となっています。年齢別に濃度を変えて販売されている商品もあります。裏書を良く読みましょう。

https://www.earth.jp/saratect/safety/deet(アース製薬)
殺虫剤の会社のホームページはとても充実しており、楽しく読めます。販売する際困ったら一度確認するといいでしょう。
服や帽子に振りかけるだけなのか、素肌につけるのか。誰に使うのか?どこに使うのか?製品の表示をよく見て、お客様のニーズに合わせて選べるようにしましょう。
春から秋にかけて様々な虫が発生し、 かゆいだけならまだしも炎症を起こしたり、毒性のある虫もいます。また蚊やダニのようにウイルスや細菌を媒介する虫もいます。農作業やアウトドア、海外旅行などニーズは様々です。
使用上の注意
1,同じ成分の物を使い続けない。虫がその成分に抵抗性をもってしまい,その成分の物をおいたりまいたりしても意味がなくなる。色々な成分のものを順番に使用するのが効果的。
2、もし体に付着してかぶれたり、吸引、飲み込んだりした場合はなんの成分だったか分かるもの、(その製品を病院へもって行ってもらうと良い)持参し受診するようお伝えする。
3、忌避剤では、耳なし芳一では無いですが、ムラなく塗り残しの無い様使用。粘膜や発疹、傷のあるところは避ける。スプレータイプの目や口への付着や吸入に気をつける。手にとって塗っていただく。
4、子供の手の届かない場所に保管してください。
今までの生活で殺虫剤を使ったことのない人は少ないのではないかと思います。振りかけたり、置いておくタイプ、バルサンのように煙を一気に噴霧して追い出したり。農業での使われ方にはあまり詳しく無いのですが、虫との戦いは多そうです、地域によっても選ばれる殺虫剤は違ってきそうですね。
映像内の表がうまくいっていませんがとっかかりにという気楽な気持ちで見てください。