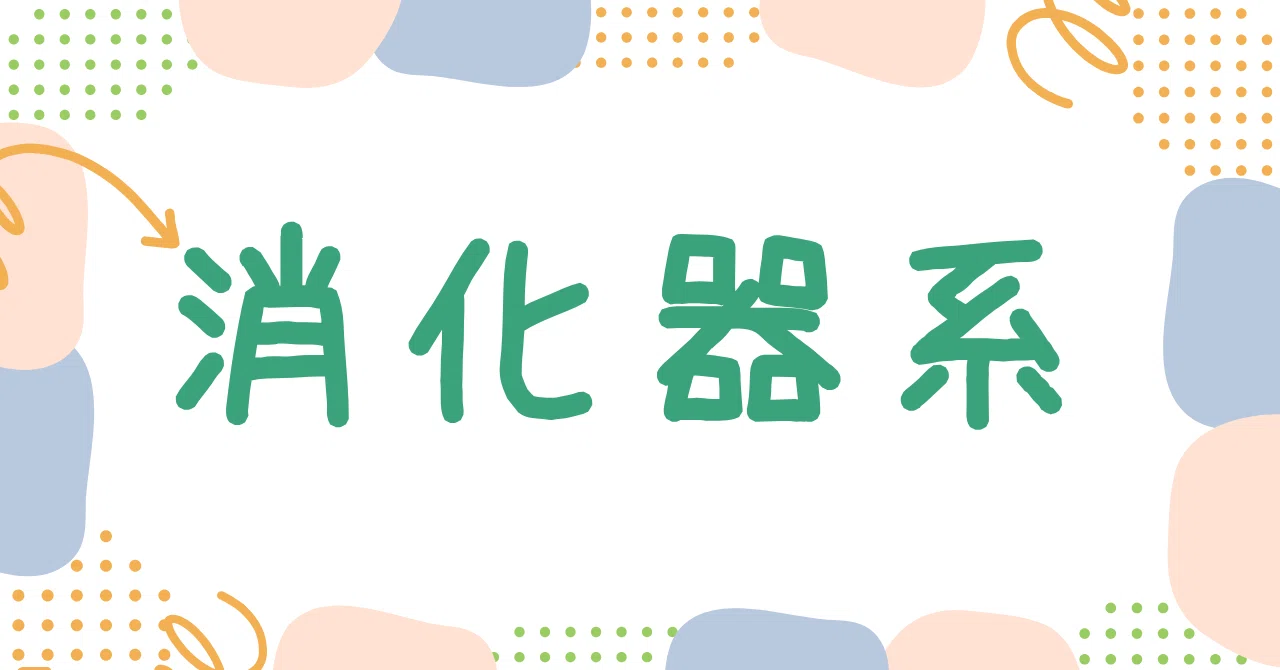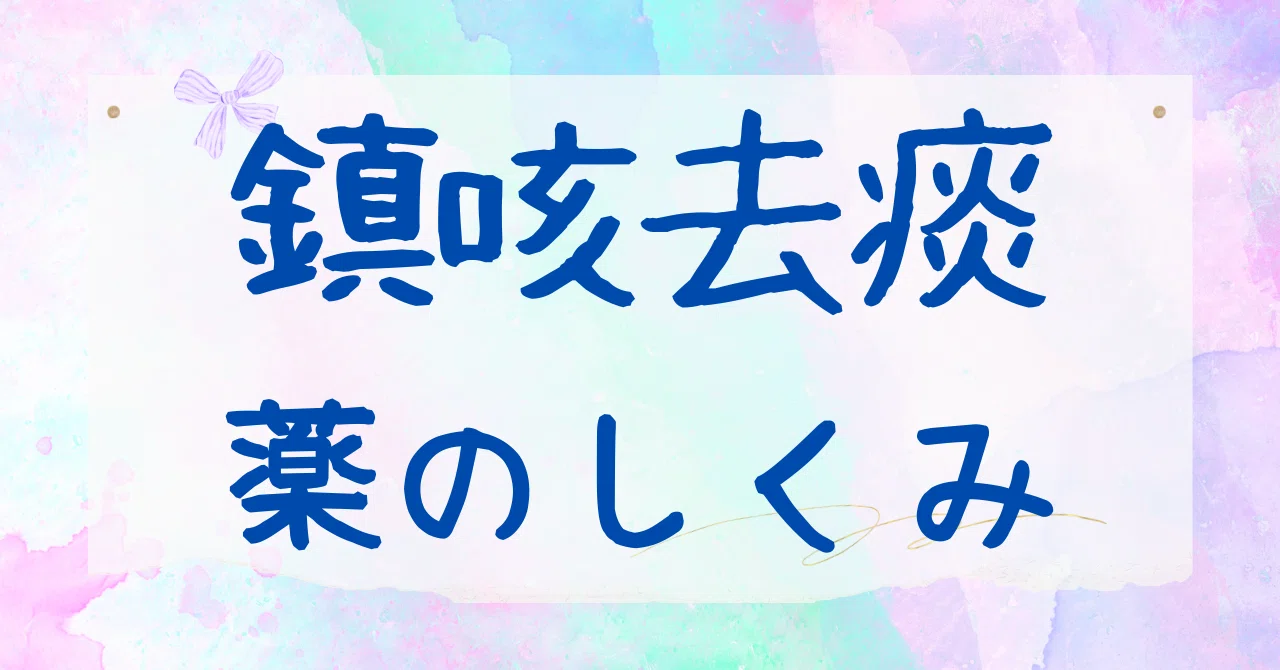登録販売者試験 関係法規#4リスク区分に応じた販売方法
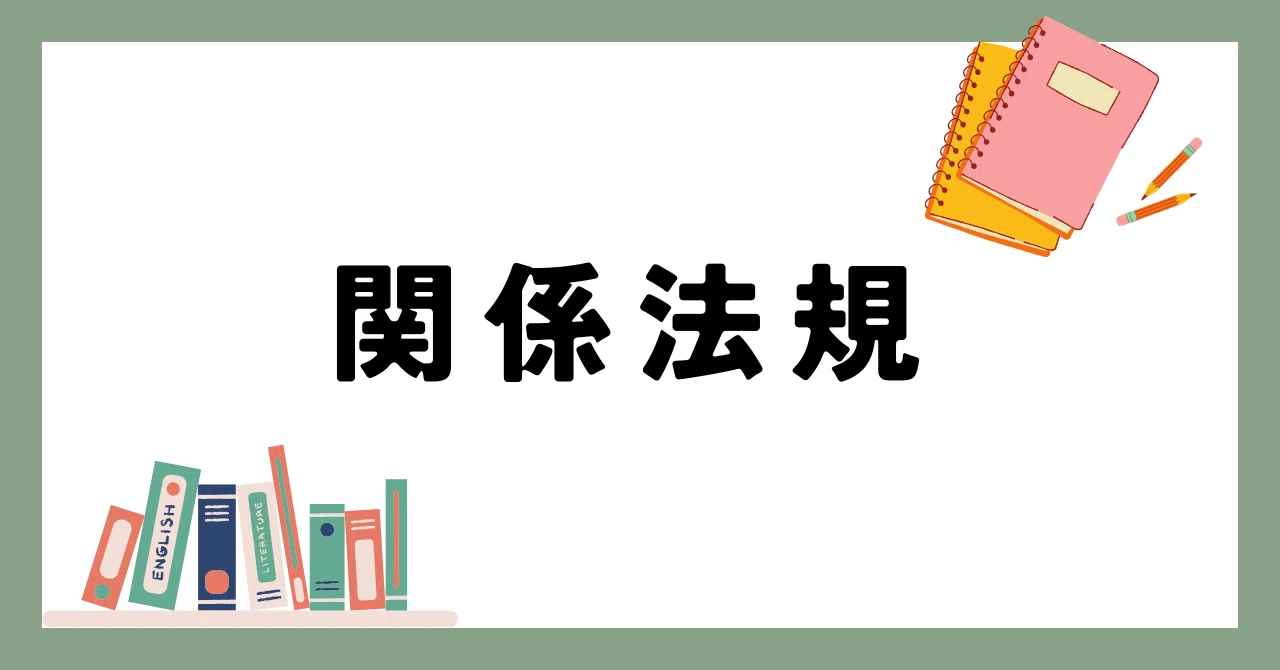
医薬品のリスク区分と販売従事者・販売方法の違いを整理!
医薬品はそのリスク(副作用や使用方法の難易度など)に応じて、「要指導医薬品」「一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)」に分類されており、それぞれに対応できる販売従事者や販売方法が法律で定められています。
⸻
1.要指導医薬品
🔸販売従事者
• 薬剤師のみが販売可能
• 登録販売者は販売できません!
🔸販売相手の制限
• 「使用しようとする本人」にしか販売できない
• 代理人や、薬剤師の判断により不適切とされる人には販売不可
🔸販売方法(販売時の流れ)
1. 販売相手が使用者本人であることを確認
2. 使用目的・状態を確認し、必要数のみ販売
3. 情報提供を受けた内容を理解しているか確認
4. 質問がないか確認
5. 相談があった場合は情報提供を行った後に販売
6. 医薬品の名前、販売店舗名・連絡先を伝える
⸻
2.一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)
| 医薬品区分 | 販売従事者 | 販売方法の注意点 |
| 第一類医薬品 | 薬剤師のみ | 購入者が情報提供を理解し、質問がないか確認したうえで販売。相談があった場合は情報提供後に販売可。 |
| 第2・3類医薬品 | 薬剤師又は登録販売者 | 原則、情報提供義務なし。ただし相談があった場合は、情報提供後に販売。販売者名、店舗名・電話番号の告知も必要。 |
これらの違いは実務でも極めて重要な知識です。試験でも「誰が」「どの医薬品を」「どう売るか」が問われやすいので、表形式で整理して頭に入れておきましょう!
小児の夜泣きや疳の虫に漢方処方を使う場合
(漢方処方製剤を小児の疳や夜泣きに用いる場合)
「漢方なら安心」は要注意。改善がなければすぐ中止を。
赤ちゃんや小児の「夜泣き」や「疳の虫(かんのむし)」に対して、漢方薬を使うことがあります。特に甘草や柴胡を含む処方がよく使われますが、「天然だから安心」「副作用がない」と思って使い続けるのは危険です。
1週間ほど服用しても症状の改善がみられない場合、それ以上の使用を続けることは避けましょう。なぜなら、体の未発達な小児では、漢方薬でも体に負担をかけることがあり、副作用が現れることもあるからです。
症状が良くならないときは、いったん服用をやめて、専門家に相談し、その子に合った処方かどうかを見極めることが大切です。自己判断はせず、「早く効いてほしい」と思うほど、慎重な対応が求められます。