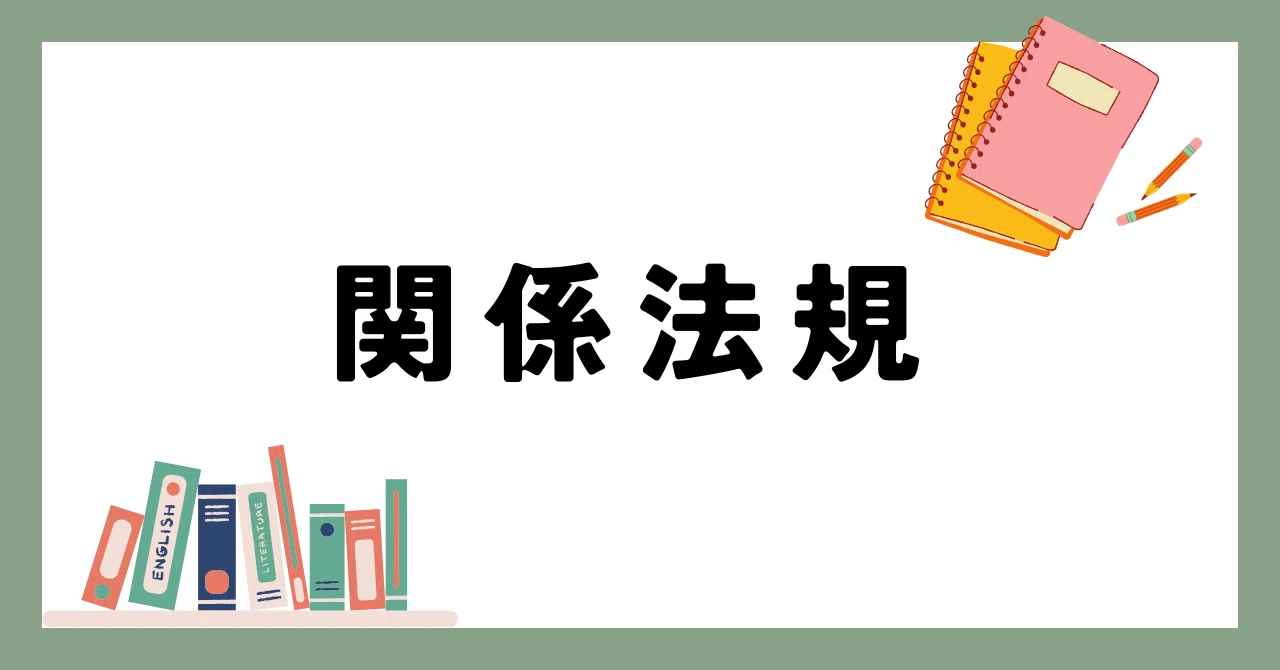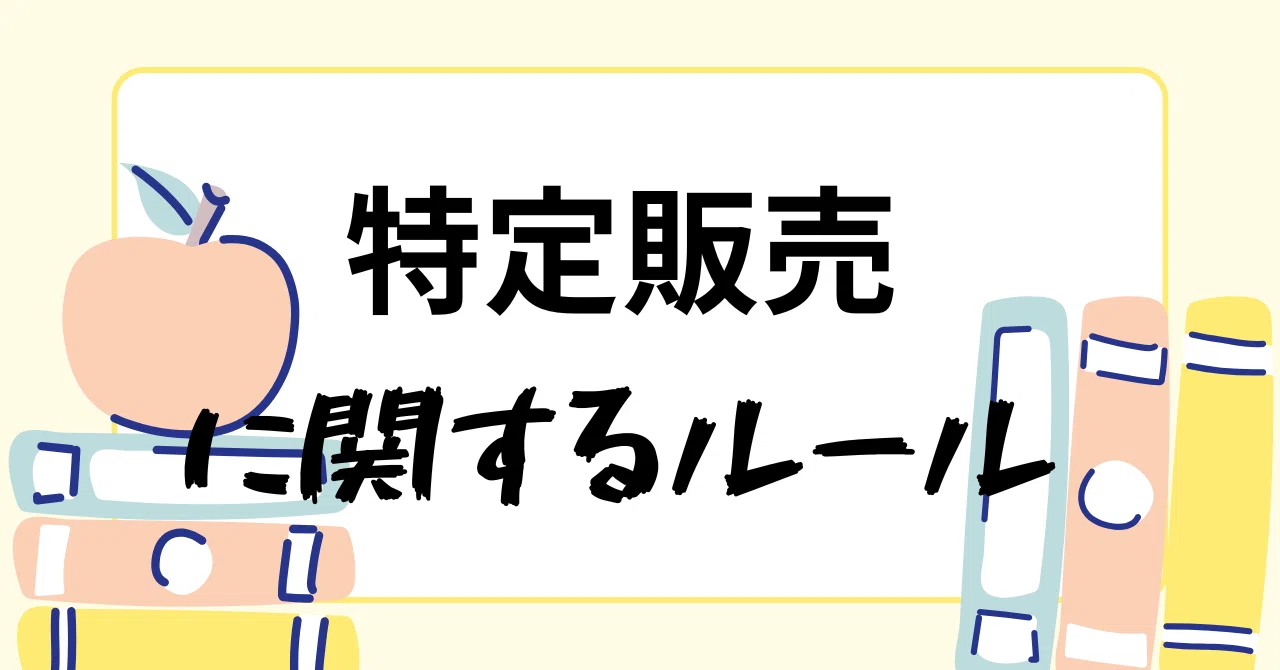登録販売者#8体の仕組み③血管、リンパ
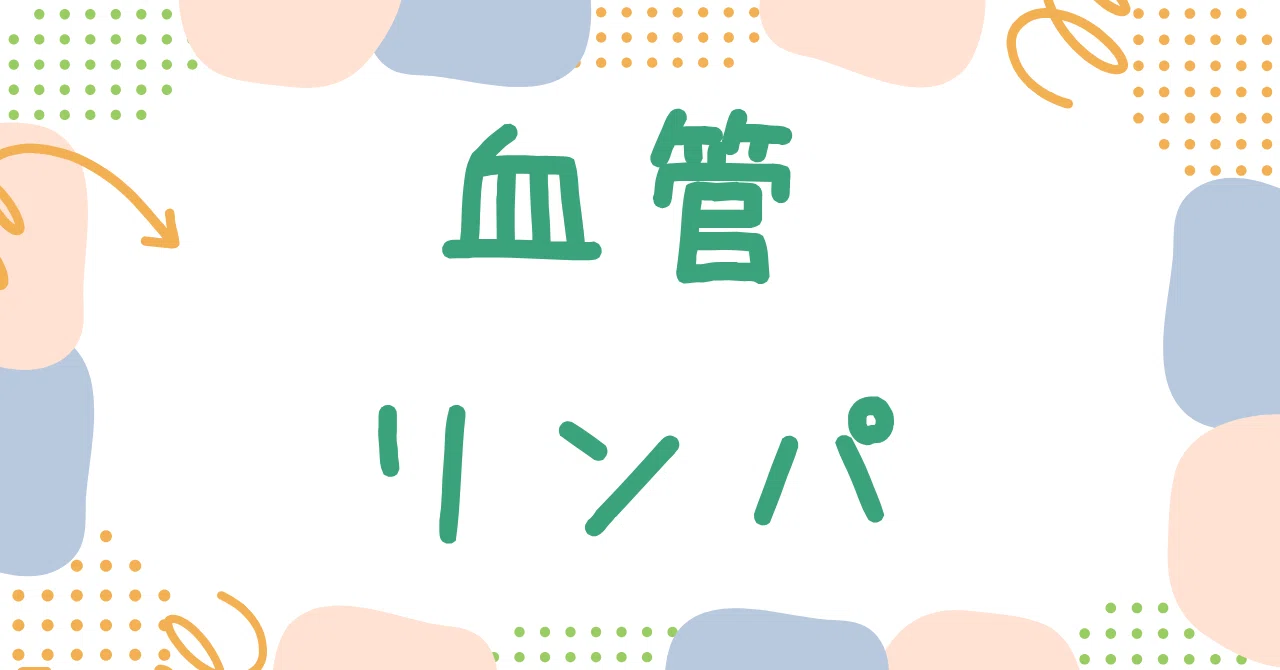
血管系(動脈・静脈・毛細血管)
動脈:心臓から血液を送る。弾力性あり、圧力に耐えられるが、高脂血症などで、血管内壁に蓄積し血小板もそれに伴い雪だるま式に血管内を埋めて血流が悪くなる、血管自体の弾力性の低下を引き起こす。
深部を通る。拍動を感じる。頸部、手首、肘の内側などは皮膚表面近くを通るため脈が触れる。
静脈:心臓へ血液を戻す、重力に負けて逆流しない様に弁が発達、皮膚近くを通り逆流防止弁がある。血管壁は動脈より薄い。
毛細血管:動脈と静脈をつなぐ極細の血管。酸素・栄養と二酸化炭素・老廃物の交換を行う。
血圧=血管壁にかかる圧力。
最大血圧:心臓が収縮したとき
最小血圧:心臓が拡張したとき血管壁の収縮、時間は自律神経に支配されています。
血液の成分と役割
成分
血漿(けっしょう):水90%以上、アルブミン・グロブリン・脂質・糖質・電解質など。
血球:赤血球、白血球(好中球・リンパ球・単球)、血小板
血液の主な働き
酸素と栄養素の運搬
二酸化炭素と老廃物の排出
ホルモン・体温の調整
免疫・止血
血球の働きと種類
酸素と結合するヘモグロビンを含む(鉄分が含まれるタンパク質)。酸素濃度の多いところで、酸素と結合し、少ないところで二酸化炭素と交換する。ココでヘモグロビンが少ないと貧血状態になる。
骨髄で作られ、全体の約40%を占める。
貧血の種類:鉄欠乏性、ビタミン欠乏性など。
好中球:食作用、白血球の60%(最多)
リンパ球:白血球の1/3、リンパ組織で増殖T細胞(異物を、認識)、B細胞(抗体を産生)
単球:白血球の5%、マクロファージに変化し貪食作用
肥満細胞
マクロファージは各器官に存在し、異物を排除(例:肺胞マクロファージ、クッパー細胞など)
損傷部位で粘着・凝集し止血。
フィブリノーゲン→フィブリン→血餅を形成。
血清
血清:血液が凝固し沈殿した後の上澄。血漿からフィブリノゲンを、除いた物。
脾臓の役割
古くなった赤血球の分解(マクロファージによる)
免疫の中枢のひとつ(リンパ球・リンパ組織が存在)
リンパ系(リンパ液・リンパ管・リンパ節)
リンパ液
血漿とほぼ同じ成分だがタンパク質少なめ。
リンパ球を含む。組織液の一部が再吸収されずにリンパ管へ入る。
リンパ管
逆流防止の弁があり、一方向に流れる。
合流して太くなり、最終的に鎖骨下の静脈に合流。
リンパ節
フィルターの役割を果たす結節。
リンパ球・マクロファージが集まり、細菌やウイルスを処理。
門脈
消化管を通っている毛細血管の大部分は門脈に集まり肝臓に運ばれて代謝や解毒後全身に循環される。
プソイドエフェドリン塩酸塩を含む医薬品
(例:風邪薬、鼻炎薬などに配合)
心臓や代謝系に影響大!持病のある方は慎重に。
プソイドエフェドリンは交感神経を活性化させる作用があり、鼻の通りをよくしたり、呼吸を楽にする目的でよく使われます。しかし、この作用によって心臓や血管系、さらには肝臓での代謝に強く影響を与えることがあります。
心疾患、高血圧、糖尿病、甲状腺機能亢進症などの既往がある人では、こうした病気を悪化させる可能性があるため注意が必要です。また、他のアドレナリン系薬剤と同様に中枢神経への刺激が強く、依存や興奮、不眠、排尿障害といった副作用が起こることもあります。
特に、モノアミン酸化酵素阻害薬(パーキンソン病治療薬など)との併用では副作用が強く出やすくなるため、薬の飲み合わせにも要注意です。