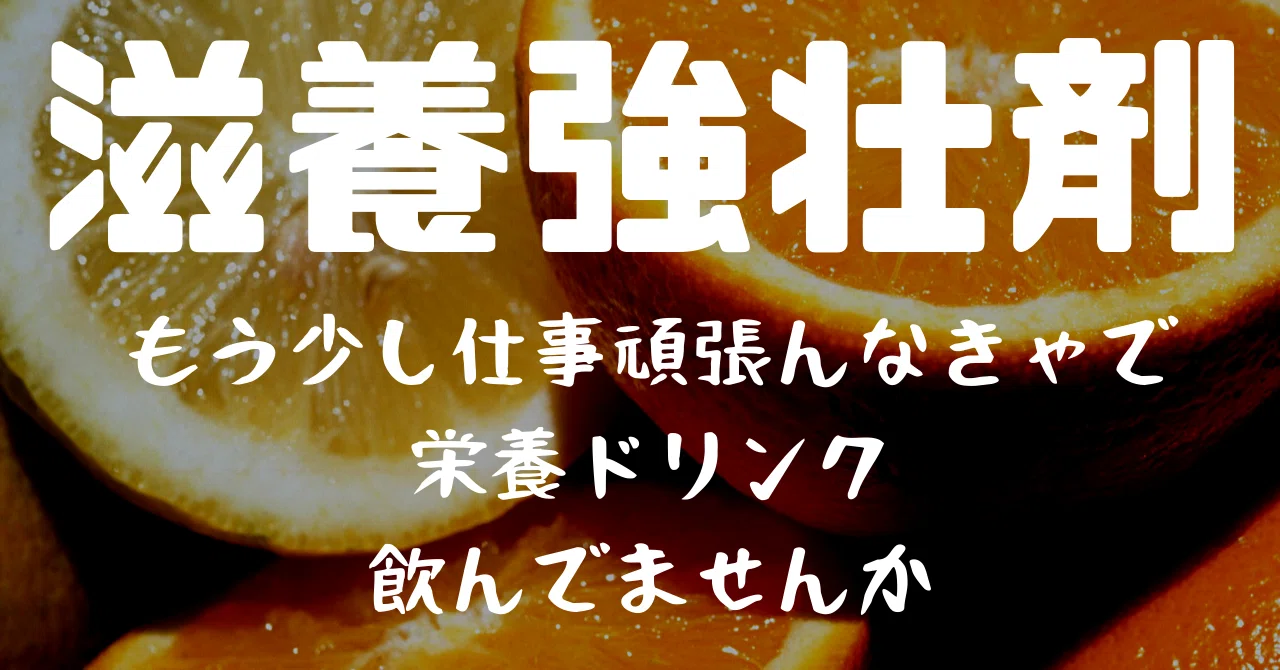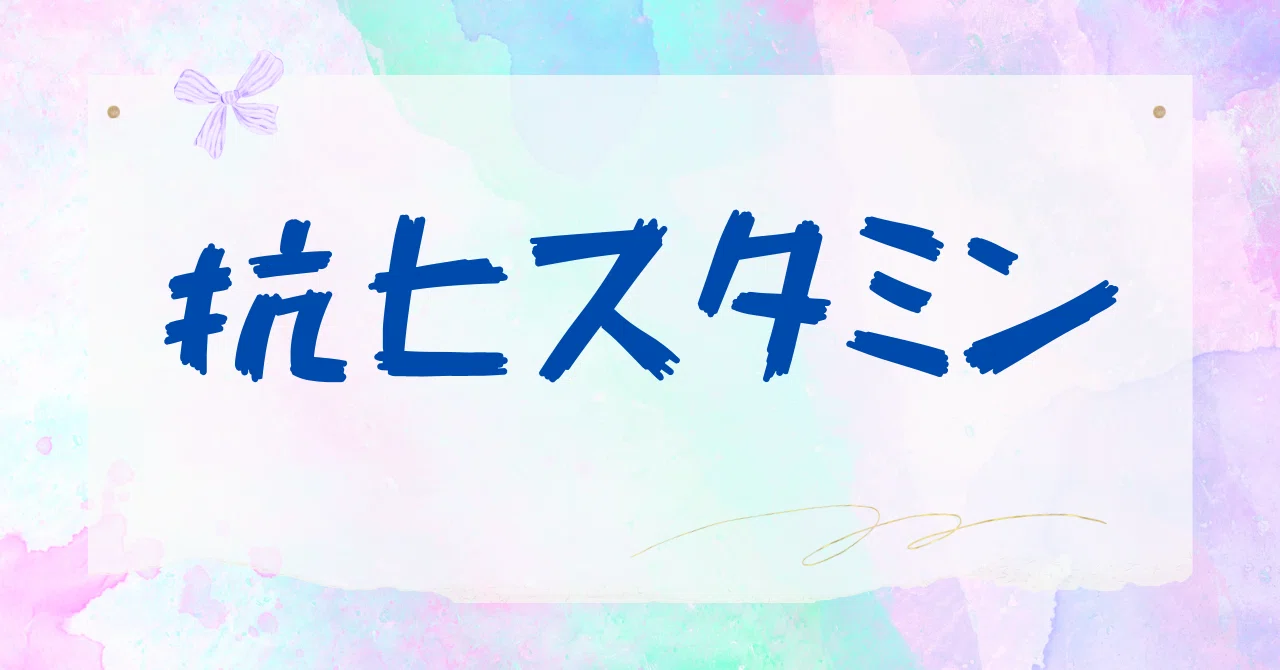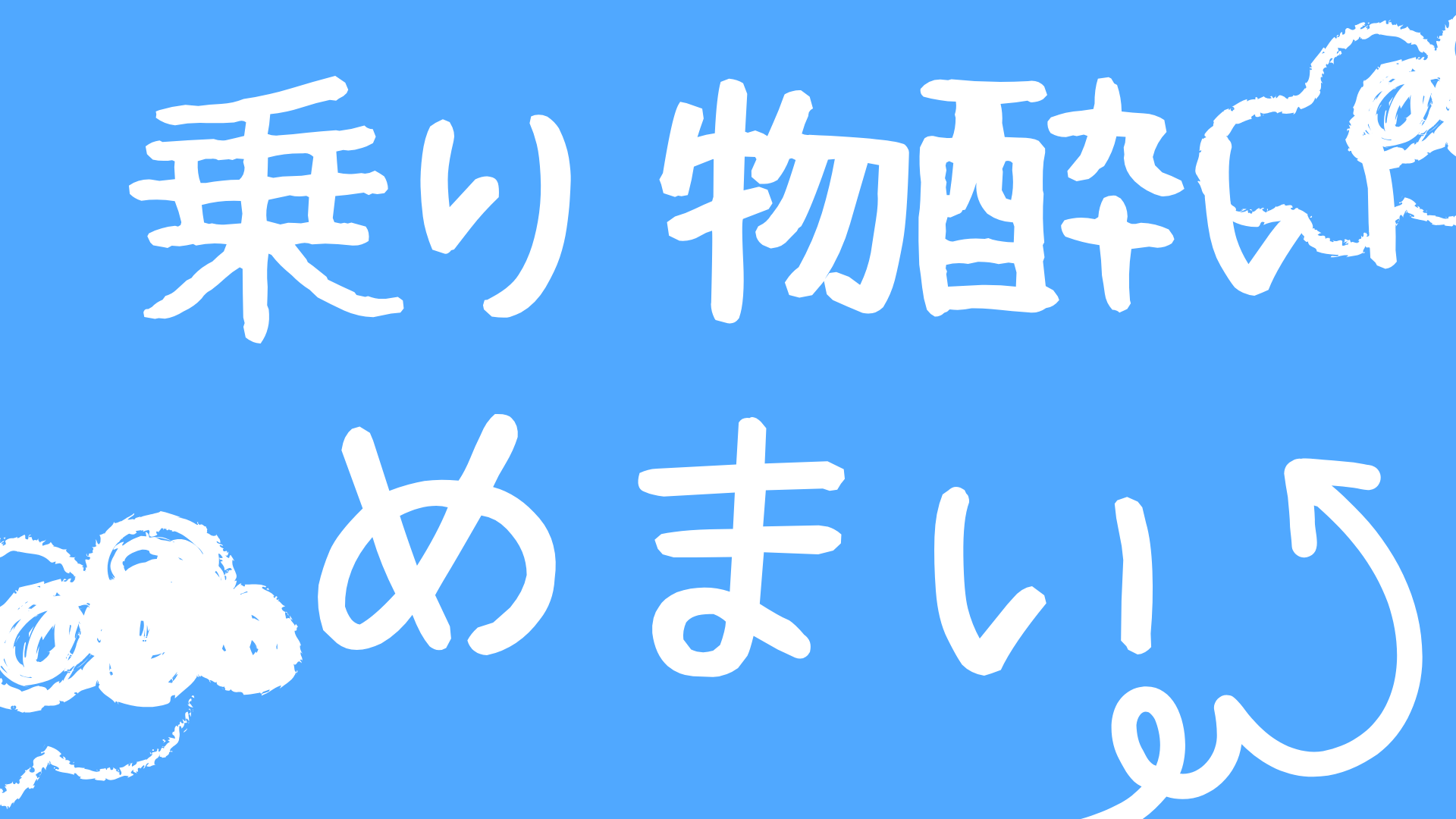登録販売者#5 体の仕組み①消化器系(前半)
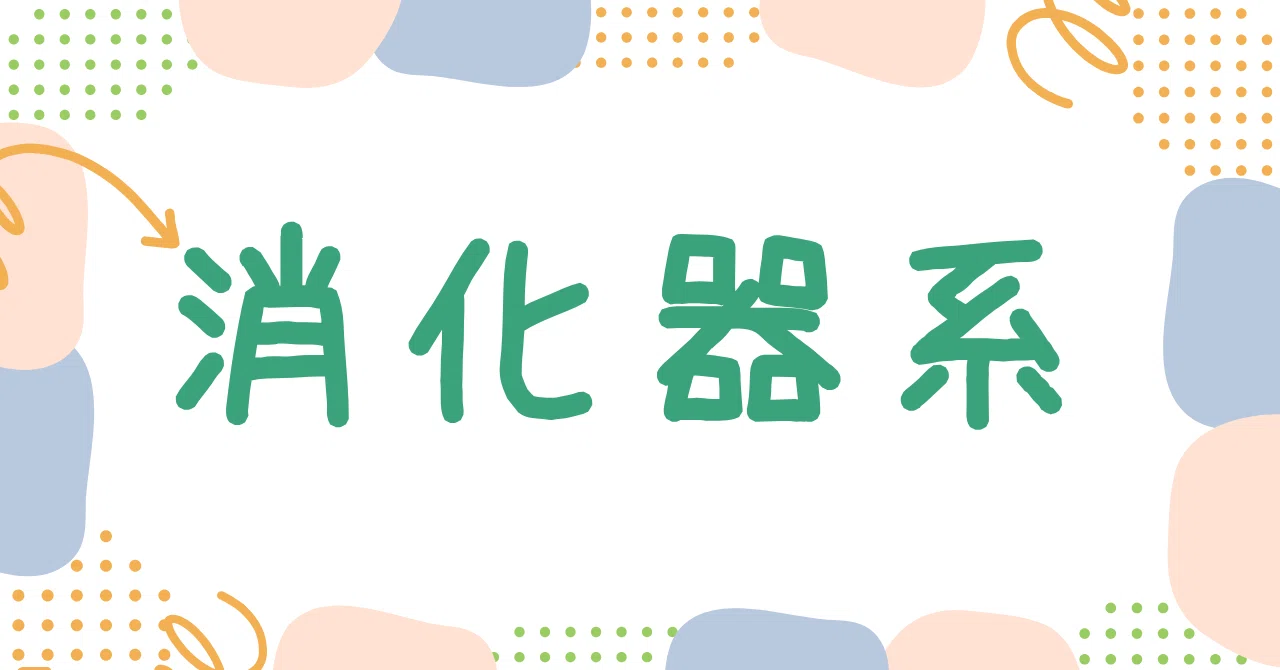
#登録販売者試験対策
登録販売者試験で頻出の「人体の構造と働き」。
中でも消化器系は、器官の名称・働き・消化吸収の流れをセットで理解することが合格のカギです。
この記事では、
- 人体の基本構造
- 消化器系の全体像
- 各器官の役割と試験ポイント
を、覚えやすく・つながりが分かる構成で解説します。
今回は、「人体の構造と働き」の中から「消化器系」について、登録販売者試験にも役立つよう、解説します。
1. 人体の構成単位とは?
私たちの体は…
細胞 → 組織 → 器官 → 器官系という順で構成されています。複数の組織が組み合わさって器官をつくり、それぞれが連携して体の働きを支えています。
2. 消化器系の主な器官とその働き
消化器系の目的:
食べたものを消化し、栄養を吸収し、不要なものを排出すること。
関連する器官:
消化管:口腔 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門
消化腺:唾液腺、肝臓、胆嚢、膵臓 など
消化には機械的消化(咀嚼、消化管の蠕動運動など)、化学的消化(消化液による)の2つがあります。
器官ごとの役割を見てみよう!
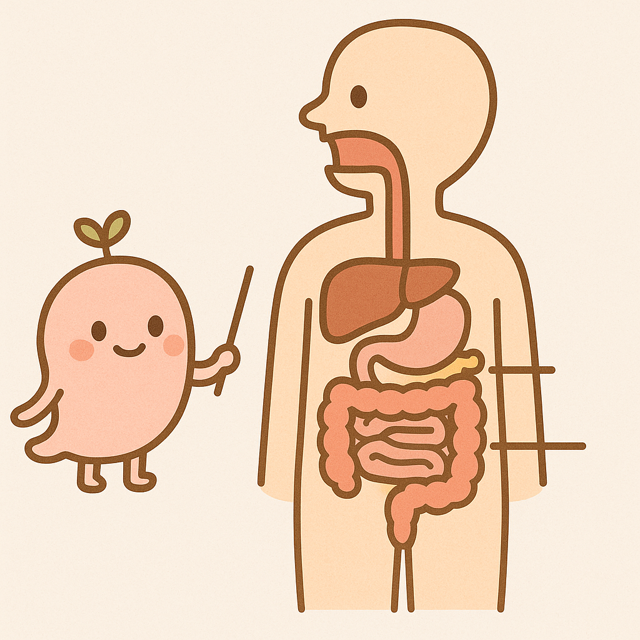
食べ物が口に入りスタート
歯
・歯は、食べ物を噛み砕いて消化を助けます。表面はエナメル質で覆われ、中には象牙質や神経・血管が通る歯髄があります。
ここまで虫歯が進むとしみたり痛みを感じる。
・体の中で一番硬いのは?→エナメル質
舌
舌には舌乳頭という突起があり「味蕾」が分布、味蕾が味を感知。また、唾液と混ぜて(攪拌)飲み込みやすくする役割も。
唾液腺
・唾液は食べ物を飲み込みやすくし、消化酵素(アミラーゼなど)を含んでいて、消化をサポートします。
・唾液アミラーゼが食物中のデンプンをデキストリンや麦芽糖に分解し甘味を感じられる。
・リゾチームなどの殺菌、抗菌物質を含んでおり、口腔内は健全に保たれる。
・pHはほぼ中性、酸による虫歯(う蝕)を防ぐ。
咽頭
食物路と気道が交わる所、嚥下時は候頭蓋が反射的に閉じる。
食道〜胃のしくみ
食道
・直径1〜2セcm程の筒状の器官。
・分泌腺は無い。
・口から飲み込んだ食べ物を胃へ送る管状の器官。重力ではなく、「蠕動運動」によって運ばれます
・上端と下端に括約筋があり、逆流を防いでいる。
胃の構造と働き
空腹時はぺたんこに縮んでいますが、食べ物が入ると伸びて消化活動を始めます。(胃適応性弛緩:平滑筋が弛緩し内容が拡がる。)
胃にある分泌腺
主細胞 ペプシノーゲン
副細胞 粘液
壁細胞 塩酸
胃では塩酸(胃酸)とペプシン(タンパク質分解酵素)を分泌し、食物を化学的に分解します。
胃の内壁は「粘膜」で覆われ、自己消化を防いでいます。
吸収
腸の働き
小腸は長さ6〜7mの管で、主に以下の3つの部位に分かれます:
十二指腸:胃とつながるC字型の最初の部分。胆汁と膵液が分泌されます。
空腸40%・回腸60%:微絨毛が密生していて栄養素の吸収を行います。パイエル板と呼ばれる免疫システムがある(特に回腸)
トリグリセリド(TG)はリパーゼ(消化酵素)により分解され小腸粘膜細胞より吸収され、吸収後再合成されトリグリセリドにもどる。脂溶性ビタミンは脂質と一緒に吸収される。
吸収のしくみ
内壁は「絨毛」「微絨毛」で覆われ、表面積が大きくなり効率的に栄養素を吸収できます。
脂質は「リパーゼ」などの酵素で分解され、「乳状脂肪(カイロミクロン)」として吸収されます。
消化と肝胆膵のはたらき:体の中のすごい工場
大腸〜直腸〜肛門の構造と働き
大腸(結腸)
• 範囲:盲腸(虫垂を含む)→上行結腸→横行結腸→下行結腸→S字結腸→直腸へと続く管状の構造
• 長さ・太さ:約150 cm、内径は約8 cm
• 主要機能:
• 小腸から送られてきた消化残渣から水分・電解質(Na⁺, K⁺, Cl⁻ など)を再吸収 → 固形便形成
• 腸内容物を蠕動運動で直腸へ送る
• 腸内細菌(700種類以上)が、発酵によって短鎖脂肪酸やビタミンK・B群を生成
直腸
• 位置・長さ:S状結腸から肛門管直前まで。長さは約12–15 cm
• 構造:粘膜・筋層・漿膜(直腸は漿膜が欠如のことあり)からなる。
機能:
• 便を貯蔵しつつ水分をさらに吸収 → 固形化を促す
• 広がることで排便刺激となる → 神経反射が働いて便意を起こす
• 粘液を分泌し、便の滑りを良くする
⸻
肛門管と肛門
• 肛門管の長さ:約2–4 cm、直腸と外界を結ぶ最後の部分
• 括約筋:
• 内肛門括約筋(自律神経支配・不随意) → 拡張して便を送り出す
• 外肛門括約筋(随意筋) → 排便タイミングを自分で調整可能
• 肛門の役割:
• 括約筋によって便の排出をコントロール
• 肛門洞からの粘液分泌で排便をスムーズにする
• 肛門部は痛み・熱・冷感など外界刺激を感知する豊かな神経分布がある
⸻
病気とトラブル(大腸〜直腸〜肛門領域でよく見られるもの)
• 大腸:便秘・下痢、IBS、炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)、ポリープ・大腸癌、憩室炎など
• 直腸・肛門:痔核・裂肛・肛門周囲膿瘍・瘻(ろう)、直腸脱、便失禁、肛門癌など
• 機能障害:骨盤底筋や括約筋の衰え(高齢者や出産後)、便秘や便失禁に関与
センナ、センノシド、ダイオウが配合された医薬品
(便秘薬、ダイエット目的の漢方など)
「自然だから安心」は間違い。刺激性下剤の使いすぎに注意!
センナやダイオウなどは、腸内で分解されることで腸を強く刺激し、排便を促す「刺激性下剤」の代表成分です。即効性がある反面、連用による“クセ”や“薬剤性便秘”のリスクが非常に高いのが特徴です。
センナには「センノシド」という成分が含まれており、これが腸内細菌によって分解されることで作用が発現します。そのため、下剤として使う場合には、適切なタイミング・間隔での使用が不可欠です。
便秘薬を日常的に服用している人は、一度自分の使用状況を見直し、生活習慣の改善や医師への相談も選択肢に入れてみましょう。