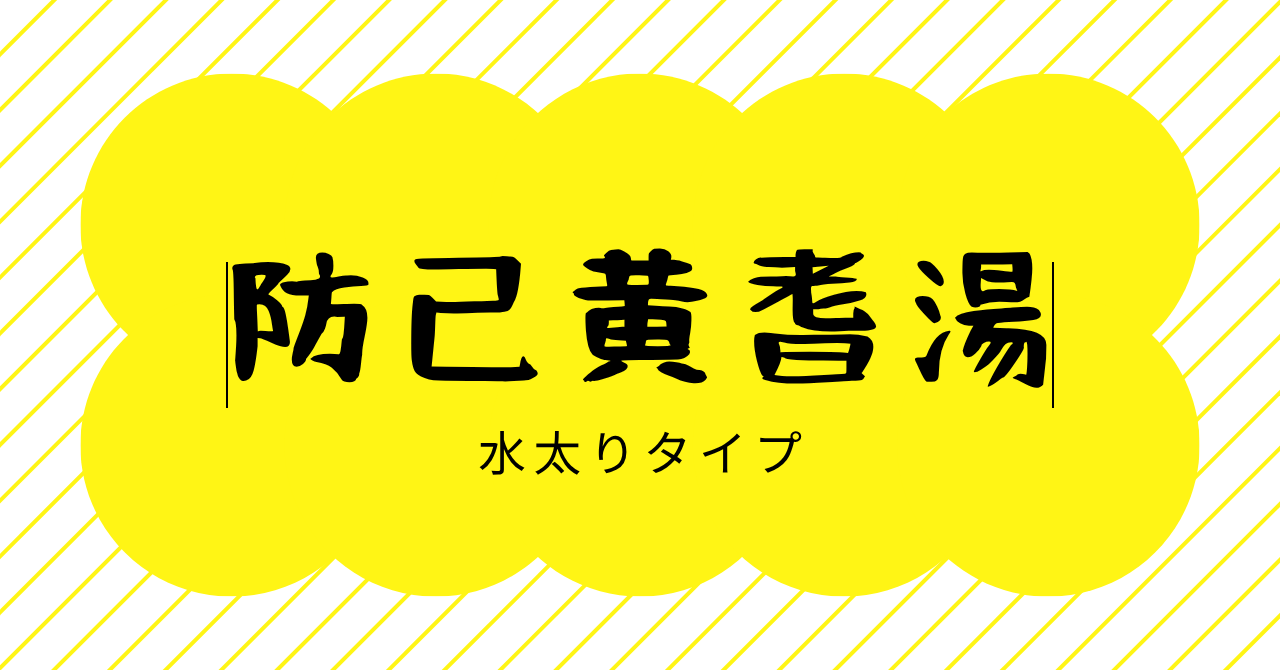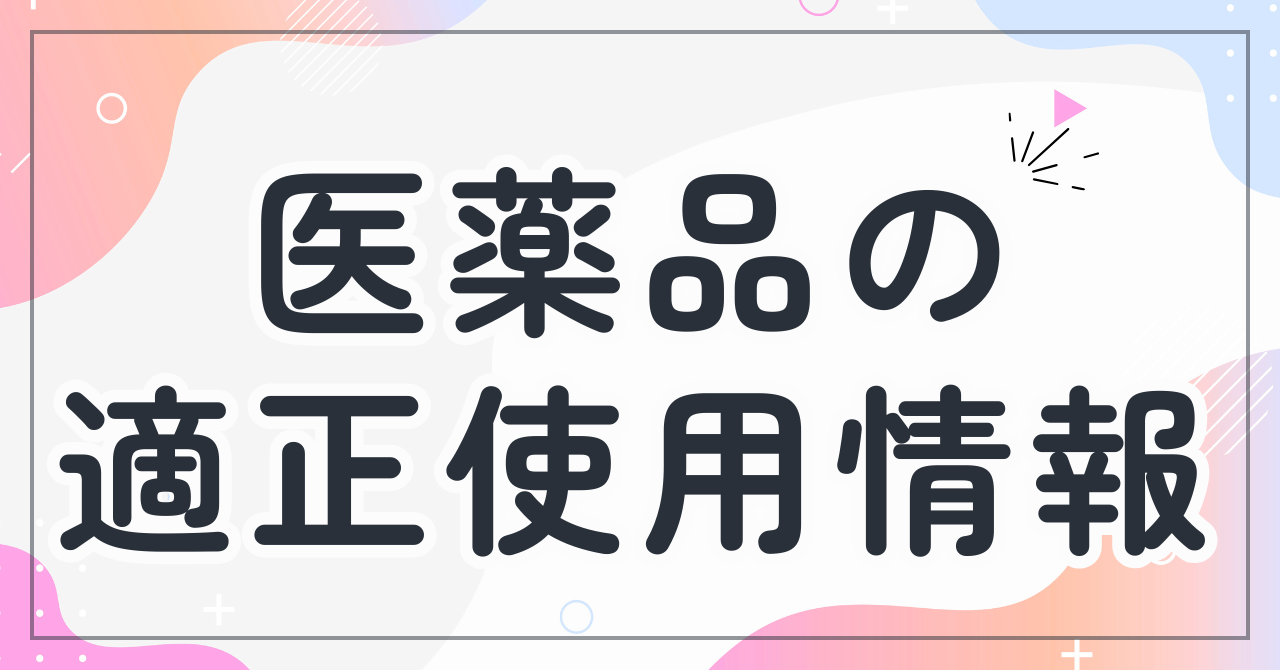登録販売者試験#54 抑肝散

◆ 抑肝散(よくかんさん)―気持ちの高ぶりを鎮める処方
● 概要
抑肝散は、イライラ・怒りっぽさ・神経の高ぶり・眠れないなど、感情のコントロールが難しいときに用いられる処方です。
古くは小児の「夜泣き・ひきつけ」に使われ、現在では認知症の興奮・不眠・神経過敏にも幅広く応用されています。
肝の失調:感情のコントロール不調、怒りの感情のコントロール不調
「肝の高ぶり(肝風)」を鎮めることで、精神的な安定を取り戻す――
まさに“心をしずめる漢方”といえます。

● 構成生薬と作用
| 生薬 | 主な働き | 作用の要点 |
|---|---|---|
| 柴胡 | 気の流れを整える | イライラ・緊張を緩和 |
| 釣藤鈎(ちょうとうこう) | 神経の興奮を鎮める | 頭痛・めまいを改善 |
| 当帰 | 血の巡りを整え心を落ち着かせる | 不眠や情緒不安定に有効 |
| 白朮 | 胃腸を補い全体のバランスを支える | 虚弱体質に対応 |
| 茯苓 | 心身の不安を鎮める | 不安・動悸に |
| 川芎 | 血流を促進しのぼせを緩和 | ストレス性の頭痛にも |
| 甘草 | 全体を調和させる | 過敏な反応を和らげる |
→ 肝の高ぶりを鎮めながら、脾(胃腸)を整える。心と体を同時に落ち着かせる構成。
【パナソニック公式】最高峰モデル炊飯器と銘柄米の定期購入サービス
● 主な適応
※添付文書上の効能効果
体力中等度をめやすとして、神経がたかぶり、怒りやすい、イライラなどがあるものの次の諸症:神経症、不眠症、小児夜泣き、小児疳症(神経過敏)、歯ぎしり、更年期障害、血の道症。血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである。
・認知症の興奮・不眠・イライラ
・神経症・不安障害
・小児の夜泣き・ひきつけ
・更年期の精神不安
→ ストレスで怒りやすい・眠れない・歯ぎしり・筋肉がこわばるタイプに適応。
→虚弱な体質で神経が高ぶるために起こる諸症状
母子共に夜泣きや引きつけで親もストレスで不眠などに陥っている事が多く、特に母親の感情を、子供も察知しているという事から母子同服と言い同じ薬を飲む、または母乳を通じて子供にも作用させるために、母親が薬をのむという考え方があります。
市販薬の場合2歳からの適応しかありませんが、古くからはそんな使い方もあると知っておいて下さい。
● 現代的な活用ポイント
売り場での対応
睡眠改善したい→不眠状態が長く、歯ぎしり、食いしばりがある。
女性婦人薬売り場→更年期や生理前後のイライラや不眠
抑肝散は交感神経の過剰興奮を鎮める作用があり、イライラだけでなく自律神経バランスの改善にも役立ちます。
精神科領域では、認知症のBPSD(行動・心理症状)の軽減にも使用される代表処方です。
医師バイトの今しか見れない最新トレンドをチェック
● 注意点
・虚弱で冷えが強い人には不向き。
・胃腸が弱く、過敏性腸症候群傾向がある場合は注意。
・妊婦・授乳婦・小児への使用は医師の指導下で行う。
[副作用]間質性肺炎、偽アルドステロン症、ミオパチー、横紋筋融解症、肝機能障害、黄疸(AST(GOT)、ALT(GPT)、AI-P、y-GTP等の著しい上昇)、過敏症(発疹、発赤、そう痒等)、消化器(食欲不振、胃部不快感、悪心、下痢等)、精神神経系(傾眠)、肝機能異常、その他(低カリウム血症、浮腫、血圧上昇、倦怠感)
抑肝散を必要とするタイプの人は、「肝気鬱結(かんきうっけつ)」「肝陽上亢(かんようじょうこう)」「気血不調」の傾向があります。
つまり、イライラ・怒りっぽい・不眠・頭のふらつき・肩こり・手の震えなどを感じやすい人です。
食事では「肝をやわらげて気の巡りを良くする」「血を補って肝を養う」「肝の高ぶりを鎮める」ことがポイントです。
| ① 気の流れを整える食べ物 | 柑橘類(みかん・グレープフルーツ・ゆず) 香りのある野菜(セロリ・しそ・ミント・フェンネル) 花茶(菊花茶・ローズティー・ジャスミン茶・陳皮茶) |
| ② 血を養い肝をやわらげる食べ物 | 黒ごま・クコの実・なつめ・龍眼肉・桑の実 卵黄・豚レバー・ほうれん草・にんじん |
| ③ 肝の高ぶりを鎮める食べ物 | セロリ・ゴーヤ・緑豆・昆布・海苔・ハスの実・百合根 |
| ④ 控えたほうがいいもの | ④ 控えたほうがいいもの 辛いもの・アルコール・コーヒー 脂っこいものや甘いものの摂りすぎ |