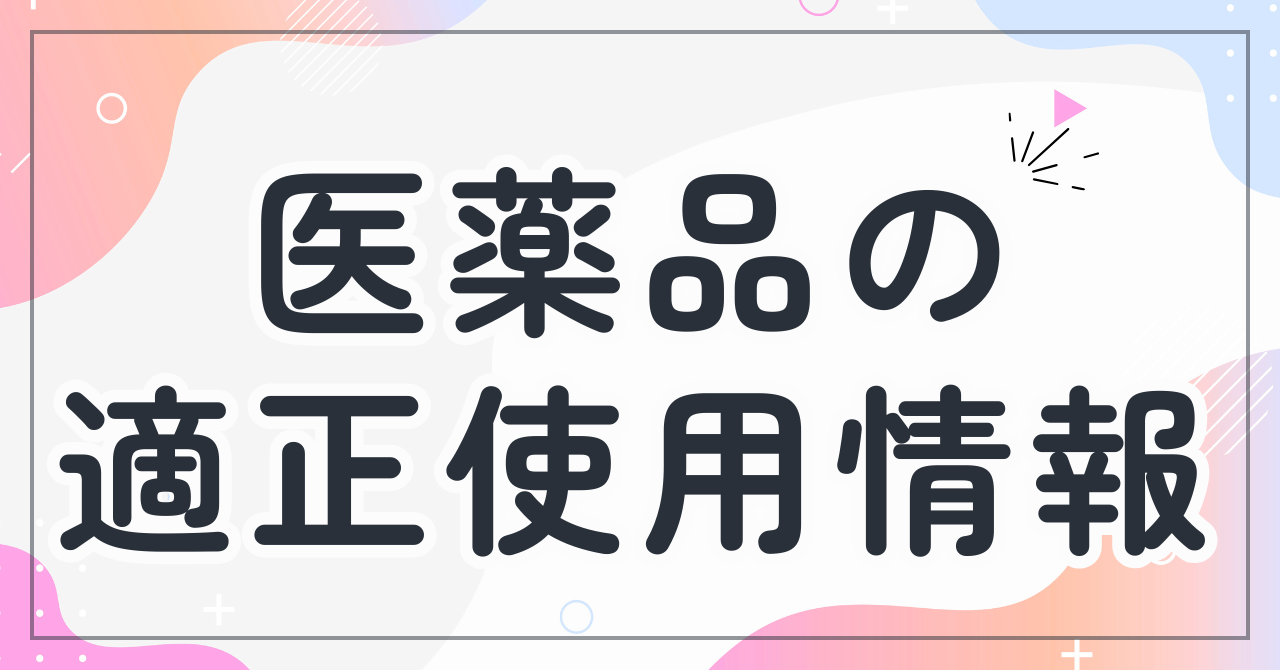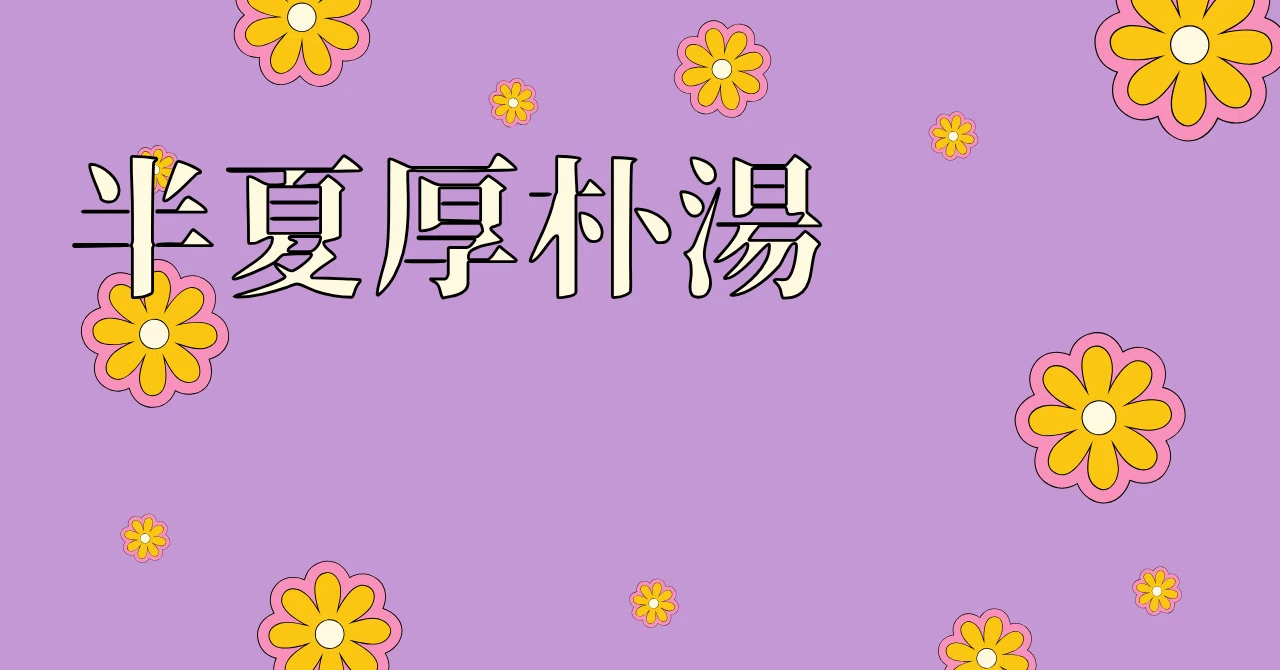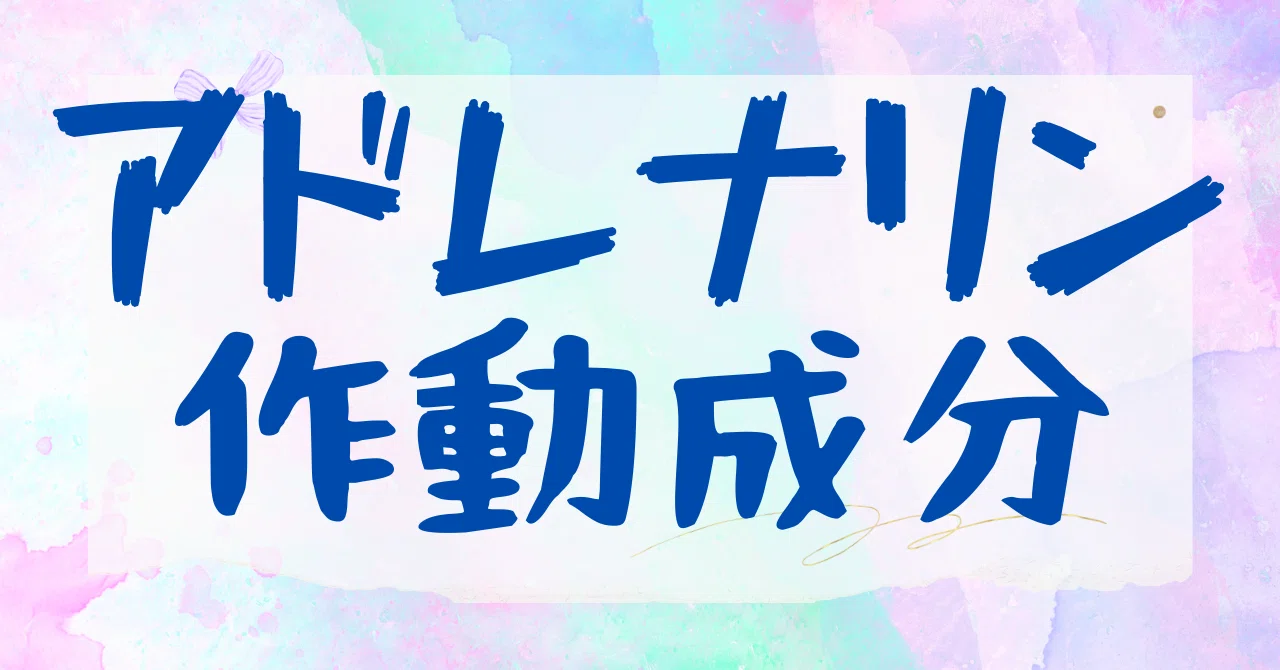登録販売者#10体の仕組み⑤感覚器官:目・鼻・耳

羅列になってしまうので1項目ごとに音声を分けます。⸻
❶ 目の構造と働き
■眼球の構造と各部の役割
白目の部分。眼球の外側を包む丈夫な膜で、結膜によって覆われている。
結膜は眼瞼の裏と眼球前面の強膜をつなぎ、組織を保護する透明膜。
黒目の部分の透明な膜。紫外線などで障害を受けると炎症を起こすことがある(雪目、角膜炎)。
角膜と水晶体の間を満たす液体で、眼内の圧力(眼圧)を保っている。血液にかわり目の栄養、酸素を届けている。
厚みを変えることで、近くや遠くの物にピントを合わせる。
厚みを変えることで、近くや遠くの物にピントを合わせる。
水晶体の厚みを調節する。
光を受け取る視細胞があり、受けた情報を神経を通じて脳に伝える。
網膜で受け取った情報を脳へ送る神経。視細胞が、密集している部分を特に黄斑部といい、最も感度の高い中心窩が存在する。ビタミンAが不足すると視力低下が起こる。(夜盲症)
涙腺から涙が分泌され鼻腔に流す(涙道)睡眠中は殆どでず、眼球運動が鈍くなったり、老廃物や脂が混じって目やに(眼脂)になる。
■その他の構造
結膜:白目とまぶたの裏側を覆う薄い膜で、透明なため血管が透けて見える。
涙腺・涙道:涙を分泌し、鼻へ流す通路。涙は異物の洗浄、角膜の保護、栄養補給、殺菌作用などの役割を持つ。
■目の調整機能
水晶体の厚さを変えることで、近くを見るときは厚く、遠くを見るときは薄くなる(調節)。
毛様体のはたらきによってこの調節が行われる。
⸻
❷ 鼻の構造と働き
• 鼻中隔の前部(キーゼルバッハ部位)は毛細血管が密集し、鼻血が出やすい。
• 鼻腔は左右に分かれており、粘膜が薄いため、刺激に敏感。粘膜の「血流が豊富」で「線毛上皮に富む」ため、傷つきやすく、ウイルスや細菌の侵入を受けやすい
• 嗅上皮の細胞は「順応」しやすく、においをかぎ続けていると感じにくくなる。
• 粘膜が薄いため、傷つきやすく、感染を起こしやすい。
• 嗅上皮には嗅細胞が存在し、においの刺激を感じ取る。
• 副鼻腔は、鼻腔とつながる空洞で、頭の重さを軽くしたり、声の共鳴を助ける。
• 副鼻腔は粘液を分泌する細胞に覆われており、炎症(副鼻腔炎)を起こすと膿がたまりやすい。
① 嗅覚(においを感じる仕組み)
• 嗅覚の役割:鼻は嗅覚情報の受容器官として、食品や煙などのにおいを感知し、危険の察知にも関わっている。
• 嗅覚情報の伝達:鼻腔の上部には嗅上皮という感覚細胞の集まりがあり、におい物質を感知すると電気信号として嗅神経を通じて脳に伝えられる。
鼻炎
• 鼻腔粘膜に炎症が起こり、腫れた状態を「鼻炎」という。これにより、においを感じにくくなる。
⸻
② 副鼻腔(ふくびくう)
• 副鼻腔とは:鼻の周囲の骨の中にある空洞で、頭の重さを軽くし、声の共鳴にも関係する。
• 粘膜の構造:鼻腔と同様、線毛を持つ粘液を分泌する上皮細胞で覆われており、異物や細菌の排除に働く。
• 線毛運動:分泌された粘液や異物を喉の方へと運ぶ。
• トラブル:鼻粘膜が腫れると、副鼻腔との通路がふさがりやすくなり、副鼻腔炎(蓄膿症)の原因になることもある。
⸻
❸ 耳の構造と働き
耳は外耳・中耳・内耳に分けられ、それぞれ異なる役割を持つ。
■外耳
• 構造:耳介〜外耳道〜鼓膜まで。
• 役割:音を集めて鼓膜に伝える。皮膚腺から耳あか(耳垢)が分泌される。
• 鼓膜は音の振動を中耳へ伝える。
■中耳
• 構造:鼓膜の奥にあり、耳小骨(ツチ骨・キヌタ骨・アブミ骨)で音の振動を内耳へ伝える。
• 役割:鼓膜の振動を耳小骨を通して内耳へ伝える。
• 耳管:咽頭とつながる細い管。圧の調整を行っている。風邪などで腫れると中耳炎の原因になる。(子供は耳管が太くて水平に近く感染が起こりやすい)
■内耳
• 構造:蝸牛(かぎゅう)と前庭・三半規管からなる。
• 蝸牛:音を電気信号に変える「聴覚器官」
• 前庭・三半規管:体の回転・重力・加速度を感知する「平衡感覚器官」
• 機能:感覚細胞が刺激を受けて、聴神経や前庭神経を通して脳へ伝えられる。
⸻
補足ポイント(まとめ)
• 鼻は嗅覚の感知器官であり、異物を防御する構造を備えている。
• 副鼻腔は「直接空気の通り道ではないが、声の共鳴や頭部の軽量化に寄与する
音の響きや軽量化にも貢献。
• 耳は聴覚と平衡感覚の両方を担う重要な器官で、3部構成に分かれる。
トラネキサム酸
(止血薬、のどの炎症止め、美白薬など)
血栓のある方にはNG!自己判断での長期使用は危険です。
トラネキサム酸は、出血を止める作用や、炎症を抑える効果があり、風邪薬や口内炎治療薬、美白目的の内服薬にも使われています。しかし、この成分は血栓(血の塊)を溶けにくくする作用があるため、脳梗塞や心筋梗塞、静脈血栓症などの既往がある方では使用を避けるべき成分です。
特に血栓リスクの高い人が、気づかずに美容目的などで長期使用してしまうと、思わぬ副作用を引き起こす可能性があります。
また、市販薬の中にも含まれているため、「効きそうだから」といって安易に併用したり、複数の薬を重ねて服用するのは危険です。服用の目的や自分の体質・病歴に合っているかを確認し、必要があれば医師や薬剤師に相談しましょう。