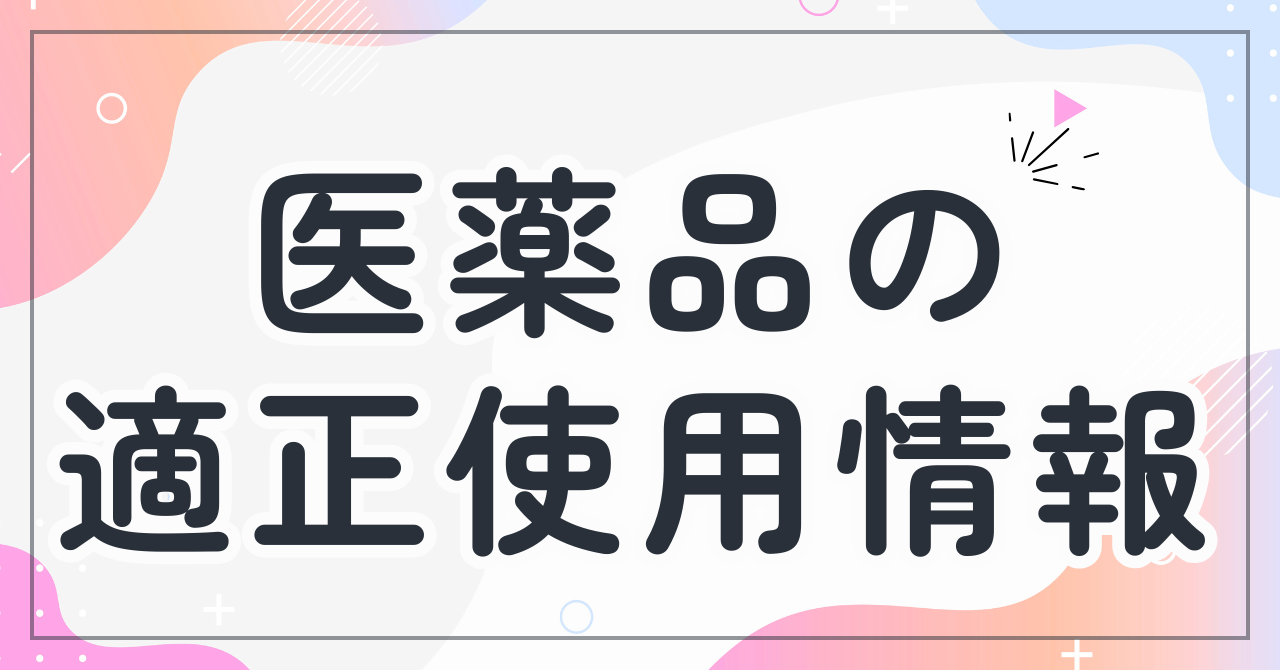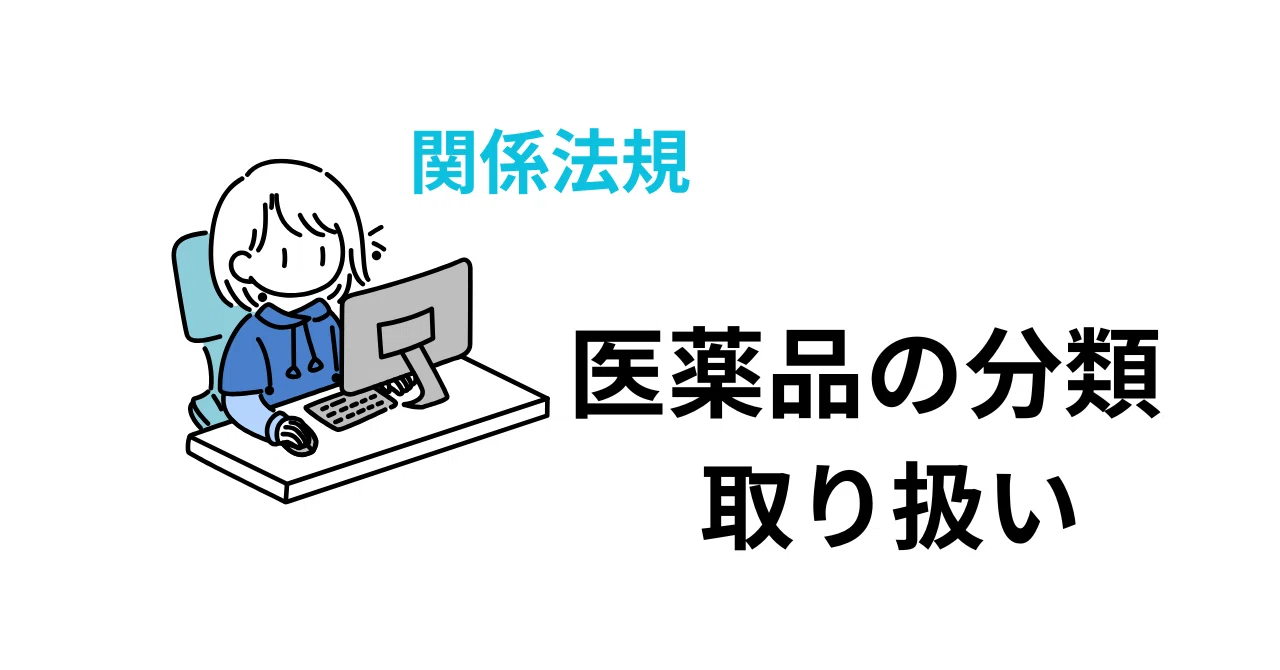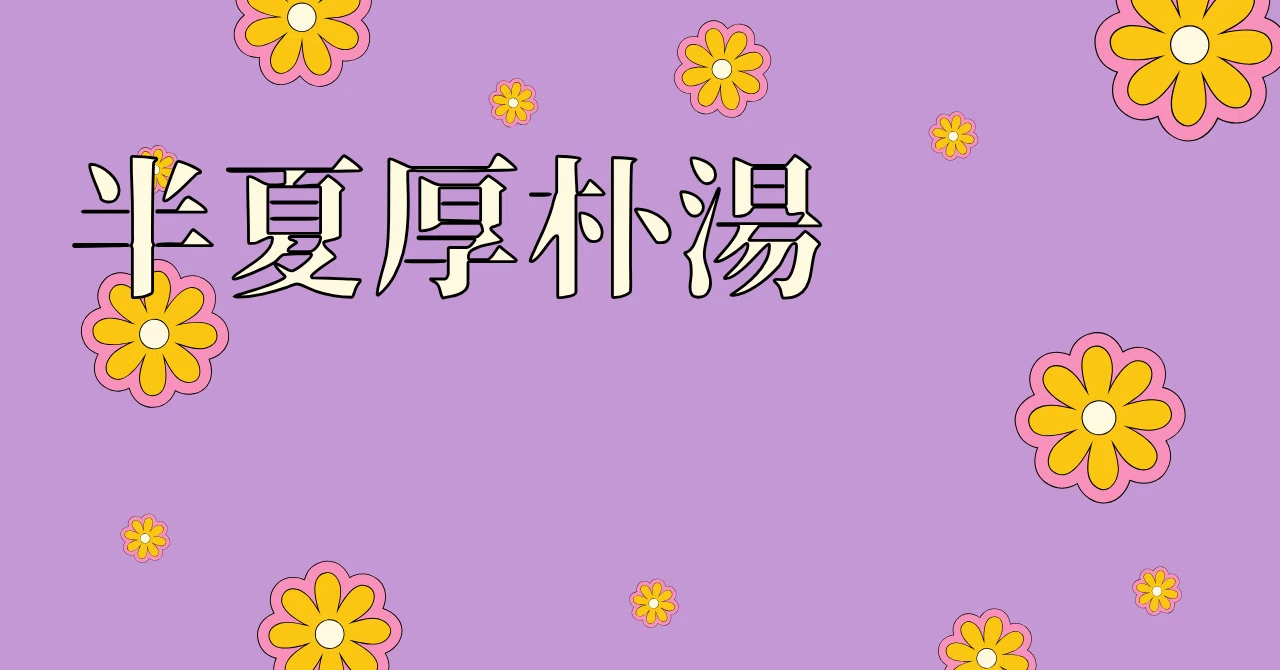登録販売者試験 関係法規#3店舗販売業とは?
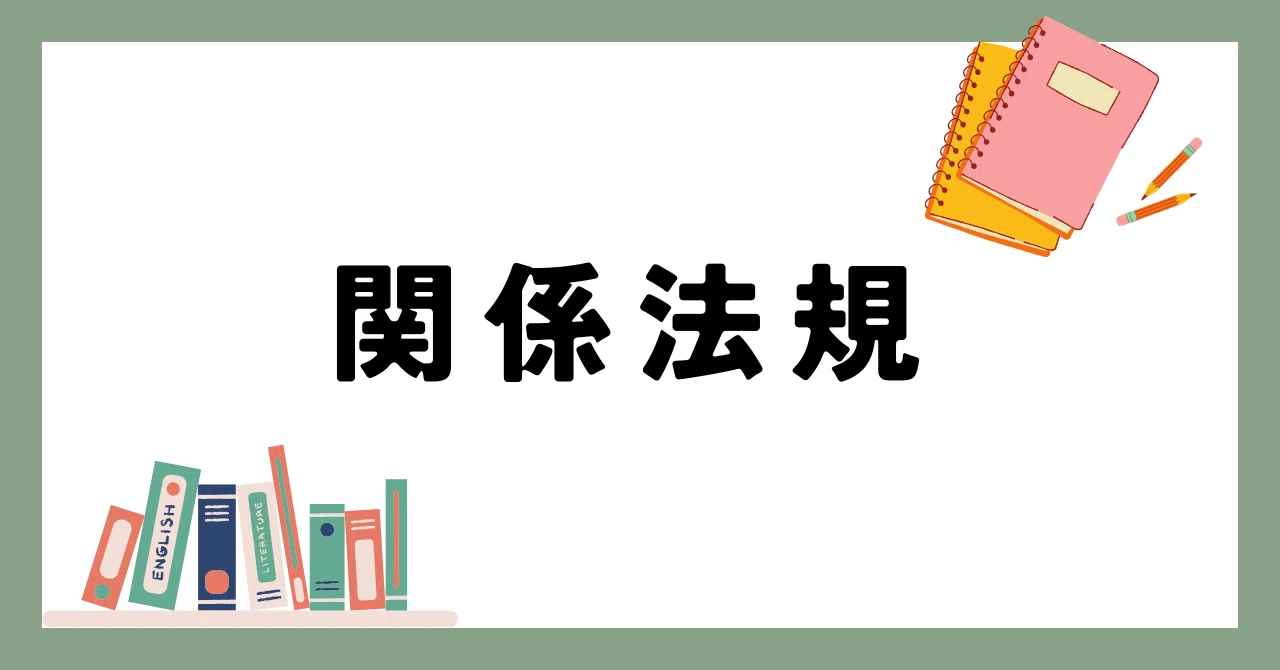
販売できる医薬品と管理体制を理解しよう
1.店舗販売業で扱える医薬品の種類
販売できないもの
• 要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売は店舗販売業では販売できません。
販売できるもの
• 一般用医薬品(OTC薬)又は要指導医薬品
• 第1類医薬品:薬剤師が販売し、情報提供も必須
• 第2類・第3類医薬品:登録販売者が販売・情報提供可能
登録販売者がいても、第1類医薬品は販売できない点に注意!
要指導医薬品、第一類医薬品は薬剤師に販売させなければならず、この薬剤師がいたとしても、店舗販売業では調剤は出来ない。
⸻
2.開設と許可について
• 店舗ごとに都道府県知事の許可が必要。
• 特別区(例:東京23区)では、市長または区長の許可。
• 開設には「店舗設備が法令に適合していること」などの条件が必要。
• 許可には有効期限があり、違反があれば更新されません。
⸻
3.店舗管理者の指定と条件
▷ 誰が管理者になれる?
• 原則:薬剤師または登録販売者
• 実際に店舗で働いていること(実地管理)が必須
▷ 管理者の要件
• 必要な能力と経験を持つこと(例:実務経験2年以上)
• 店舗管理者は、その店舗以外で他の業務に従事できない(※都道府県知事の許可がない限り)
販売できる医薬品
:一般用医薬品(第1~第3類)。ただし、第1類は薬剤師のみ対応可。
許可:
店舗ごとに必要。都道府県知事の許可制。
管理者:
薬剤師または登録販売者が実地で管理。必要な能力と経験が必須。
店舗販売業と配置販売業の管理者制度をマスターしよう
店舗販売業の管理体制
店舗区分、店舗管理者
要指導医薬品・第1類医薬品を扱う;薬剤師のみ
第2類・第3類医薬品のみを扱う;薬剤師 or 登録販売者
● 第1類医薬品を扱う店舗
• 管理者は薬剤師が原則
• やむを得ず薬剤師を置けない場合、以下の要件を満たす登録販売者が代わりに管理可能:
• 第1類又は要指導医薬品を扱う薬局等で販売経験あり
薬剤師が区域管理者である、第一類医薬品を販売する配置販売業で、登録販売者として直近5年間のうち通算3年以上従事した経験がある
もし、第一類医薬品を販売する店舗で、登録販売者を店舗管理者とする場合、補佐として薬剤師を置かなければならない。
● 第2類・第3類のみ扱う店舗
• 登録販売者でも管理者になれる
• 過去5年のうち、2年以上の勤務経験が必要。ただし直近5年間に限定せず従事期間が通算して2年以上かつ過去に店舗管理者や区域管理者として従事した経験があるものもなれる。
5.管理者の業務内容
• 保健衛生の支障を防ぐため、業務全体を把握し監督
• 勤務者への指導内容を記録・保存(薬剤師・登録販売者共通)
• 違反があると営業停止等の行政処分の対象となる
⸻
配置販売業の管理体制
1.定義と特徴
• 購入者の自宅などに医薬品をあらかじめ預けておき、必要になったときに販売する仕組み(先用後利)
• 通常、家庭用品とセットで販売されることが多い(人の家のスペースを借りて陳列している事になる)
• 店舗型ではないことが最大の特徴
⸻
2.販売できる医薬品
• 基本は一般用医薬品
• 第1類医薬品は薬剤師のみ
• 登録販売者が販売できるのは、第2類・第3類に限られる
⸻
3.許可と要件
• 配置しようとする区域ごとに都道府県知事の許可が必要
• 申請時には薬事法令を遵守し、一定の基準に合致していなければ許可されない
⸻
4.区域管理者とは?
販売する医薬品の種類
区域管理者
第1類医薬品を扱う:薬剤師のみ
第2類・第3類医薬品を扱う
:薬剤師または登録販売者
要件
• 登録販売者で、直近5年のうち、2年以上の従事経験が必要
• 店舗販売業・配置販売業・薬局等での勤務歴があればOK
⸻
5.区域管理者の業務
• 配置員への指導・監督
• 必要な措置の記録と保存
• 業務が法令に適合するよう指導の記録を保管
⸻
〇配置員に関する届け出
• 配置販売業者または配置員は、勤務「前」に次を都道府県知事に届け出る必要あり:
1. 配置販売業者、従事者の氏名と住所
2. 配置しようとする区域
3. 従事予定の期間
⸻
〇 その他重要ポイント
• 分割販売は禁止(医薬品を小分けして販売することは不可)
• 「住所」は、配置員・業者どちらが販売するかによって記載方法が異なる
• 違反があれば罰則・営業停止などの行政処分
⸻
試験対策ポイントまとめ
管理者の種類
店舗販売業:店舗管理者、配置販売業:区域管理者
管理者の要件
過去5年で2年以上の勤務経験(販売業 or 薬局など)
管理者の業務
指導内容の記録・保存、違反時の報告など
販売できる薬
第1類は薬剤師のみ。登録販売者は第2・3類まで
分割販売
どの販売形態でも原則禁止
一般用医薬品の中で薬剤師の存在が必要なのは10%ほど、残りの90%は登録販売者が販売できるので、2.3類のみか~と思わずに結構多くの種類に携わることが出来ます。
発熱を伴う場合における受診勧奨
(一般用医薬品による対応の限界)
自己判断せず、発熱時には医療機関での診察を。
市販薬はあくまで「一時的な症状の緩和」が目的です。特に発熱を伴うような状態では、感染症や炎症性疾患などの重大な病気が隠れていることもあるため、自己判断で市販薬だけで済ませようとせず、早めに医療機関での診察を受けることが推奨されます。
高齢者や基礎疾患のある方、熱が数日続く場合、悪寒や強い倦怠感を伴う場合などは、早急に受診するべきです。市販薬で熱を下げることはできますが、病気の本質を見逃さないためには、医師の判断が欠かせません。また、高齢者や虚弱(何らかの免疫疾患)では高熱を出す力が無く、微熱が続くという場面もあります、高熱ではないからと安易な判断は避けるようにしましょう。