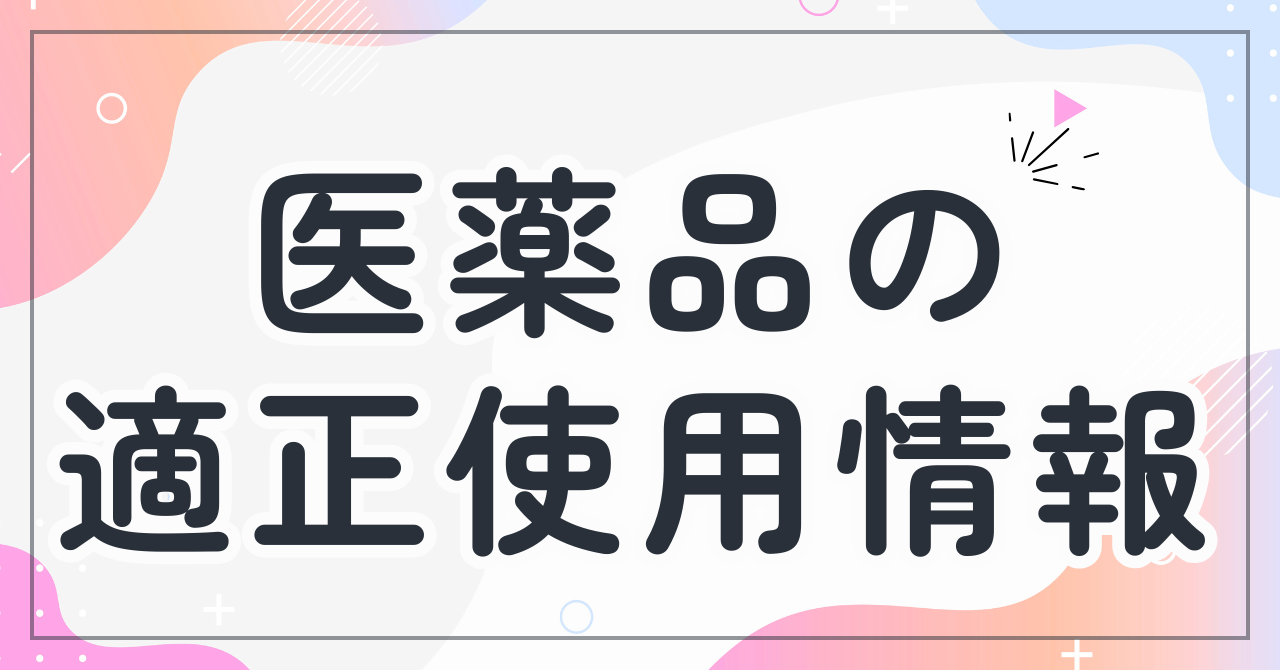登録販売者試験 #51 低気圧頭痛(気象病)

気圧が下がる、あるいは天候が崩れる前後に頭痛やめまい、吐き気を訴える人がいます。
このような「気象の変化によって起こる頭痛」を低気圧頭痛(気象病)といいます。
発症の仕組み:
• 気圧が下がる → 体内の水分バランスが崩れ、むくみや血管拡張が起こる
• 自律神経が乱れ、交感神経と副交感神経の切り替えが不安定になる
• 結果として、脳の血管が拡張し、周囲の神経が刺激され頭痛を感じます
頭痛のタイプとメカニズム
| タイプ | 主な特徴 | メカニズム |
| 片頭痛(へんずつう) | ズキズキと脈打つような痛み。光・音・においに敏感。季節の変わり目や気圧変化により誘発されやすい。 | 水分バランスの偏りにより脳の血管が拡張 → 周囲の神経が刺激される |
| 緊張型頭痛(きんちょうがたずつう) | 頭を締めつけられるような痛み。こめかみや後頭部の痛みや肩こりやストレスが関係。 | 筋肉の緊張 → 血流悪化 → 酸素不足で痛み物質が出る。ふわふわしためまいになる事もある。 |
低気圧頭痛に用いられる代表的な漢方薬
分類:利水剤(体内の水の流れを整える)
効能効果:体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、
めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれを伴う次の諸症:頭痛、むくみ、二日酔など
(参考)体内の水分バランスの乱れによるめまい・頭重感・吐き気・むくみ、二日酔いに伴う前述の症状。
とくに「水滞(すいたい)体質」の人(雨の日や湿度が高いと体調が悪くなる人)に適します。
① 五苓散(ごれいさん)〈ツムラ17〉
構成生薬(五味):
• 猪苓(ちょれい)
• 茯苓(ぶくりょう)
• 蒼朮(そうじゅつ)
• 桂皮(けいひ)
• 澤瀉(たくしゃ)
ポイント:
体内の余分な水分を集めて出す働きの生薬が配合されており利水剤として使われます、「頭が重い」「むくみやすい」「天気が悪いと体調が崩れる」といった症状に用いられます。
[売り場で見かけるこんな人に]
痛み止め(頭痛)→天候が悪いと起こる頭痛、二日酔いの頭痛
下痢止め→水っぽい下痢、二日酔いの吐き気と下痢
女性薬→顔や足のむくみ(危険性の低い慢性的なもの)
この流れで少し詳しく書きますと…
日ごろの生活習慣を少し見直すことで、体調の改善につながります。
漢方薬の服用と合わせて、こんな「養生の工夫」もおすすめです。
⸻
その一。。気圧の変化を知って、自分の体調と向き合いましょう。
天気や気圧の変化によって、頭痛や肩こり、倦怠感などの不調があらわれることがあります。
これは、気圧の変動が体の自律神経に影響を与えるためです。
日ごろから天気の変化を意識して、自分の体調のリズムを知るようにしましょう。
たとえば、気象変化による頭痛の記録をつけておくと、早めの対策にもつながります。
自分の体調変化に気づくこと、それがいちばんの予防です。
⸻
その二。。「ほどほど」を意識して、むくみ知らずをめざしましょう。
一日が終わるころ、足がパンパンに張っていたり、重だるいと感じることはありませんか。
それは、体の中の水分バランスがくずれ、血流が滞っているサインかもしれません。
塩分の多い食事やアルコールの摂りすぎも、体のむくみに影響します。
食べすぎや飲みすぎを控え、体をいたわるようにしましょう。
デスクワークが続いた日は、軽くストレッチをしたり、湯船につかって血流を整えるのもおすすめです。
「ほどほど」を心がけて、体の中に水をためこまないようにすることが大切です。
⸻
その三。。旬の食材を選んで、体のバランスを整えましょう。
体調を整えるには、食事も大切です。
特に旬の食材は、栄養価が高く、体のバランスを助けてくれます。
むくみをとり、余分な水分を出し、胃腸を整える効果が期待できる食材を取り入れましょう。
おすすめの食材
はと麦、アスパラ、レタス、カリン、ハマグリ、黒豆、エンドウ豆、トウモロコシ、レモン、昆布、小豆、キュウリ、ナス、ブドウ、ひじき など。
ひとことアドバイス
気圧の変化を感じたら、無理をせず、少し早めに体を休めましょう。
むくみやすい日には、水分をこまめにとり、冷えすぎに注意することも大切です。
浮腫があるからと、水分制限をしても、体の中の澱みは流れません、適度な水分とストレッチや食事、漢方を上手く使って流してあげることが改善のキモです。
日々のちょっとした工夫が、頭痛やむくみの予防につながります。
② 釣藤散(ちょうとうさん)〈ツムラ47〉
分類:鎮静・鎮痙剤(自律神経や血流を整える)
効能効果:体力中等度で、慢性に経過する頭痛、めまい、肩こりなどがあるものの次の諸症:
慢性頭痛、神経症、高血圧の傾向のあるもの
(参考)低気圧による自律神経の乱れで交感神経が優位になると、脳血管な一時的にに収縮しその後拡張し周りの組織を圧迫する事により、近辺の神経も圧迫され痛みになるを肩こりやストレスによる事もあります。
高血圧傾向のある人の慢性頭痛・肩こり・耳鳴り・めまいなど。
精神的緊張やストレスで頭痛が悪化しやすいタイプに。
釣藤鈎(ちょうとうこう)
構成生薬(11味):<ツムラ17>
・菊花
・半夏
・麦門冬
・人参
・茯苓
・石膏
・陳皮
・甘草
・防風
・生姜
ポイント:
• 「血管の拡張・収縮」に関係する自律神経の乱れを整える
• 頭痛・肩こり・耳鳴りなどを改善
• 「ストレス」「高血圧傾向」「年配者の慢性頭痛」に向く
ではどう生活に活かすか
その一。。ストレスをためず、気の流れを整えましょう。
釣藤散は、イライラや緊張、肩こりをともなう頭痛などに用いられます。
このような症状は、気のめぐりが滞っているサインです。
一日の中で、深呼吸をしたり、軽いストレッチをしたりして、気分をほぐしましょう。
パソコン作業が続いたら、空を見上げたり、肩を回したりして、意識的にリセットする時間を持つことが大切です。
気がめぐると、血のめぐりも自然に整い、体も心も軽くなります。
⸻
その二。。血圧と血流を意識した生活を心がけましょう。
釣藤散は、高血圧傾向のある人の慢性的な頭痛や肩こり、めまいに使われます。
急な立ちくらみや、首の後ろの重だるさを感じるときは、血の流れが乱れていることがあります。
塩分のとりすぎを控え、野菜や果物からカリウムをしっかりとるようにしましょう。
お風呂では熱すぎる湯ではなく、ぬるめのお湯にゆっくりとつかることで、
血管が穏やかに広がり、全身の緊張もやわらぎます。
眠る前に、軽く深呼吸をして心を落ち着けるのもおすすめです。
⸻
その三。。「眠り」と「朝のリズム」を大切にしましょう。
釣藤散が合うタイプの人は、神経が張りつめやすく、睡眠の質が下がることがあります。
夜遅くまでスマートフォンを見たり、カフェインを多くとったりすると、眠りが浅くなります。
寝る一時間前には照明を落とし、ぬるめのお茶を飲んで気持ちをゆるめましょう。
朝は、カーテンを開けて光を浴び、体内時計を整えることが大切です。
眠りと覚醒のリズムを整えることで、自律神経のバランスも安定しやすくなります。
⸻
🍵 体のめぐりを整える食材紹介
体の緊張をゆるめ、気と血の流れをよくする食材を取り入れてみましょう。
おすすめの食材
理気(りき)=気の流れをよくする食材
セロリ、みょうが、ピーマン、 シソ
清熱(せいねつ)=のぼせや頭痛、ほてりを鎮める食材
ホウレンソウ、 キュウリ、トマト、ナス、ブロッコリー
補血(ほけつ)・活血(かっけつ)=血流を整える食材
黒ごま、青魚、きのこ類
お手軽な食品の例
飲みものは、ジャスミン茶やハーブティー、麦茶など。
主食には、雑穀ごはんや梅入りおにぎり。
副菜には、青魚の焼きもの、または豆腐と野菜の煮びたし。
甘味には、黒ごまプリンや豆乳ゼリーなどが向いています。
⸻
ひとことアドバイス
肩こりや目の疲れを感じたら、深く息を吸ってゆっくり吐きましょう。
気持ちが落ち着くだけでなく、体のこわばりも和らぎます。
ストレスをためこまない工夫が、自律神経の安定と頭痛の予防につながります。
⸻
試験対策ポイントまとめ
• 五苓散 → 利水作用。体内の水の偏りを調える(めまい・頭重・むくみ)
• 釣藤散 → 血管・神経のバランスを整える(慢性頭痛・肩こり・高血圧傾向)
• 低気圧頭痛は自律神経と血管反応の乱れが関係
• 頭痛は「片頭痛型(血管拡張)」「緊張型(筋肉のこり)」に大別される
• 登録販売者は「症状タイプと体質」に合わせた漢方を選ぶ視点が重要
⸻
まとめ
天気の変化や気圧の低下によって起こる「低気圧頭痛」は、自律神経や体内の水分バランスの乱れが関係します。
体がむくみやすく頭が重いタイプには五苓散、ストレスや高血圧傾向で頭痛を感じるタイプには釣藤散がよく用いられます。
漢方では「その人の体質」に合わせて選ぶことがポイントです。