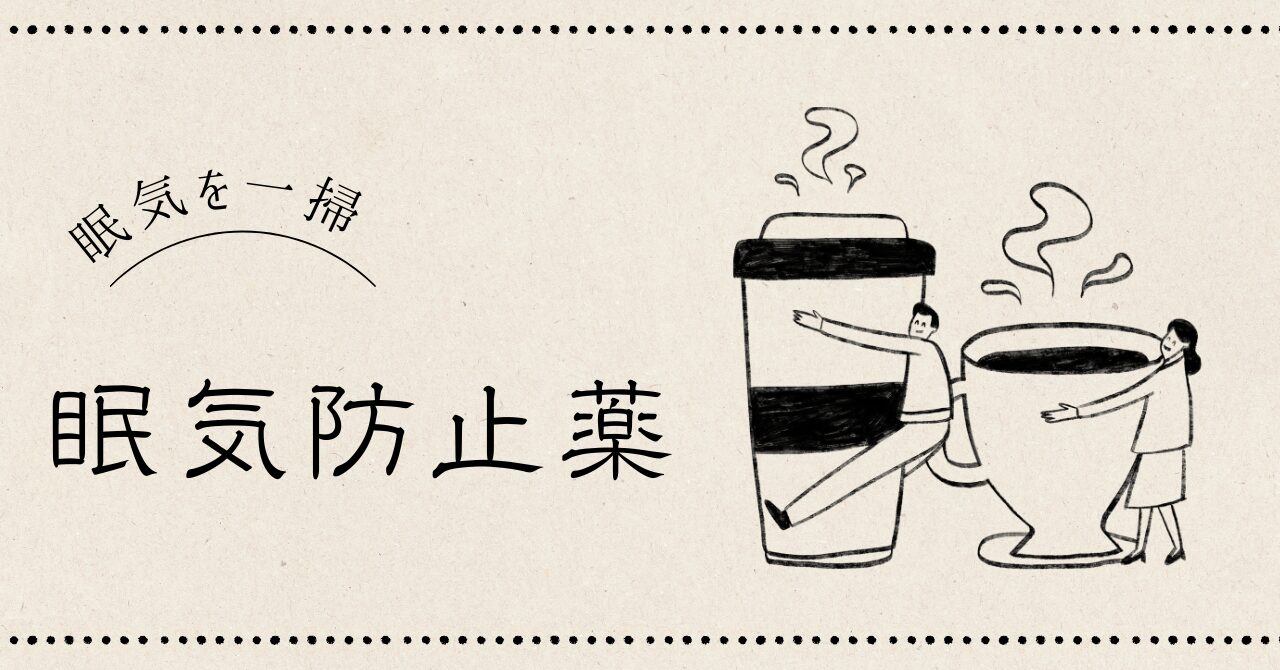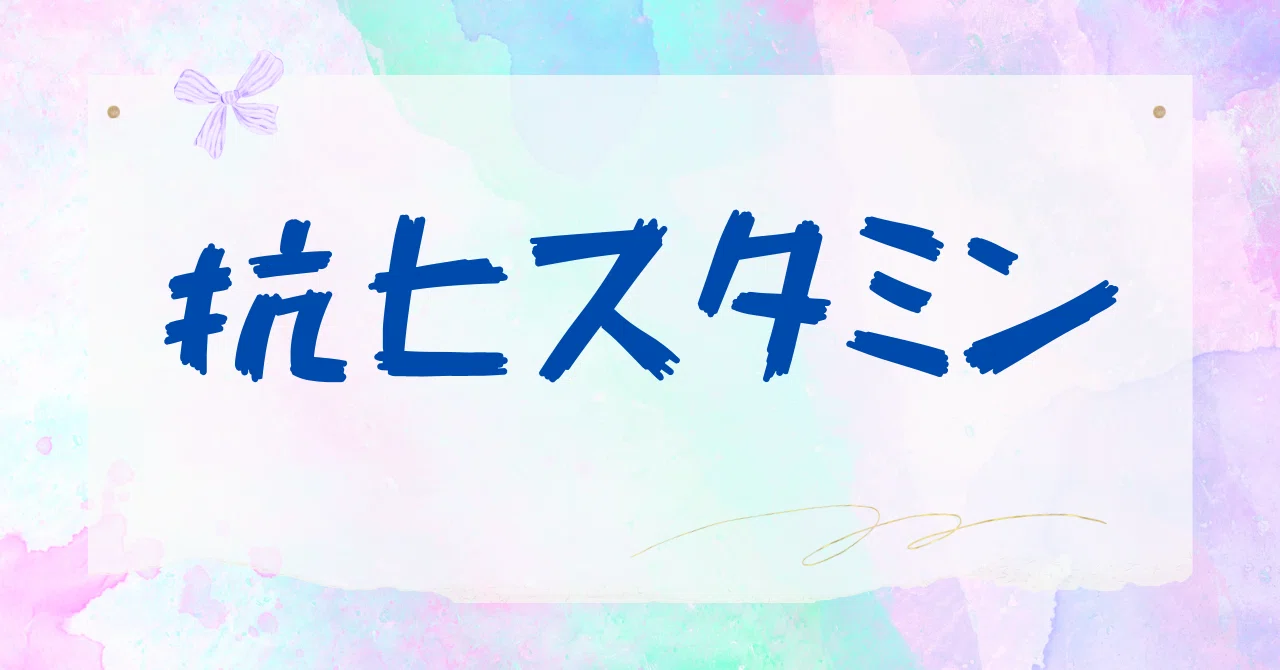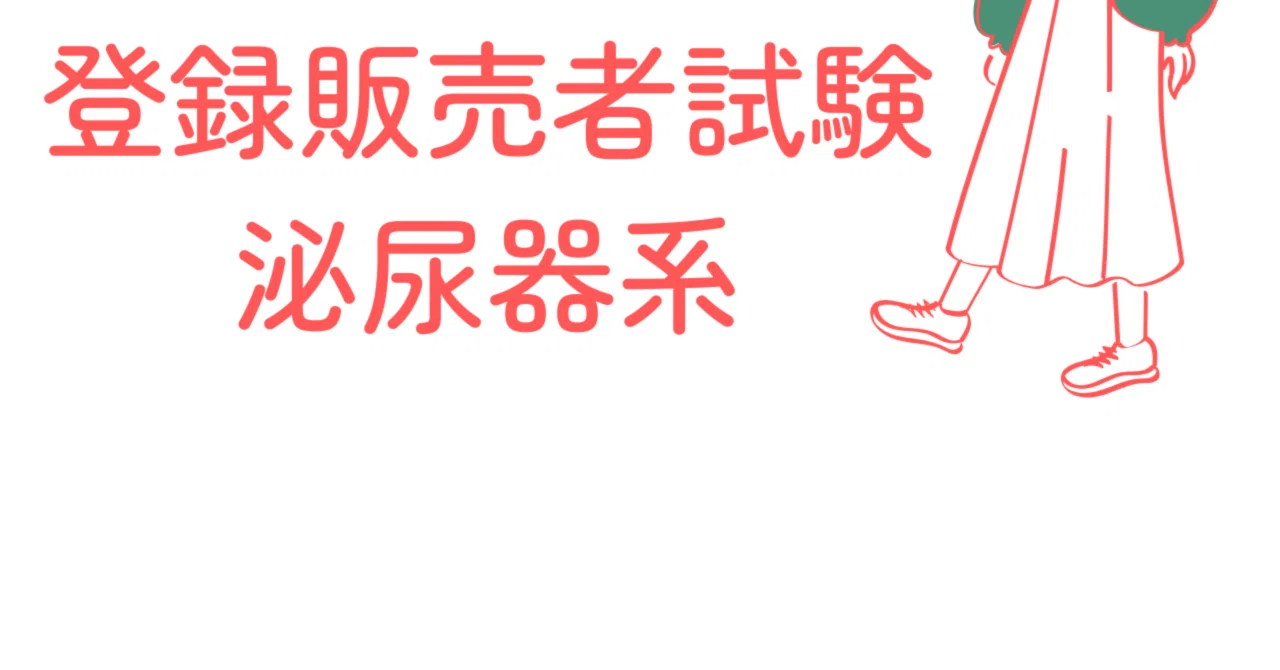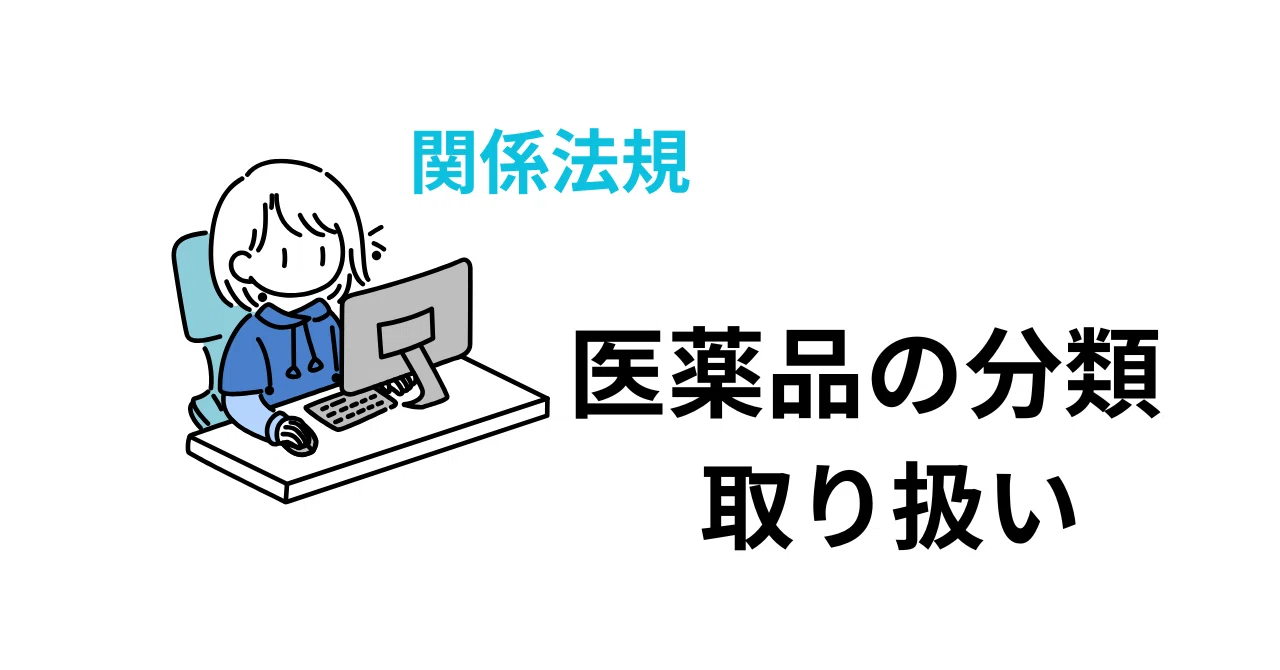登録販売者試験#24鎮咳去痰薬のしくみ
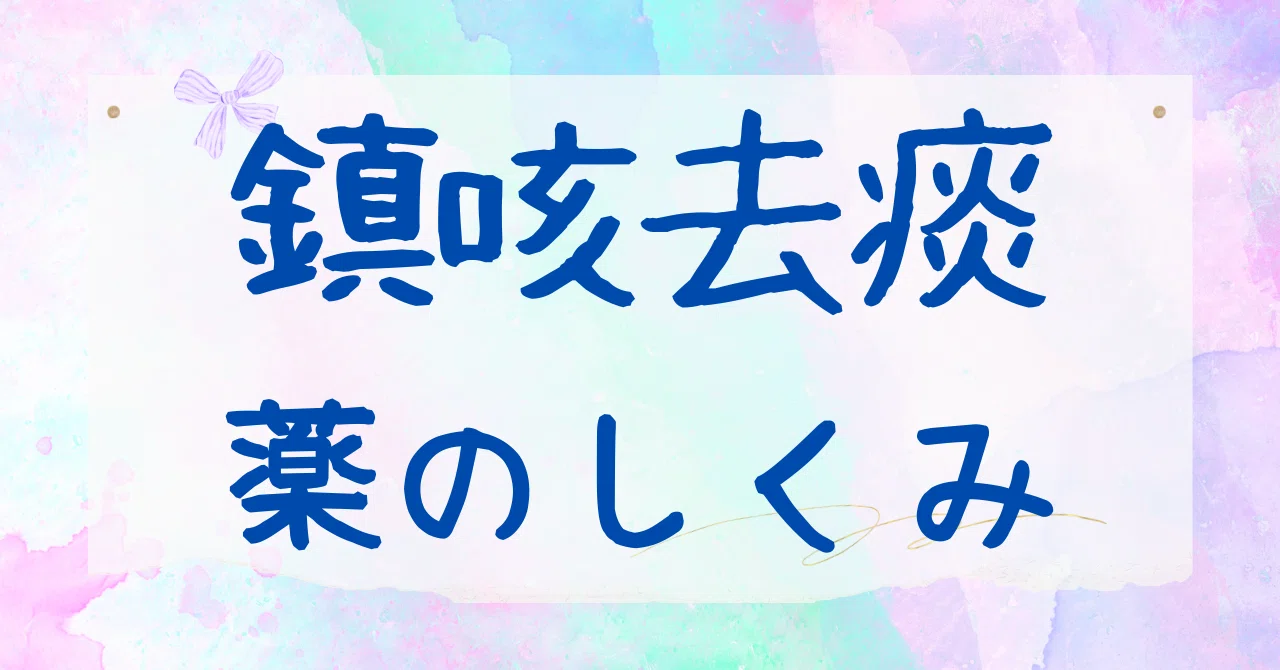
呼吸器に作用する薬とは?
呼吸器に異常が起きたときに使われる薬には、以下のような分類があります:
• 鎮咳去痰薬(ちんがいきょたんやく)
• 口腔咽喉薬(こうくういんこうやく)
• 吸入薬、含嗽薬(がんそうやく)など
今回はその中でも、もっともよく使われる「鎮咳去痰薬」を中心に書いていきます。
⸻
鎮咳去痰薬とは?
● 咳(せき)が出る仕組み
気管や気管支に異物(ウイルス・ほこり・痰など)が入ると、体はこれを排除しようと咳反射を起こします。これは防御反応で、無理に咳を止めてはいけない場合もあります。
⸻
痰(たん)が出る仕組み
風邪や喫煙などで気道に炎症が起きると、気道粘膜から粘液分泌が増え、それが痰になります。この痰が粘っこいと気道に残りやすく、それを排出しようと咳が出ます。
⸻
喘息(ぜんそく)とは?
気道粘膜の炎症がひどくなると、気道が収縮して「ぜーぜー」「ヒューヒュー」といった喘鳴(ぜんめい)をともなう喘息を引き起こします。
⸻
鎮咳去痰薬は何をする薬?
以下のような作用を持つ成分が組み合わされて処方されます:
• 鎮咳成分:咳を抑える
• 去痰成分:痰を出しやすくする
• 気管支拡張成分:呼吸を楽にする
• 抗炎症成分:気道の炎症を和らげる
⸻
鎮咳薬の成分(咳を抑える)
◎ 麻薬性鎮咳成分(中枢性)
成分名
コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩
| 特徴 | 延髄の咳中枢に作用し、強力に咳を抑える。ただし、眠気や便秘、薬物依存の恐れがあるため注意。 |
| 注意点 | ・12歳未満の小児には呼吸抑制の恐れ、使用禁止 ・妊婦・授乳婦には慎重使用(乳児にモルヒネ中毒) ・併用薬に注意(モノアミン酸化酵素阻害薬など) |
*咳止めシロップ:カップで1回分ずつ量って飲むタイプなどが売っていますが、知識のある中毒者が全量を一気に飲むという使い方をする危険性があります。大量購入や頻繁購入者には販売しないようお客様ときちんとコミュニケーションを取る様にしましょう。
◎ 非麻薬性镇咳成分
成分名
ノスカピン、デキストロメトルファン、チペピジン、クロペラスチンなど
| 特徴 | 咳中枢に穏やかに作用し、眠気や依存性が少ない。 軽い咳に用いられやすい。 |
気管支拡張成分
咳や喘息などで呼吸が苦しいときに、気道を広げて呼吸を楽にする成分です。
◎ アドレナリン作動成分
成分名
メチルエフェドリン塩酸塩、メチルエフェドリンサッカリン塩など
麻黄(エフェドリン含む)
| 特徴 | 交感神経刺激によって気管支を拡張し、呼吸を楽にする。 眠気は出にくいが、動悸や高血圧、血糖上昇、依存性に注意。発汗、利尿の作用あり。 |
| 注意点 | ・高血圧、心疾患、甲状腺機能亢進症の人は使用を避ける ・乳汁移行あり ・長期使用は避ける(依存・薬物耐性) |
◎ キサンチン系成分
成分名
ジプロフィリン
| 特徴 | 自律神経を介さず、気道の平滑筋に直接作用して気管支を拡張。 |
| 注意点 | てんかん患者の場合発作を誘発したり、甲状腺機能亢進、うっ血性心不全なども注意が必要です。 動悸やけいれんに注意。 |
 | 2025-26年版 登録販売者 合格のトリセツ テキスト&一問一答問題 (登録販売者合格のトリセツシリーズ) [ 東京リーガルマインド LEC登録販売者試験対策プロジェクト ] 価格:2860円 |
去痰成分・抗炎症成分・抗ヒスタミン成分の働きと注意点
⸻
去痰成分(痰を出しやすくする)
◎ 去痰薬の役割とは?
痰が粘り気を持つと気道に絡んで咳が出やすくなります。
去痰成分は、痰をサラサラにして排出しやすくすることで咳の原因を根本から取り除きます。
⸻
◎ 代表的な成分
| 成分名 | 働きと特徴 |
| グアイフェネシン | 気道粘液の分泌を促し、痰を薄めて出しやすくする。比較的穏やか。 |
| ブロムヘキシン塩酸塩 | 痰の粘度を下げて排出を助ける。痰が多い咳に適す。 |
| アンブロキソール塩酸塩 | ブロムヘキシンと同じく痰を出しやすくする。去痰力は強め。 |
| カルボシステイン | 粘稠度を下げ、粘液成分を調節する事により痰を外に出しやすくする。 |
| セネガ・キキョウエキス | 生薬由来。気道粘膜を刺激して分泌を促す。漢方との併用に注意。 |
抗炎症成分(気道の炎症を抑える)
◎ 気道炎症の原因
風邪やアレルギーなどにより、鼻や喉・気管支に炎症が起きると、腫れ・痛み・痰などの症状が現れます。抗炎症成分は、これらの炎症症状を抑えるために配合されます。
⸻
◎ 主な成分と注意点
| 成分名 | 働き | 注意点 |
| グリチルリチン酸二カリウム | 甘草由来。副腎皮質ホルモン様作用で炎症を抑える。 | 長期使用で偽アルドステロン症のリスクあり(むくみ、高血圧、低カリウム血症など) |
| トラネキサム酸 | 炎症性物質(プラスミン)を抑制。喉の痛みや腫れに使用される。 | まれに血栓傾向の人には注意。 |
| カンゾウエキス | 漢方と重複することも。甘草同様の抗炎症作用あり。 | 他剤との重複摂取に注意。 |
抗ヒスタミン成分(アレルギー・鼻水・くしゃみを抑える)
◎ アレルギー性鼻炎の仕組み
アレルゲン(花粉・ハウスダストなど)が鼻粘膜に付着 →
ヒスタミンが放出され、くしゃみ・鼻水・鼻づまりを引き起こす。
⸻
◎ 抗ヒスタミン薬の役割
ヒスタミンの働きをブロックすることで、
アレルギー症状(鼻水・くしゃみなど)を軽減します。
⸻
◎ 代表的な成分(第一世代)
| 成分名 | 働きと特徴 |
| クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 抗ヒスタミン作用+中枢鎮咳作用もあり、風邪薬にも配合される。 副作用:眠気、口渇、排尿困難など。 |
| d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 上記の光学異性体で効果が高く副作用は少なめ。 |
| クレマスチンフマル酸塩 | 持続時間が長く、眠気もやや強い。 |
| ジフェンヒドラミン塩酸塩 | 眠気が非常に強く、乗り物運転不可。鼻炎よりはかゆみ止めに多用。 |
◎ 使用上の注意
• 第一世代抗ヒスタミン薬は、眠気や注意力低下を起こすため、運転・機械操作はNG
• 排尿障害(前立腺肥大症など)、緑内障のある人は使用を避ける
• 妊娠・授乳中は医師と相談の上で使用
⸻
その他:補助的な成分
| 成分群 | 内容 |
| ビタミン類(B1、B2、Cなど) | 粘膜の健康維持、抗酸化作用で回復をサポート |
| 抗コリン成分(ベラドンナ総アルカロイドなど) | 鼻水・くしゃみを抑えるが、副作用強く一般薬ではほぼ使われない |
| セチルピリジニウム | トローチやドロップに含有する、消毒殺菌成分。 外部から効かせる形で飲み込まずゆっくり時間をかけて舐めて溶かす。 |